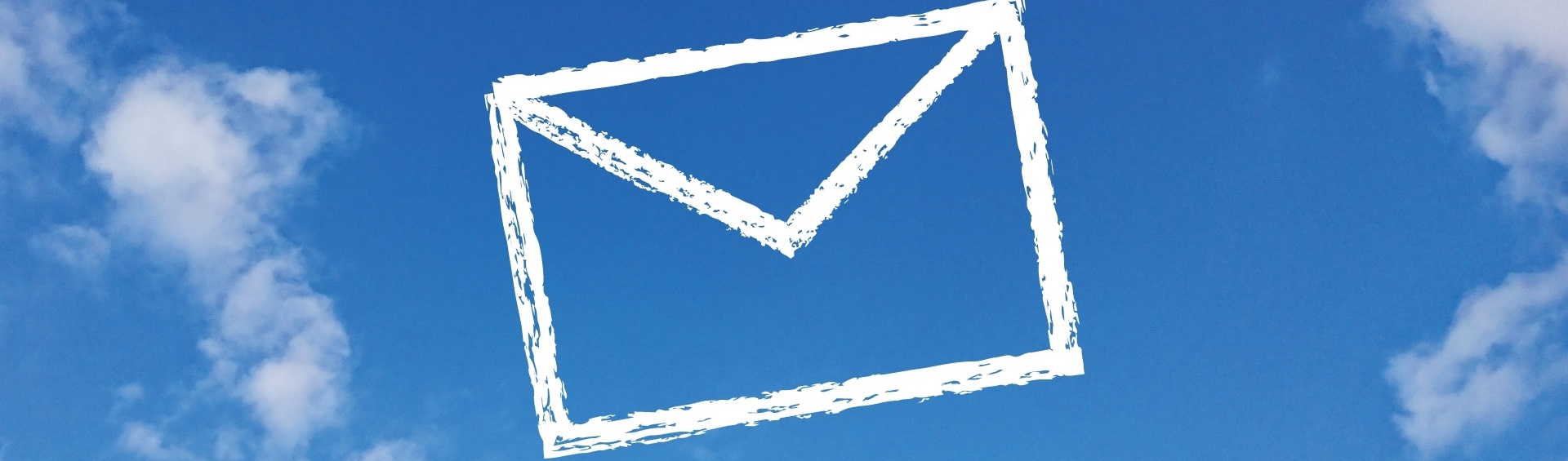目次
公害の救済法について
公害の救済法では、救済方法と共に救済対象が規定されています。また、救済の対象となる地域が特定されていることもあります。
これらの救済の具体的な内容に関しては、多くは、省令等の下部法令に委任されています。
代表的な公害である水俣病について見てみますと、水俣病被害者救済のために適用された法律としては、まず、昭和44年12月に制定された「公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法」(以下「救済法」といいます。)があります。
救済法は、水俣病以外にもイタイイタイ病、四日市ぜんそく等の他の公害被害も対象としたものでしたが、昭和48年6月に「公害健康被害の補償等に関する法律」(以下「公健法」といいます。)が制定(昭和49年9月施行)されると共に廃止されました。
更に、「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法」(以下「特措法」といいます。)が平成21年7月に制定され、同月に公布、施行されました。
ここでは、近時、訴訟上問題となっている公健法と特措法について考察を加えることとします。
公健法と特措法の相違について
まず、公健法と特措法の救済対象の相異についてみてみます。
公健法による水俣病公害被害者の救済は、水俣病に罹患している方への療養費、障害補償費等の補償給付をおこなうものです。
これは、公健法2条2項の「第二種地域」に該当する地域(水俣病に関係する地域としては、公健法施行令により熊本県の水俣市及び葦北郡の区域並びに鹿児島県では出水市の区域が指定されています。)において水質の汚濁の生じていた時期(水俣病公害が生じていた時期)、一定期間住所を有していた方(公健法4条2項の準用する同条1項1号ないし3号でその要件を定めています。)で、水質の汚濁の原因物質による疾患(公健法施行令により水俣病が当該疾患に指定されています。)に罹患していると認められる方の申請により、その該当性を都道府県知事が認定することにより、その認定者へ補償給付がなされるというスキームになっています。
つまり、水俣病公害の影響を受けた一定地域に、水俣病公害当時、一定期間居住していた方たちのうち、水俣病に罹患した方に対し補償給付をおこなうというものです。
そして、水俣病に罹患しているかの認定基準については、昭和52年7月1日に発出された環境省保健部長通知に示されています。
これは、一般には「52年判断条件」と言われており、この通知以降、公健法の認定に際しては52年判断条件が採用されています。
一方、特措法による救済は、特措法5条1項、2項からすると、(1)一定のメチル水銀の曝露を受けた可能性があり、(2)四肢末梢優位の感覚障害及び全身性の感覚障害を受けた方、その他四肢末梢優位の感覚障害を有する方に準ずる方といった、特定の症状を有する方に対し、一時金、療養費及び療養手当の支給(一時金は支給されず療養費のみの支給となる場合もあります。)という救済措置を講ずることにより、水俣病公害の被害者救済をおこなおうとするものです。
特措法の5条の救済措置方針を定めた条文の文言解釈からすれば、同法の救済措置の対象者は、メチル水銀に曝露した方達の内、一定の症状を有する方であり、水俣病公害被害地域に居住したことにより水俣病公害による一定の被害を被った方であり、「水俣病」患者の集合より広い範囲の方を対象としているとも読み取れます。
現に水俣病公害の原因企業であるチッソは、訴訟において、特措法は公健法により水俣病患者と認められていない方々を、地域における紛争を終結させ水俣病問題の最終解決を図るため、「水俣病被害者」として救済の対象としているのだと主張しています。
しかし、本来の定義通り、メチル水銀中毒症を水俣病と称するのであれば、中毒症状には軽重があることから、チッソが言うところの「水俣病被害者」の多くは水俣病患者ということになると考えられます。
この意味の水俣病患者には、上記(2)の症状を有する方も多いでしょうが、必ずしも水俣病患者全員が上記(2)の症状を有するとも言えません。
この意味の水俣病患者には症状の軽い方から重い方まで広く存在しますし、また、重症の水俣病患者の全てが(2)の症状を充たしていると断言できるほど「水俣病」に関する検診基準が確立されているわけでもありません(だからこそ、水俣病公害から半世紀以上たってからも、法廷において水俣病の病像論が争われ、国の主張が裁判において否定されることもあるのです。)。
メチル水銀中毒症であるところの水俣病患者の全てが、(2)の症状を必ずしも有しているわけではありません。
そうすると、論理的には水俣病患者の中には、(2)の条件を充たさず特措法の対象になり得ない方がいると言いうることとなり、水俣病に罹患していることを立証しても特措法の認定を義務付けることは出来ないこととなります。特措法の認定条件は(1)及び(2)なのですから、特措法の義務付け訴訟においては、立証の対象は、(1)及び(2)の該当性なのであり、水俣病該当性ではないからです。
義務付け訴訟の判断枠組みについて
次に、義務付け訴訟の判断のフレームワークをみてみます。
公健法の義務付け訴訟である平成25年4月16日の最高裁判決(以下同判決の事件の1審から最高裁判所までの訴訟事件を「F氏訴訟」ということとします。)では、
処分行政庁の判断の適否に関する裁判所の審理及び判断は,原判決のいうように,処分行政庁の判断の基準とされた昭和52年判断条件に現在の最新の医学水準に照らして不合理な点があるか否か(中略)といった観点から行われるべきものではなく,裁判所において,(中略)申請者につき水俣病のり患の有無を個別具体的に判断すべきものと解するのが相当である
最判平成25年4月16日
と判示されています。
この最高裁判所の判決については、「裁判所が処分行政庁と同一の立場に立って独自の判断を下し、これをもって行政庁の判断に置き換える判断代置型審査」(『最高裁判所判例解説民事篇(平成25年度)』p.241)により審理し判断を下していると捉えられています。
つまり、申請者が水俣病に罹患しているかを申請県の判定基準に捕らわれずに独自に判断をおこなうものとしているのです。
そうすると、F氏訴訟の最高裁判所判決の判断フレームワークからすると、裁判においては、原告の水俣病罹患性が立証対象とされているものといえます。
一方、水俣病被害の補償を損害賠償請求訴訟で求める場合も、損害賠償請求訴訟の因果関係の主な立証対象は水俣病罹患性です(損害の立証は別として)。
そうしますと、公健法の申請が認められなかった方が被害回復を訴訟手続きにより図る場合、義務付け訴訟と損害賠償請求訴訟のいずれを選択しても最重要争点及び最重要立証対象が水俣病罹患性であることは異ならないこととなります。
一方、特措法の救済対象者は水俣病患者ではなく、特措法の定める症状を有する「水俣病被害者」(水俣病患者ではない)なのですから、特措法の申請が認められなかった方が被害回復として訴訟手続きを取る場合、義務付け訴訟の立証対象は水俣病罹患性ではなく上記(1)及び(2)の該当性の問題となるものと考えられ、損害賠償請求訴訟を選択した場合に立証対象となる水俣病罹患性とは異なるものとなります。
勿論、特措法がその立法経緯から(1)及び(2)の該当性を充たさない水俣病患者も救済対象としていると主張していくことは可能でしょうが、特措法の救済対象の範囲を裁判により実質的に拡大するものとも考えられ、当該主張を裁判所に認定させるのは相当困難であるものと思われます。
ところで、F氏訴訟の控訴審では、「処分行政庁の判断の適否に関する裁判所の審理及び判断は・・・処分行政庁の判断の基準とされた・・・判断条件に現在の最新の医学水準に照らして不合理な点があるか否か(中略)といった観点」(F氏訴訟最高裁判決中控訴審判決について言及した部分)から審査をおこなっていますが、これは、「処分行政庁に要件裁量が認められ,裁判所が処分行政庁の判断に裁量権の逸脱・濫用があるか否かを審査する裁量審査判断」(前掲最高裁判所判例解説同ページ)を採用していたものと考えられています。
上記のように公健法の救済対象者は「水俣病患者」という救済立法以前に社会的事実として存在していた客観的に存在する水俣病患者全般を対象としているのに対し、特措法は、特定の症状を有する「水俣病被害者」という救済立法により新たに規定された特定の被害者の集合体を救済の対象としています。
このことからすると、特措法の義務付け訴訟が提起された場合、判断基準が立法上明文化されていることから、(a)検診に過誤があったか、(b)検診結果の特措法の基準である(1)及び(2)該当性の認定に誤りがあるかという点が、訴訟における判断対象となり、抽象的にどのような症状を有する方が特措法の救済対象になるかは、原則として、問題とならないものと考えられます。
F氏訴訟上告審では、判断代置型審査を採用する理由として、公健法の「認定自体は,・・・・客観的事象としての水俣病のり患の有無という現在又は過去の確定した客観的事実を確認する行為であって,この点に関する処分行政庁の判断はその裁量に委ねられるべき性質のものではない」という判断を述べています。
しかし、特措法の救済対象は、前述のように客観的事象として存在する公害病の該当性により画定されるものではなく、立法上で規定された要件の該当性により判断されるものなのですから、F氏訴訟の判断フレームワークによれば、特措法の裁判において判断代置型審査が採用される可能性は低いものと考えられます。
更に、前掲最高裁判所判例解説同ページでは、「処分要件の充足に係る処分行政庁の裁量,すなわち要件裁量を認め得るか否かについては,これを否定的に解する見解もあるが,最高裁判例及び下級審裁判例はこれを肯定している。」とも述べ、昭和53年10月4日の最高裁判所判決を引用しているように、裁判所は要件裁量を認めていると考えられています。
そうすると、上記のように特措法の義務付け訴訟においては、特措法の処分要件(上記(1)及び(2))が問題となることから、その審査においては裁量審査判断の対象となる可能性が高いものとも考えられます。
ところで、F氏訴訟の第1審では、取消請求については、「2 熊本県知事が昭和55年5月2日付けで原告に対してした原告の水俣病認定申請を棄却する旨の処分を取り消す。」、義務付け請求に関しては、「3 熊本県知事は,原告に対し,公害健康被害の補償等に関する法律4条2項に基づき,原告がかかっている疾病が,熊本県の区域のうち,水俣市及び葦北郡の区域並びに鹿児島県の区域のうち,出水市の区域に係る水質の汚濁の影響による水俣病である旨の認定をせよ。」との判決が下されています。
第1審では、判決理由中において、「公健法の下における『水俣病』とは,魚介類に蓄積されたメチル水銀を経口摂取することにより起こる神経系疾患をいうものと解するのが相当である。」とし、「水俣病にかかっていると認められるためには,経験則に照らして全証拠を総合検討し,当該申請者が水俣病にかかっていることが証明される必要があり,その判定は,通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ち得るものであることを要するものというべきである。」と判示しており、上告審と同様のフレームワークにより原告の主張を認容しています。
しかし、控訴審では、「被控訴人の水俣病認定申請棄却処分取消請求を棄却する」と一転して原告の請求を退ける判断を示しています。この違いは、判断のフレームワークとそれに基づく立証対象の差異からくるものとも考えられます。
更に損害賠償請求の因果関係に関する判断のフレームワークについて検討してみます。
損害賠償請求を求めた水俣病訴訟としては平成16年10月15日の最高裁判所判決(以下同事件の1審から上告審までの事件を「関西訴訟」といいます。)が有名ですが、関西訴訟の控訴審では、
いかなる症候があれば、メチル水銀中毒症と認められるかという問題である。この点について、原告らは、被告らが主張する病像は狭きに失するとし、後記のようなより広い病像を主張しているが、被告ら主張の病像で必要とされる症候を持つ者をメチル水銀中毒症と判断すること自体は争っていない
大阪高判平成13年4月27日
という事案で、
本判示において、『水俣病』ではなく、できるだけ『メチル水銀中毒症』あるいは『本件メチルに起因する症状』との文言を用いることとしたが、それは、『水俣病患者』という言葉が、ややもすると『(救済法あるいは、公健法において)認定された水俣病患者』の意味で使用されるので、本件がメチル水銀中毒による被害についての不法行為に基づく損害賠償請求事件であることを意識してのことである
大阪高判平成13年4月27日
とした上で、
本件で問題となっている病像論は、五二年判断条件とは別個に、被告チッソ水俣工場から排出されたメチル水銀中毒被害についての不法行為に基づく損害賠償請求事件であるから、前述のとおり、民事訴訟における被害の立証として、通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ち得る高度の蓋然性の証明は、いかなる知見、経験則に基づいてなされるべきか、また、メチル水銀中毒症によるどの程度の症状について、賠償請求が認められるべきかという問題ということになる
大阪高判平成13年4月27日
と判示し、52年判断条件と損害賠償請求における水俣病の認定基準は異なるという考え方を採用しています。
そして関西訴訟上告審でも、
昭和35年1月以降、チッソ水俣工場の排水に関して規制権限を行使しなかったことが違法であり、上告人らは、同月以降に水俣湾又はその周辺海域の魚介類を摂取して水俣病となった者及び健康被害の拡大があった者に対して国家賠償法1条1項による損害賠償責任を負うとした原審の判断は、後述のとおり、正当として是認することができる
最判平成16年10月15日
と判示し、控訴審の52年判断条件と損害賠償請求における水俣病の認定は異なるという考え方を維持しています。
このように、最高裁判所の判例からすると、義務付け請求あるいは損害賠償請求の因果関係のいずれにおいても、訴訟においては、52年判断基準ではなく、医学的見地から水俣病罹患の有無を判断することとなります。
原告が訴訟上主張・立証を要する事項について
これを前提にすると、訴訟においてどのような主張・立証をしていく必要が原告にはあるのでしょうか。
F氏訴訟上告審判決では、「水俣病のり患の有無を個別具体的に判断すべきものと解するのが相当」とされていることからすると、原告は、個別に医師の水俣病に罹患している旨の診断書を提出し、その診断書の証拠力を裁判所に判断してもらうようにも考えられます。
しかし、関西訴訟控訴審判決では、「第3 判断の根拠」において、
上記のようなメチル水銀中毒に起因する感覚障害に鑑み、メチル水銀化合物により汚染された水俣湾の魚介類を多量に摂取したことによる中毒性の神経障害を請求原因とする本件において、本件患者らが訴えている症状が被告チッソが排出したメチル水銀中毒に起因すると推認できる準拠を次のとおりとして誤りがないと考える。
大阪高判平成13年4月27日
として、
1 まず、当然ながら、水俣湾周辺地域において上記汚染された魚介類を多量に摂取していたことの証明がなされる必要がある。
2 次に、上記のようなメチル水銀によって生じる症状を考慮すると、いわゆるメチル水銀曝露に加え、次の三要件のいずれかに該当する者は、メチル水銀に起因する障害が生じている患者と認定してさしつかえない。
大阪高判平成13年4月27日
と述べた上で、当該三要素として、
(1) 舌先の二点識別覚に異常のある者及び指先の二点識別覚に異常があって、頸椎狭窄などの影響がないと認められる者。
大阪高判平成13年4月27日
(2) 家族内に認定患者がいて、四肢末梢優位の感覚障害がある者。
(3) 死亡などの理由により二点識別覚の検査を受けていないときは、口周辺の感覚障害あるいは求心性視野狭窄があった者。
という要素を列挙しています。そして、この判断を上告審も是認しています。
このように関西訴訟の判決からすると、水俣病罹患性の個別具体的な判断においても(ⅰ)水俣病罹患性の判断基準を定立し、その後に(ⅱ)個別の請求者(原告、申請者)の居住歴、症状等の当該判断基準充足性に関する判断をおこなうという2段階の過程(規範を定立しあてはめをおこなうという過程)を経て水俣病罹患の認定を裁判所はおこなっているということになります。
そうすると、原告は、52年判断条件に代わる医学的見地から相当な水俣病診断基準を証拠を基に提示し、原告が当該水俣病診断基準を充たしていることを検査結果、居住歴を証しする書面、人証等により立証していくこととなります。
立証課題の違いによる立証の容易性の相違について
続いて、立証課題の違いによる立証の容易性を比較してみます。
公害訴訟の義務付け訴訟において判断代置型審査が採用された場合、上記のように新たな判断基準を主張・立証していくこととなりますが、この立証は、裁量審査判断が採用され行政の判断に不合理な点があることを立証することより容易なのでしょうか。
(A)行政の判断基準が設定当時の医学的水準の標準的な診断基準と初めから異なっていた場合
(B)行政の判断基準は妥当であるが申請人の認定過程に瑕疵があった場合
(C)行政の判断基準が設定当時の医学的水準の標準的な診断基準と合致しており申請人の認定過程にも瑕疵はなかったが、その後の医学の進歩等により現在の医学水準における標準的な診断基準と異なったものとなっている場合
(D)行政の判断基準が設定当時の医学的水準の標準的な診断基準と合致しており申請人の認定過程にも瑕疵はなかったがいたが、経年による公害被害者の病状の変化により現時点では病状が異なったものとなっている場合
に分けて考えてみます。
まず、裁量審査判断の場合の「行政の判断の不合理性」については、水俣病訴訟で裁量審査判断を採用しているF氏訴訟控訴審判決においても、行政の判断過程に「看過しがたい過誤、欠落」があるか否かにより判断しており、民事訴訟における立証の程度より求められるハードルは高くなっていると考えられます。
そうしますと、一般論としては、判断代置型審査の方が裁量審査判断より立証は容易であると言えそうです。
しかし、(A)の場合、裁量審査判断においては、行政の判断に不合理な点があることを立証するには、判断基準に誤りがあることを主張すれば良く、正しい基準まで指摘する必要は必ずしもないことから、新たな判断基準を主張・立証するよりも容易なようにも思われます。
ただし、ある判断基準に不合理性があることを主張するには正しい判断基準を指摘する方が説得的です。
更に、公害訴訟の義務付け訴訟においては、行政の判断基準が誤っていることを指摘するだけでは義務付け請求の前提となる原処分の取消請求が認容されるに留まります。
結局、義務付け請求の認容のためには正しい基準を示し、その正しい基準を原告が充たしていることを立証する必要があることとなります。
そうすると、立証の程度の問題を別としても、裁量審査判断で行政の判断に不合理な点があることを立証する場合においても、新たな立証課題の立証が必要となると考えられます。
このことから(A)の場合においても、裁量審査判断の方が判断代置型審査より原告の立証が容易であるとは一概には言えないこととなります。
一方、(B)の場合においては裁量審査判断で行政の判断に不合理な点があることを立証するには、新たな診断書の提出等により、原告(申請者)の症状等が行政の判断基準を充たしていることを主張・立証していくこととなるのであり、新たな立証課題の立証が必要となるわけではありません。
一方、この場合の判断代置型審査においても新たな公害病罹患性の認定基準を定立するのではなく、原告(申請者)の症状等が行政の判断基準を充たしていることを主張・立証していくこととなります。
このように、(B)の場合では、いずれにせよ、原告(申請者)の症状等が行政の判断基準を充たしていることの主張・立証に尽きることとなることから、観念的には、立証程度の差異により、判断代置型審査の方が立証は容易であるということになりそうです。
しかし、このような場合、行政の判断基準を援用した際に判断代置型審査が取られるかは疑問であり、(B)の場合をここで検討するのは不適切なのかもしれません。
(C)の場合、現時点で行政が行政の判断基準を採用し続けている点をどのように評価するかが問題となります。
この点、F氏訴訟控訴審判決では、
公健法4条2項に基づく水俣病認定申請(本件申請)に対する棄却処分(本件処分)の取消訴訟における裁判所の審理,判断は,熊本県認定審査会の医学上の科学的,専門的な調査審議及び判断を基にしてされた処分行政庁(熊本県知事)の判断に不合理な点があるか否かという観点から行われるべきであって,現在の最新の医学水準に照らし,上記調査審議において用いられた具体的審査基準である52年判断条件に不合理な点があり,あるいは被控訴人の本件申請が52年判断条件に適合しないとした認定審査会の調査審議及び判断の過程に看過し難い過誤,欠落があり,処分行政庁の判断がこれに依拠してされたと認められる場合には,処分行政庁の同判断に不合理な点があるものとして,同判断に基づく本件処分は違法と解すべきである(最高裁昭和60年(行ツ)第133号平成4年10月29日第一小法廷判決・民集46巻7号1174頁参照)
大阪高判平成13年4月27日
と判示されており、(C)の場合にも不合理性が認定され得ることとなります。
ただし、救済法制定当時の医学的知見に準拠する基準を現在も採用し続けることに「看過しがたい過誤、欠落」があるとまで言いうるかは、ケースバイケースということになろうかと思われます。
一方、判断代置審査を前提とした新たな認定基準の主張・立証は、現在の医学的知見では比較的容易ということになります。
そこで、裁量審査判断で行政の判断に不合理な点があることを立証するのは、判断代置型審査での新たな立証課題の立証よりこの点からも困難であると言えそうです。
次に(D)の場合を考えるにあたり、まず、(D)がどのような場合に問題となるかについて述べます。
毒作用は毒性が現れる速さ及び時期により,
ⓐ短期間に急速に毒作用が生じる「急性中毒」
ⓑ反復して長期間に渡り毒と接触することにより毒性が徐々に生じてくる「慢性中毒」
ⓒ毒と接触しなくなってから何年か後に中毒症状が現れる「遅延毒性」
があります(Anthony T.Tu『中毒学概論』pp.3-4(薬業時報社、1999)参照)。
そして、それらの症状は同じ毒を原因物質とする場合でも異なることとなります。
水俣病公害が顕在化した昭和30年代に急性・劇症型のメチル水銀中毒症が水俣病として問題となったように、公害病では最初にⓐの急性中毒症が問題となります。
公害発生当初は公害病の原因物質に短期間に大量に曝露した場合に発生する急性症状が当該公害病と考えられ、公害病の判断基準も急性症状を基に決められます。
しかし、主に低濃度の原因物質に長期間曝露し続けた場合に発症する慢性中毒症、及び原因物質の曝露(特に低濃度の曝露と思われる)から相当期間経過後に発症する遅延中毒症は、公害発生から相当期間してからその存在が顕在化することとなります。
ところが、慢性中毒症も遅延中毒症も、公害の有害物質の曝露から発症するのですから、公害病なのですが、急性症状とは症状が異なることから急性症状を基に定められた判断基準には該当しないことがあり得ることとなります。
このような理由から生じる(D)のケースにおいて、慢性中毒症あるいは遅延中毒症の公害被害者は、行政の判断基準を充たさないこととがあることから、救済対象から除外されるケースが生じ、訴訟上の問題が生じ得るのです。
慢性中毒症あるいは遅延中毒症の公害被害者に行政の採用した判断基準を用いることが不合理であると言えるかは、救済法の救済対象の規定のされ方により異なることとなります。
水俣病の公健法のように公害病を救済対象としているのか、特措法のように特定の症状を有する者を救済対象としているかにより異なるからです。
後者の場合、そもそも当該救済法は慢性中毒症あるいは遅延中毒症の公害被害者を対象としてはいないことから行政の判断に不合理な点はないと考えることも可能です。
一方、前者の場合、当該救済法は慢性中毒症あるいは遅延中毒症の公害被害者も対象としていると考えることが出来ます。
そして、この場合、そもそも立法当時に想定していなかった慢性中毒症あるいは遅発性中毒症を救済の対象としなかったことが「看過しがたい過誤、欠落」とまでは言い得るかという点が問題となり得ます。
また、この点について「看過しがたい過誤、欠落」と言いうるとしても、(A)の場合と同様に、行政の判断に不合理な点があることを立証する場合、義務付け請求の認容判決を得るためには新たな立証課題の立証が必要となります。
そうすると、裁量審査判断で行政の判断に不合理な点があることを立証することが、判断代置型審査で新たな立証課題を立証することより、必ずしも困難であるとは言い得ないこととなります。
以上のことからすると、(B)の場合にはそもそも新な立証課題の問題は発生しませんし、(A)と(D)の場合には、裁量審査判断の行政の判断に不合理な点があることの立証と判断代置型審査の新たな立証課題の立証の容易性の比較の問題がそもそも発生し得るのかが不明であるといえます。
しかし、(C)の場合には、裁量審査判断で行政の判断に不合理な点があることを立証するのは、判断代置型審査で新たな立証課題を立証より困難であると言えそうです。
この結論はF氏訴訟の事件経過とも親和的です。
義務付け訴訟と損害賠償請求訴訟の選択問題
次に公害被害者が損害を回復するために訴訟を提起する場合、義務付け請求と損害賠償請求のいずれを選択するのが有利なのかを水俣病罹患性の立証という観点から検討してみます。
ここでまず考えなければならないのは、損害賠償請求においては因果関係以外にも、被告の損害賠償責任(違法性、過失)、損害額について主張・立証しなければなりませんが、義務付け訴訟ではそれらの立証は問題とはならないことです。
また、救済法による補償金額以上の補償を得ようと考えれば損害賠償請求を選択するしかないことも念頭に置いておかなければなりません。
これらのことを前提として、ここでは、義務付け請求の因果関係の立証と損害賠償請求の立証の容易性について、(1)行政の判断基準自体が公害病の病像論から誤りがあった場合
(2)行政の判断基準が現時点においても病像論に基づく公害病の診断基準と合致しており、具体的な診断にも誤りがなかった場合
(3)行政の判断基準が現時点においても病像論から導かれる公害病の診断基準と合致しているが、具体的な診断に誤りがあった(偽陰性の)場合
(4)行政の判断基準が現時点の病像論から導かれる診断基準より限定的なものとなっているが(現在の診断基準で認定される人の中に行政の認定基準では認定されない人が存在する)、行政の判断基準への適合性の認定には誤りがない場合
(5)行政の判断基準が現時点の病像論から導かれる診断基準より限定的なものとなっており(現在の診断基準で認定される人の中に行政の認定基準では認定されない人が存在する)、かつ行政の判断基準への適合性の認定にも誤りがある場合
に分けて検討してみます。
まず、(1)行政の判断基準自体が公害病の病像論から誤りがあった場合、義務付け訴訟においても現在の最新の医学水準に照らして不合理な点があることは明らかであり、義務付け訴訟の前提となる原処分の取消請求における不合理な点の立証に際し、新たな診断基準の立証は不要です。
しかし、訴訟の本来の目的である義務付け請求においては、当該公害病の病像論に基づく新たな診断基準を主張・立証を要することとなります。
そうしますと、結局のところ、義務付け請求においても、主張・立証責任の分配から、新たな公害病の診断基準の主張・立証を要することになることには変わりがないこととなります。
次に、(2)行政の判断基準が現時点においても病像論に合致した公害病の診断基準と合致しており、具体的な診断にも誤りがなかった場合は行政の判断に誤りがないこととなり、取消請求も義務付け請求も棄却されることとなります。
一方、損害賠償請求においても行政の判定基準と異なる基準を主張することは出来ないことから、具体的な認定(判定基準への症状のあてはめ)の段階において、行政と異なる結論を導けないと因果関係は認定されず請求は棄却されることとなります。
一方、(3)行政の判断基準が現時点においても病像論から導かれる公害病の診断基準と合致しているが、具体的な診断に誤りがあった(偽陰性の)場合は、新たな診断書を作成してもらい、行政の認定基準を充たしていることを主張・立証することにより義務付け請求が認められることとなります。
この場合、損害賠償請求においても、因果関係の存在に関しては行政の判断基準を用いれば良く、判断基準への該当性は新たな診断書により立証し得ることとなります。
したがいまして、因果関係の主張・立証の点においては、義務付け訴訟と損害賠償請求とは基本的には異ならないといえます。
(4)行政の判断基準が、現時点の病像論から導かれる診断基準より限定的なものとなっているが、行政の判断基準への適合性の認定には誤りがない場合は、立法上の救済範囲が公健法のように公害病患者となっているのか、特措法のように特定の条件を充たしたものとなっているかにより異なるものと考えられます。
前者の場合は、F氏訴訟の上告審及び第1審の判断スキームと同様に、公害病の新たな診断基準を主張・立証することとなり、損害賠償請求の因果関係の立証と同じこととなります。
一方、後者(救済範囲を特定の条件を充たしたグループと規定している場合)の場合、義務付け請求の前提となる取消請求は棄却され、義務付け請求は却下されることとなります。
しかし、損害賠償請求においては、公害病の新たな診断基準を主張・立証することにより、訴訟上で因果関係が認定され得ることとなります。
(5)行政の判断基準が現時点の病像論から導かれる診断基準より限定的なものとなっていますが、行政の判断条件への適合性の認定にも誤りがある場合も(4)の場合と同様、公健法のように立法上の救済範囲が公害病患者となっているのか、特措法のように特定の条件を充たしたものとなっているかにより異なるものと考えられます。
前者の場合は、判断条件の不合理性を主張する必要はなく、新たな診断書を提出して行政の判断基準に適合していることを主張・立証すれば良いこととなり、損害賠償請求の因果関係についても特に新たな診断基準を持ち出さず行政の判断条件に合致していることのみを主張・立証すれば良いこととなります。
後者の場合、明確ではありませんが、義務付け訴訟において救済立法の不当性を争うことは可能かもしれませんが、仮に救済立法の不当性を立証しえても、義務付け訴訟の認定には結びつかいないことから、請求は認められないこととなります。
一方、損害賠償請求では、公害病の新たな診断基準を主張・立証することにより、因果関係を訴訟上で認定され得ることとなります。
このような(1)~(5)の類型の検討を通じて分かるのは、行政の判断基準が現時点の病像論から導かれる診断基準より限定的なものとなっており、かつ判断条件への適合性の認定にも誤りがない場合、救済立法の救済範囲が公害病と定められていれば義務付け請求と損害賠償請求の因果関係の主張立証は重なるということです。
一方、特措法のように救済対象の要件が条文で規定されている場合、義務付け訴訟は困難で損害賠償請求を提起することとなります。
水俣病公害以外の公害の救済法に関する考察
それでは、その他の公害の救済法ではどのようになるのでしょか。
水俣病の場合、補償金の負担をするチッソの支払能力を考慮した上で政策的に救済範囲を措定し、その制約を充足するように水俣病該当性の判断基準(52年判断条件)を決めているといわれることもあります。
このように責任企業の財務力に救済範囲が制限されるということを単純に一般化することはできませんが、少なくとも責任企業、国及び地方団体の財政面の制約に一定程度の影響を受ける可能性が存在し得るとは言えます(財政的裏づけなしに公的補償はなしえません。)。
そこで、他の公害においても同様な問題は生じ得るものと思われます。
水俣病訴訟において国は救済措置の対象者の範囲を画する基準、つまり、救済措置の申請者の内、当該救済措置での救済対象者とする者と救済対象者としない者を区分する基準(水俣病救済措置の場合52年判断基準)を財政的側面も考慮して設定しているともいわれています。
その他の公害においても、どのような症状が認められる人までを当該救済措置の対象としての「立法上の公害病」に罹患した者と認定するかについて、財政的側面も考慮して決めている場合は、水俣病の救済法と同様な問題が生じ得ると思われます。
立法の救済法による被害者救済の限界
立法の救済措置による公害被害者の限界としては、このような(ⅰ)救済原資からくる制約の外にも(ⅱ)公害病患者と公害病未発症者の連続性、(ⅲ)誤診の問題等があります。
公害病は、特定の方達が生活する環境が公害原因物質に侵され、特定の地域に生活する人らが、その汚染物質に曝露し、その曝露により当該特定地域に生活する方達の身体に不具合が生じるものです。
その不具合が明らかに「病気」と言いうる程度に至っていれば比較的容易に「公害病患者」といいうると考えられます。
一方、その程度に至っていない場合、公害病患者とは容易に言い得ないかもしれませんが、少なくとも「公害被害者」とは比較的容易に言いうると考えられます(ここでは、人の公害被害についてのみ言及するため、特に断りのない限り、公害の被害者を人間に限定して論を進めます。)。
また、同水準の汚染物質の曝露歴のある人の間でも、個々人の耐性により身体に生じる不具合の程度は異なると考えられます。
更に、慢性公害病のように汚染物質の曝露が長期に渡ることがあり(比較的低濃度の曝露の場合にこのような曝露が問題になると思われます。)、その場合、身体の不具合は正常な状態から病的な状態へと不連続ではなく連続的に生じる可能性があると考えられます(この点、国らは曝露状態(水俣病の場合、メチル水銀の体内摂取量)が閾値(一定水準)以下の場合は水俣病を発症し得ないと主張していますが、国らは「水俣病」とは一定の症状が一定水準で現れている状態であると想定していると考えられます。そうすると、国の主張はトートロジーともいえます。)。
また、遅発性の公害病が想定される場合、公害病を発症するトリガー(公害病を発症し得るだけの汚染物質の曝露)が引かれながらも公害病を発症していない時期を観念し得ることとなりますが、この時期は病像論からは、公害病に罹患していないとも言いうることとなります。
更に、同量の曝露に晒された人の間でも、個々人の人体への影響は異なるものと考えられます(耐性の個人差)。
これらのことを考えますと、疫学条件を重視した救済条件を設ける場合、そのハードルを発生している症状が「公害病」にまで至ったレベルに設定するか、あるいはこれらの「公害病」と「公害病」至る前の「公害被害状態」の生じている方を一定の割合で含むレベルに設定するかの問題が生じます。
一方、時系列で公害病の推移を考えると、外観的な公害病の発症前の「公害被害者」を救済の対象にするか否かが救済措置の申請期限との関係で問題となり得ることとなります。
上記の連続性からくる問題はの解決としては、公害被害者の救済という観点からすると、全ての被害者をもれなく救済するためには認定基準を全ての被害者が対象となるように緩和すれば良いとも言えます。
しかし、救済の原資が税金により賄われるとすれば、「公害病」に至らない人まで救済の対象となることに対し、公平の観点から問題が生じ得ます。
仮に公害被害企業に救済の原資を負担させるとしても公平の観点から問題は生じ得ます。
このことからも、公害病を発症していない者を当該救済措置の対象とすることを可能な限り回避する方向で認定基準を設けることとなります。
つまり、救済措置の対象範囲の認定は、原資の調達の限界という予算上の制約を内包していることから抑制的となり、公害病に至らない公害被害者のみならず公害病に罹患しながら救済措置の対象から外れる者の層が存在することとなるのです。
また、本来であれば立法による救済措置の対象者となっているにも関わらず診断をおこなう医師の誤診により救済対象外と診断される(偽陰性)一定程度の公害被害者の発生が不可避です。
このように、立法の救済措置による公害被害者全員の救済は、制度上から困難なものであり、救済措置により被害の金銭面での回復を成し得ない方が一定範囲で生じ得ることとなります。
つまり、救済措置の認定基準を充たさない公害被害者のみならず、救済措置の認定基準を充たさない公害病に罹患している被害者も存在し得ることとなるのです。
このようなことからすると、公害訴訟において立法による救済措置の対象外とされたものが、司法により救済を求める場合、(A)誤診により認定されなかった方は元々救済措置の認定基準を充たしているのであるから、その認定基準該当性を主張・立証することにより義務付け請求が認められ、訴訟を通じて損害の回復が可能となります。
一方、(B)元々認定基準に該当しない公害病患者、あるいは公害被害者が義務付け訴訟で損害を回復するには、F氏訴訟の判断枠組みのように公害病患者と認定基準を別のカテゴリーと捉えるのであれば、公健法のように抽象的に公害病患者を救済対象としている場合には、行政の認定基準と異なる基準を定立し、申請者がその定立した基準を充たしていることを立証すれば良いこととなります。
しかし、特措法のように条文上規定された認定基準を充たすものを救済対象と定めているような場合には、当該認定に誤りがないこととなり、救済措置の対象から外れた者が当該救済措置の判断基準に該当することを立証することは困難ということとなります。
一方、損害賠償請求訴訟であれば行政の採用する判断基準との抵触は理論上は回避し得ることとなります。
このように、公害の救済立法の救済対象の規定の仕方により公害被害者の被害回復に向けた裁判上取りうる訴訟類型は異なるものといえます。