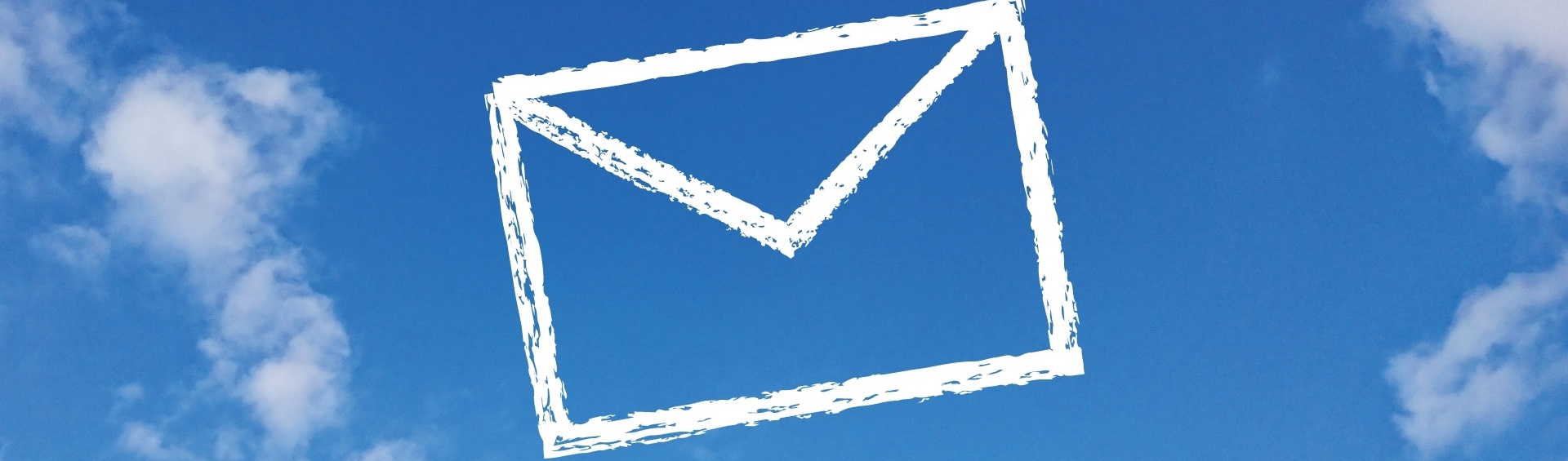目次
残雪の八ヶ岳縦走遭難事件の概要
事故の概要について
まず、商業ツアーの登山事故の中でも、損害賠償請求権の存否の検討が比較的容易な、ⅱ)残雪の八ヶ岳縦走遭難事件をみてみます。
この事件は、静岡県の団体が主催し30名程度が参加した、昭和48年4月末の残雪期の八ヶ岳を麦草峠から編笠岳を経て小淵沢へ縦走するツアー(前日車中泊、赤岳石室(現:赤岳展望荘)1泊予定)において、4月29日午後、横岳稜線付近で20歳代の方が登山道から滑落あるいは転落して死亡したものです。
この事故の被害者は、硫黄岳方面から赤岳方面へ向かう途中、横岳の主峰を越え鉾岳の手前の稜線から行者小屋側(茅野側)へ鎖を使って下降した後、水平にトラバースする積雪のある登山道を通過中、滑落あるいは転落しました。
この年は、例年に比べ積雪が多く、滑落による死亡等の遭難事故が多発していたことから、県警本部を含む長野県の各団体より警告が出ているような状態でしたが、事故発生時、被害者はアイゼンを装着していませんでした。
季節を問わず八ヶ岳を縦走したことのある方はお判りになるかと思いますが、車中泊明けで麦草峠から赤岳展望荘まで1日で縦走するのは結構大変です。
とくにゴールデンウイークはじめは、麦草峠~高見石~中山峠、および夏沢峠手前の樹林帯には残雪のある可能性は高く、残雪の踏み抜きがあれば更に体力・気力が奪われます。
また、根石岳付近および硫黄岳~横岳は風が強いのが常態です。
事故発生日も、参加者に疲れが見え、硫黄岳石室(現:硫黄岳山荘)で宿泊しようという話が出ていたようです。
計画上、事件の翌日、地蔵の頭近くの赤岳石室から赤岳山頂を越え、キレット~権現岳~編笠山を経て小淵沢へ下山することとなっており、時期的に考えても当該ツアーは相当程度の体力のある、経験者向けのものと言えます。
このように、参加者の登山レベルからすると日程的な問題もありますが、この事件で最も問題だと思われるのは、参加者の多くがアイゼンを持参していなかったという点です。
被害者は一応アイゼンを持参していましたが、未装着のままで死亡しています(尚、当時も稜線からトラバースの登山道へ下降する岩場には鎖が張られていたようですが、事件現場であるトラバース箇所には鎖、ロープは張られておらず、主催者もロープを出しておりませんでした。)。
尚、被害者が持参していたアイゼンも4本爪の軽アイゼンであり、計画されていたルートを縦走するにふさわしいとは言い難いものでした。
翌日も赤岳をキレット方向へ向かう計画となっていたことから、多くの参加者は赤岳~竜頭峰付近もアイゼン未装着で通過する予定となっていたこととなります。
このような、登山計画を立てながら、主催者の職員であるツアーリーダーは、参加者からの事前の問合せに対し、ピッケル・アイゼンは不要と回答しています。
もちろん、昭和48年当時の登山装備および技術事情と、今日のそれとを同視することは出来ませんが、雪の多い年のゴールデンウイークはじめにアイゼン未装着でピッケルもなしに、横岳および赤岳のトラバースルートを通過するのは相当な危険があることは確かです(今日では、一般の登山者でアイゼンを持参せずに、当該時期に、当該ルートを通過する登山者は大変稀だと思われます。)。
裁判所の判断
この事故では、死亡した人の親が、同行したツアーリーダーを務めた主催者の職員、主催者団体、主催者団体の代表者個人および主催者団体でツアー事業を掌握していた職員に対し、損害賠償を求め訴訟を提起しました。
その裁判では、上記のように事前のツアー計画にも相当な問題があったこともあり、当日の具体的な行為と考え併せ、ツアーリーダーを務めた主催者の職員には過失が認定されています。
少し長くなりますが、判決文の過失認定箇所を引用します。
尚、判決引用部分の甲は主催者団体、乙は甲の職員であるツアーリーダー、Aは被害者となっています。
参加者を募集して残雪期に標高二九〇〇メートルに近い八ケ岳登山を企画、実施する者としては、参加者らの装備、技術、経験及び体力等に相応した登山コースを選択し、日程を組まなければならないことは当然のことである。しかしながら、以上に認定した本件登山のコース、日程、参加方法等をみると、本件登山は右のような点を検討して企画されたものであるとはいえないのであつて、参加者らが相応の装備、技術、経験及び体力等をもつ者であれば格別、これらの劣る者が参加するときは、前記春山情報の指摘にあるような残雪期の登山に伴う滑落等の遭難事故が発生する蓋然性の高い企画内容であつたといえる。本件登山は・・・甲が主催し、参加者が・・・登山コース、日程等を承知したうえ自主的に参加した登山であるとしても、その参加者は広く・・・法人又は個人事業所の従業員や一般個人であつて、当然には一定水準の登山技術、経験及び体力や必要な装備等をもつ者が参加すると期待できないのであるから、被告甲は本件登山を企画、実施するに際して責任のある相当の登山経験、技術を具えた者にこれを担当させるべきであり、その担当者は参加申込者に対し右装備、技術、経験及び体力等の有無を審査し、不適当な者の参加を拒絶するとともに、参加を許した者に対し登山計画の具体的内容及び八ケ岳の状況等を説明し、必要な指示、助言を与えるなどして十分な登山準備をさせたうえ、登山中の参加者らの状態、動静を十分掌握できる体制を作り、山の気象状況にも留意し、慎重に登山を実施すべきである。更に登山中リーダー等は装備、技術、経験及び体力等の劣る参加者の動静に関心を払い、特に危険箇所を通過する際にはその者の動静を十分注視し、かつ同人が危険の意識を欠くときには注意を喚起し、安全な通過方法を指示し、場合によつては助勢する等適切な措置をとつて、参加者の安全を確保する注意義務があるものといわねばならない。
静岡地判昭和58年12月9日
と注意義務の内容を明らかにした上で、
しかるに、被告乙は、前記のとおり参加者の装備、技術、経験及び体力等を検討せずに本件登山を企画し、本件登山が滑落等遭難事故の発生する蓋然性の高い企画内容であつたにもかかわらず、装備の点で明らかに不適当な者一名の参加を拒否したものの、Aを含め装備、技術、経験及び体力等の劣る者を相当数本件登山に参加させ、また参加者らに対し登山計画の具体的内容を説明しなかつたし、必要な指示助言を与えなかつた。そのため、被告乙は参加者らに対し装備、心構え等の点につき十分な登山準備をさせることなく本件登山を実施し、また登山中の参加者らの状態、動静を十分掌握できる体制を作らず、参加者らにとつて多少ともコース、日程に無理のある本件登山を強行して本件事故直前頃はAを含む参加者に相当疲労した者が出てきたのにその認識を欠き、本件事故現場の道を渡り切つた附近で順次鎖場を約三、四〇メートル下降したうえ本件事故現場を通過して来る参加者らを待つていただけで、Aが同様にして鎖場を下降し、眼鏡をはずしたまま前記のように危険箇所である本件事故現場を通過しようとしたにもかかわらず、同所を通過し終つた者に気をとられAの動静を注視していなかつたため、Aに対し注意を喚起したり、安全な通過方法を指示することができず、同女に対する安全確保の義務を怠り、よつて、Aをして本件事故現場を通過中前記のとおり滑落させ死亡するに至らしめたものというべきである。
静岡地判昭和58年12月9日
と具体的な注意義務違反行為および因果関係を認定した上で、
したがつて、被告乙は原告に対し、民法七〇九条に基づき、本件事故により生じた損害を賠償する義務がある。
静岡地判昭和58年12月9日
と乙に対する不法行為に基づく損害賠償請求を認容しています。
ここでは、判例の引用部分において、乙の注意義務およびそれに違反する行為(注意義務違反行為)を相当程度具体的に示している点に留意していただきたいと思います。
下記の記事で扱っています、平成12年3月の文科省登山研修所冬山研修会での大日岳雪崩遭難事故の裁判においても、注意義務および注意義務違反行為を相当具体的に認定しています。
登山事故における過失の認定について
過失について
ところで、法的な観点を捨象してⅱ)の事件を俯瞰してみますと、ある程度登山経験のある方は、このツアーは、参加者の属性、行程、装備等から問題が多いものであったとの印象を持たれるものと思われます。
しかし、その「問題が多い」という漠然とした印象から、過失の認定をすぐに導きだすことはできません。
不法行為責任を定める民法709条の「過失」のような法律要件(法律の条文で定められた一定の法律効果(ここでいえば損害賠償請求権の成立)を導くために要求される前提条件)は、実際に発生した事実ではなく、発生した事実に対し一定の法的評価を下した規範的要件と言われるものです。
過失の主張・立証について
そこで訴訟上、裁判所に過失を認定してもらうためには、単に「被告には『過失』があった」と主張するだけでは足りません。
具体的な過失行為を特定し、その具体的な過失行為を裁判上主張、立証していく必要があります。
その過失行為の主張としては、当該事件において被告に求められる具体的な注意義務を措定し、その注意義務に違反する行為を特定します。
ⅱ)の事件においても、原告は、乙にいかなる注意義務が存在し、乙がその注意義務に反する行為をおこなったかを漠然とではなく、具体的に訴訟で主張しています。
ここで、問題となるのは、訴訟では具体的な注意義務違反行為だけではなく、その事件における具体的な注意義務の存在に争いが生じ得るということです。
過失の存在に争いがある場合、訴訟上では
(a)法的に具体的な注意義務が存在するか(存在したか)
(b)(a)の具体的注意義務に反する(作為)行為あるいは不作為行為(行為をしないということが「不作為(行為)」とされます。たとえば、信号無視で交通事故が生じた場合、信号を確認する行為をしないことが不作為行為となり得ます。)の存否
の2点で争いが生じ得ます。
もちろん、(b)の作為行為、不作為行為は、ツアーリーダーを務めた主催者の職員に課された注意義務に反する行為のことですから、一定の法的評価を含むこととなり(たとえば、その人に求められている救護行為をしない不作為(行為)が救護義務違反となりますので、救護義務違反に該当する不作為行為は、その人に求められる救護行為の範囲により決まってくることとなります。そして、その人に、どこまでの救護行為が求められているかは一定の法的観点に基づくものであることから、結局、救護義務違反の不作為行為は一定の法的評価を含むこととなります。)、具体的行為が注意義務違反行為に該当するかについては法的な問題は生じ得ます。
しかし、実際には、(b)注意義務違反行為に該当するかという争いは、法的には作為義務では問題となりますが、不作為行為ではあまり問題となりません。
何故なら、不作為行為としての注意義務違反行為は、注意義務が課せられた行為をおこなわなかったことなので、当該行為を行ったか否かという事実の争いは生じても、法的な問題にはあまりならないからです。
もちろん、ある程度義務行為をおこなったが、求められる注意義務の程度にいたっていなかったと評価されるかについて争いが生じることもあり得ます。
しかし、その場合、注意義務の解釈の問題として(a)の注意義務の程度の問題として処理されることが多いと思われます。
ツアー登山事故の裁判においては、主にツアーリーダー、およびその他の参加者が、求められているなんらかの行為をおこなわなかったという不作為行為が問題となり、注意義務違反行為をおこなったかという作為行為の問題は多くの場合は生じません。
そこで、裁判では、(a)法的に具体的な注意義務が存在するかが主に争われることとなります。
ⅱ)の事件においても、原告の、
被告乙は、本件事故現場が前記のように危険な場所であつたのであるから、Aを含む参加者らがそこを通過するに際して同所に滑落防止のためのザイルを張るとか、アイゼンを持参していたAに対しその着装等を指示し、その他適切な注意、指導を与えるなどして同所を安全に通過させるべき注意義務があるにもかかわらず、Aに対し右のような安全確保のための措置を怠つた過失がある。
静岡地判昭和58年12月9日
との具体的な主張に対し、被告らは、
本件事故現場の道はほぼ水平であり、湿つた雪で覆われ、路面は積雪を踏み固めた状態であつたが、特に滑り易い場所ではなかつた。したがつて、同所の通過にアイゼンの着装は必要なく、通常の登山技術を有する者であれば無事通過しうる場所であつた。
静岡地判昭和58年12月9日
と主張して、原告が主張する注意義務の存在について争っています。
登山事故の裁判における立証の問題
裁判では、原告が具体的な注意義務の存在について主張、立証する必要があります。
しかし、ツアー登山の場合、主催者側の方が、登山に関する知見が豊富な場合が多く、原告の立証は困難を伴うことも少なくはありません。
この問題は、登山事故のみならず、その他の損害賠償請求事件においても同様に生じ得るものです。
それでは、具体的な注意義務の存在について争いがある場合(原告も当該注意義務の存在を認めていれば、原則として、立証の必要はありません。)、どのように立証していけばよいのでしょうか。
人証について
まず、証拠には、大きく分けて人証と書証があり、人証は主に証人尋問の形で裁判の場に顕出されることとなります(実際には証人尋問に先行して、証人の証言内容を陳述書という書面にまとめて提出し、証人尋問の場では、その陳述書を基に証人尋問がおこなわれます。)。
この人証を立証の柱とする場合、証人の人選が証拠力、裁判官の心象形成に大きくかかわってくることは否定できません。
しかし、この人選も、要証事実である当該事件における注意義務の内容の立証に、誰が最も適切かという観点から考えることとなります。
たとえば、ⅱ)の事件でラインホルト・メスナーを証人として招聘しても(無論時代が違いますが、その点はさておき、)あまり適切とは思われません。
そもそもメスナーは八ヶ岳の事件現場の状況を知らないでしょうし、ⅱ)の事件のツアー参加者の技術水準を知悉しているかもわかりません。
当該地域の地形および登山事故状況に造詣の深い山小屋関係者、山岳救助関係者等の方が、メスナーより証人としては適切かと思われます。
書証について
しかし、実際には、このような人証に先行して、各種の書証を提出することとなります。
ツアーの主催関係者、あるいは参加者が参考にするであろう登山書、および登山関係団体が公開している情報(今日ではホームページの記事)を中心として、書証を提出することを検討していきます。
実際に、ⅱ)の判決でも、
長野県山岳遭難防止対策協会、同県教育委員会及び同県警察本部発行の昭和五三年春山情報には、春山登山でも天候が悪化すれば冬山と同様であり、登山の装備、日程、心構えは厳冬期登山と同じようにすること及び春山遭難の一番の原因は雪上スリツプであつて、雪上における基本的な技術、特にピツケル、アイゼン等の正しい使用方法を身につけることが事故防止の第一歩であることを指摘し、八ケ岳連峰の状況については、積雪が一ないし1.5メートル、殊に沢筋では二、三メートルもあり、雪上スリツプを起し易い危険箇所として横岳の稜線、赤岳石室から地蔵尾根に至るコース及び文三郎新道を挙げており、市販の八ケ岳ガイドブツクにもほぼ同趣旨の記事が掲載されている。
静岡地判昭和58年12月9日
として、県諸団体の春山情報、市販の八ケ岳ガイドブツクなどの書証を、過失認定に際し引用しています。
使用者および代理監督者の責任
主催者団体および関係者の責任
このように、主催者の職員であり、ツアーリーダーでもあった乙個人には過失が認定され、乙に対する損害賠償請求は認められています。
更に、主催者団体甲および主催者団体においてツアー事業を掌握していた職員(以下「丙」といいます。)に対する損害賠償請求も認められましたが、主催者団体の代表者(以下「丁」といいます。)への請求は棄却されています。
使用者責任について
本件ツアー登山が甲の事業の執行として行われたものであることには争いがなかったことから、乙に対する不法行為責任が成立する以上、原告の甲に対する使用者責任が認められたのは当然と言えます。
尚、民法715条1項但書から、乙の選任、監督における過失の不存在を甲が証明すれば甲は免責されるように思われます。
しかし、実際には、同項但書が適用されることはないと考えられており、本件でも同項但書の適用は否定されています。
代理監督者の責任について
一方、丙および丁に対し、原告は民法715条2項の代理監督者としての責任に基づく損害賠償を求めました。
しかし、裁判所は、丙に対する請求は認めたものの、丁に対する請求は棄却しています。
裁判所の丙および丁に対する判断が異なった理由は、判決中で明確になっていますので、判決の丙および丁に対する責任について触れた部分を引用します。
まず、丙の責任に関しては、
本件事故当時丙が甲(の)事務局長として甲の職員を選任、監督し、甲に代つて事業を監督する者であつたことは当事者間に争いがないから、丙は原告に対し、民法七一五条二項に基づき、本件事故により生じた損害を賠償する義務がある
静岡地判昭和58年12月9日
と判示しています。
一方、丁に関しては、
本件事故当時丁が甲(の)会長であつたことは当事者間に争いがない。原告は、丁が本件事故当時甲に代つて事業を監督する者であつたと主張するけれども、民法七一五条二項にいう代理監督者とは、客観的にみて、使用者に代り現実に事業を監督する地位にある者を指称するものと解すべきであるところ、丁及び丙各本人尋問の結果によれば、丁は被告の総会及び理事会を招集し、その議長となるなど甲(の)会則に定められた形式的な業務を担当しているが、職員の選任、監督等事業の執行及び監督はすべて事務局長である丙が行つていたことが認められるから、丁は右条項にいう代理監督者であるということはできず、他に右原告の主張を認めるに足りる証拠はない。したがつて、丁が代理監督者であることを理由に同被告に対し本件事故による損害賠償を求める原告の請求は失当である
静岡地判昭和58年12月9日
としています。
この丁の判断に関する部分から明らかなように、民法715条2項の代理監督者としての責任の認定に際しては、使用者に代わり、実際にツアー企画者およびツアーリーダーの業務を監督する地位にあったか否かを、実質的に検討することとなります。
この事故においては、丙は業務として乙の監督を実質的におこなっていました。
一方、丁は甲のツアー登山を含む日常業務にはタッチしていません。
この違いから、丁は代理監督者に該当しないと認定されたものと思われます。
このように、ツアーリーダーに不法行為責任が認められた場合、そのツアーが業務上のものであれば、使用者が責任を免れることは困難ですが、組織上監督的な立場にある者に関しては、その中でも実質的な関与を認定できる者のみが代理監督者として損害賠償責任を負うこととなります。
報償責任について
被用者(この場合主に乙)が損害賠償責任を負う場合、直接過失行為をおこなったとは言い難い使用者と代理監督者も損害賠償責任を負うのは、一般的には報償責任に基づくものであると考えられています。
この報償責任は、使用者は被用者を事業に用いることにより利益を得ていることから、当該事業から生じる損失も負担すべきであるという考え方(報償責任)、および使用者が社会に対して当該事業に内包する危険を作出していることから、当該危険が具現化した場合は、損害を負担すべきであるという考え方(危険責任)に依拠するものと考えられています。
しかし、同じ報償責任に基づくものでありながら、本件では、使用者である甲に対しては簡単に使用者責任を認定しながら、組織上、ライン上の上位にいる丙および丁の責任に対しては実質的な審理を加え、丁に対する責任を否定しています。
雇用契約から、甲乙間の使用関係は明確であり、甲に関しては形式的に使用者責任を認定しえます。
一方、丙および丁に関しては、乙との関係が契約上明確というわけではありません。
そこで、丙および丁に関しては、代理監督者に該当するかを実質的に判断する必要があったと考えられます。
従いまして、
- ツアー登山の企画・募集において多重に複数の組織が関与しているような場合
- ツアーリーダーとツアーの企画・運営者の間の契約が、単純な雇用契約ではなく、請負契約などの形態となっており、使用関係が明確とはいえない場合
においては、使用者責任に関しても実質的な判断を要するケースがあり得ると考えられます。
本件は、過失の内容が単純でわかりやすく、また、主催者およびその関係者の責任を理解するのに役立つものであることから、ツアー事故の法的責任の考え方を整理するのに役立つと考え、最初にこの事故を取り上げました。