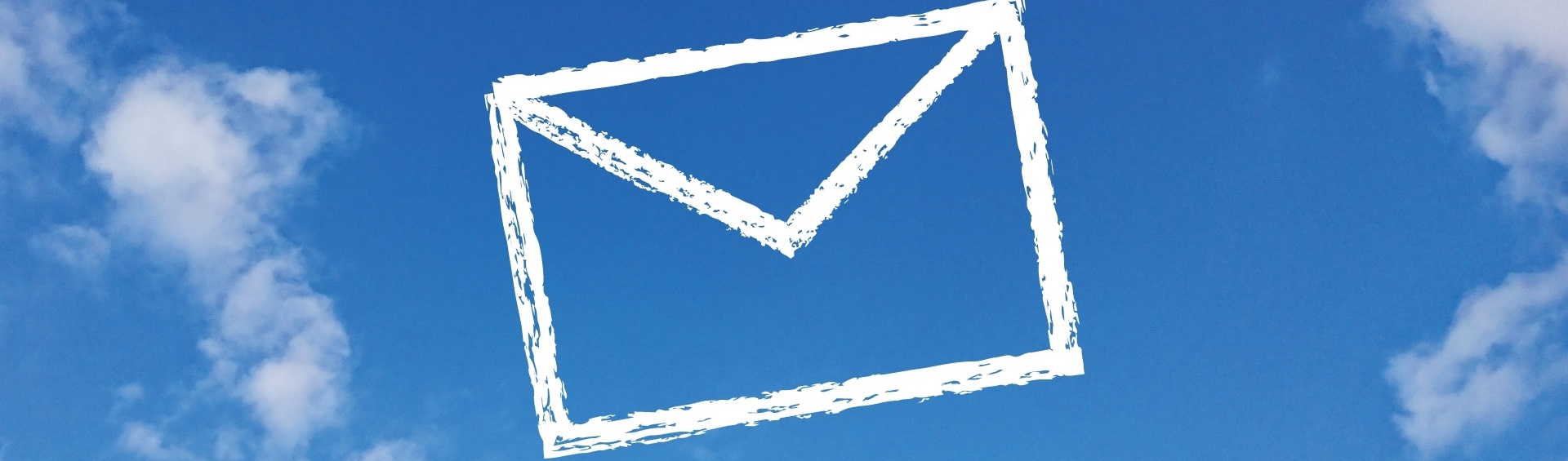目次
積丹岳遭難事故の概要
ここでは、11)積丹岳遭難事故についてみていきます。
この事故の発端となった遭難事故は、1月末の積丹岳にバックカントリーでのスノーボードおよびスキーを目的に入山した3人(内、被害者(以下「A」といいます。)はスノーボード、他の2人(以下「B」および「C」といいます。)はスキー目的)の内、Aが積丹岳山頂(付近)まで登頂した後、吹雪のため下山道を見失い、山頂から高度で70~80m位下った地点においてツェルトでビバークしたものでした。
この時、天候が悪化していたためヘリコプターでの捜索・救助は困難であったことから、地上からの救助となりました。
遭難者は、救助に向かった警察の救助隊(警察官である隊員5名、以下小隊長を「乙」、分隊長を「丙」、残りの隊員を「丁」「戊」「己」といいます。)に翌日の正午頃発見され、隊員に脇を抱えられるようにして下山を開始しました。
しかし、下山開始直後に雪庇を踏み抜きAは救助隊員と共に滑落しました。
そこで、救助隊は、滑落地点からAをストレッチャーで稜線へ吊り上げようと試みましたが、吊上げ作業が難航したため、途中、一時的にストレッチャーをハイマツに結びつけ確保することとなりました。
その確保後、救助隊員がストレッチャーから一時離れたのですが、その離れた間に、ハイマツからストレッチャーが離脱し、ストレッチャーごとAは滑落し、凍死することとなりました。
尚、Bの証言によりますと、Aは冬山経験豊富で、冬の積丹岳ははじめてではあったものの、積丹岳の雪崩研究会の講座に数回出席していたこと等もあり、冬の積丹岳の状況については詳しかったとのことでした。
積丹岳遭難事故の裁判について
この事故後、Aの遺族は、救助隊員の属していた警察本部が所属する地方公共団体(以下「甲」といいます。)に対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求め提訴しました。
1審判決
この11)積丹岳遭難事故の1審(札幌地判平成24年11月19日)では、まず、
救助隊員の救助活動は、警察官の職務の一環として行われているのであるから、純然たる私経済作用といえないことは明らかなので、国賠法一条にいう「公権力の行使」に当たる
札幌地判平成24年11月19日
として、救助活動が公権力の行使であると認定しています。
その上で、
個人の生命、身体及び財産の保護に任じることなどを警察の責務と規定する警察法の・・・規定や、要保護者を発見した場合に応急の保護をすべき事を定めた警察官職務執行法の規定・・・に照らせば、山岳救助隊員として職務を行っている警察官が遭難者を発見した場合には、適切に救助をしなければならない職務上の義務を負うというべきである
札幌地判平成24年11月19日
として、救助隊員に救助義務があったことを認定しています。
ここでは、警察の救助隊員に救助義務が存在することの理由付けとして、警察法および警察官職務執行法を引用しています。
このことからしましても、救助者が、①警察官・消防隊員等の公務員の場合と、②遭対協、山小屋関係者等の民間人の場合では、救助義務の存否およびその程度が異なると考えられます。
続いて、山岳救助、とくに冬山での救助においては、遭難者の置かれた具体的状況およびその変化を、十分な時間をかけることなく現場で判断せざるを得ないことなどを指摘した上で、
適切な救助方法の選択については、実際に救助に当たる救助隊員に合理的な選択が認められているといわざるを得ず、救助を行う際の救助隊員及び遭難者が置かれた具体的状況に照らし・・・その時点において実際にとった方法が合理的な選択として相当であったといえるか否かという観点から(救助活動が国賠法上の違法な行為に該当するか)検討するのが相当
合理的と認められる救助方法を選択しながら結果的に救助に失敗したとしても・・・国賠法上違法と解することは相当でない・・・違法と評価されるためには・・・具体的状況に照らし、明らかに合理的と認められない方法をとったと認められることが必要・・
札幌地判平成24年11月19日
と判示した上で乙~己の具体的行為について過失が認められるかについて検討しています。
救助隊はA発見後、往路を戻ることをせずに、Aの捜索時に雪上車が9合目まで到達していることを確認していたことから、この雪上車へ向かい、その途中で雪庇を踏み抜いています。
そこで、往路を忠実に戻れば雪庇を踏む抜くこともなかったとも考えられ、A発見場所から雪上車方向へAを移動させたこと、およびその移動時の行為について過失が存在するのではないかが問題となりました。
この点について裁判所は、
救助隊が・・・雪上車に向けて、登山してきたルートを戻らず・・・最短ルートで移動しようとしたことは・・・不合理な選択であったとは認められない・・・Aは体を支えられれば立位を保ち、自らの意思で足を動かせるくらいの体力は残っているような状態だったので・・・強風下で丸めたストレッチャーを広げることを避けた救助隊員の判断が不合理な選択であったとは認められない・・・救助隊員が持参し・・・Aが飲用したカフェオレは約一〇〇ml、うちカフェインは約三八mgと少量であって、これにより低体温症が促進されたとはいえないことから・・・カフェオレを飲ませた行為が不合理な選択であったとは認められない
札幌地判平成24年11月19日
として、雪上車方向へAを移動させたこと、およびその移動時の行為の過失を否定しています。
続いて救助隊員の進行方法に関し、まず、
主な救助隊員は・・・崖がAの発見場所の近くであること、山頂付近の南斜面では、雪庇を踏み抜くなどして崖下へと滑落する危険性があることを十分認識していたと認められ・・・北風が強く、南側に体が流される危険性が強く、視界も悪かった上、斜面自体がでこぼこして・・・進行方向がずれる可能性の高いことが容易に認識でき・・・Aの発見場所から・・・雪上車を目視することはできなかった。また・・・Aの発見場所から雪庇まではおおむね五〇mの距離にあり、進行方向が若干南方向に向けば、雪庇を踏み抜く危険が現実化する状況にあった(ので、)進行方向が南にぶれる危険性のある方法は、細心の注意を払うのでなければ合理的な選択には当たらない
札幌地判平成24年11月19日
として、雪庇を踏み抜く現実的な危険性が存在していたことから、進行方向が目的経路より南へぶれる危険性のある進行方法を採用した当時の行動には、高度な注意義務が課されていたとしています。
このような高度の注意義務の存在を前提として、救助隊員の具体的行動について、
乙小隊長が指示した進行方法は、コンパスで方位を確認し、進行すべき方向を指で示したというものであるが・・・進行すべき方角は、雪上車の位置が特定できない以上目測に基づくものにならざるを得なかった上・・・コンパスは滑落するまでの間数回確認したというもので・・・南にぶれやすい方法であったといわざるを得ず、細心の注意を払ったものとは到底いえないものであった・・・さらに、①北東方向に進行すれば、南側の崖に向かうことはない位置関係であったこと、②GPSに自分がたどってきた場所をポイントとして固定し、位置を後から確認する機能を利用してそのとおり下山すること、常時コンパスで方角を確認しながら、進行方向を指示することなど、当時の状況下でもとりうる他の方法が容易に想定できることをも考慮すれば、救助隊が選択した上記進行方法は、合理的なものであったと認めることはできず、この選択は国賠法上違法といわざるを得ない・・・Aらの滑落は・・・風にあおられて飛ばされたような事情は見られず・・・雪庇を踏み抜いたものと認められ・・・救助隊員には少なくとも過失があったと認められる
札幌地判平成24年11月19日
と認定し、雪庇を踏む抜いた行為について過失を認定しています。
そして、過失行為である雪庇踏抜き行為とAの死亡という結果との間の因果関係について、
仮に、Aを乗せたストレッチャーを崖上まで引き上げることができたとしても、Aは、凍傷や低体温症が悪化して死亡した蓋然性が高いものと認められ・・・救助隊員が合理的な進行方法をとらなかったこととAの死亡(凍死)との間には因果関係があるというべき
札幌地判平成24年11月19日
として、これを認めています。
このようにして、1審裁判所は、雪庇踏抜き行為を過失行為とし、救助隊員には救助義務を怠った過失があったとして、甲に対する国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求を認容しています。
控訴審判決
一方控訴審では、まず、救助隊の法的救助義務について、
山岳遭難救助活動は警察の責務であり,警察官職務執行法3条1項2号の保護対象者には山岳遭難者も含まれると解されるところ,・・・乙らがAを発見したのは警察官の職務としてAの捜索活動を実施していたことによるのであり,Aを発見した当時,Aには救命の可能性があったが,乙らのほかにAを救助できる者がおらず,当時の気象状況は厳しいものではあったものの,救助が不可能ないしは著しく困難であったとは認められないのであるから,乙らには,Aを発見した時点でAを救助すべき職務上の義務(救助義務)を負っていたというべき
札幌高判平成27年3月26日
と判示しています。
ここでは、警察官職務執行法3条1項2号の根拠規定の存在に加え、救命の可能性、排他性(救助をおこなうことができる者が他にはいなかったこと)、救助の可能性の検討を加え、乙らの救助義務を認めています。
その上で、1審と同様に
救助隊員の救助活動が国家賠償法上違法となるのは,実際に救助活動に当たる救助隊員及び当該山岳遭難者が置かれた具体的状況を踏まえて,合理的と認められない方法を執った場合に限られる
札幌高判平成27年3月26日
と「具体的状況を踏まえて、合理的と認められない方法を執った場合」に国賠法上の違法性が認定されるとの判断基準を示しています。
ところで、上記のように、1審判決は雪庇を踏み抜いて滑落した行為を過失行為とし、雪庇を踏み抜いた後の行為に関しては、因果関係の認定に際し、Aの救助可能性は認められないと認定しているだけです。
ハイマツに固定していたストレッチャーが滑落した時点およびその後の救助隊員の行為については、過失の検討を加えていません。
しかし、控訴審では、ストレッチャー滑落後に甲を捜索せずに下山をはじめたことについて、
本件滑落2(注:ハイマツに固定したストレッチャーの滑落のこと)当時,本件滑落地点2付近は吹雪であり・・・ストレッチャーの滑走痕をたどって甲を捜索することは困難であった・・・引上作業の進ちょく状況を踏まえると,日没時刻までに,上記のように困難な状況下でAを捜索し,発見したAを本件登山道まで引き上げることは,不可能であったとみるのが相当である・・・乙らの携行していた装備及び身体状態ないし負傷状況等を踏まえると,乙らが,ビバークすることも想定した捜索救助活動を実施することは,二次遭難のおそれがあったものといわざるを得ない・・・Aは,・・・警察地域部航空隊によって・・・発見され・・・病院に搬送され,同日午前8時54分に死亡が確認されたが,乙らが,本件滑落2発生後も,捜索救助活動を継続したとしても・・・航空隊よりも早く発見でき,発見したAを救命できたと認めることは困難で・・・乙らが本件滑落2発生後に甲の捜索をせずに下山を始めたことをもって救助義務に違反するとは認められない
札幌高判平成27年3月26日
として、注意義務違反が認められるかの検討をしています。
結果としては、ストレッチャー滑落後の乙らの過失を否定しています。
次に、やはり1審において詳細な検討をしていなかったストレッチャー滑落時の救助隊員の行為について、注意義務違反の有無の検討をおこなっています。
まず、ストレッチャーをハイマツに固定する際に幹および枝に「ひと回りふた結び」の結び方で結束しただけでストレッチャーの滑落を防止する予備的な措置を講じていなかった点に関して、
甲を縛着したストレッチャーをハイマツに結束するに当たっては,甲を滑落させないよう,結び目がほどけたり,枝から抜け落ちたりしないような結び方で結束するとともに,仮に結び目がほどけたり,枝から抜け落ちたりしても,直ちに滑落しないような予備的な措置を講じる義務があったと認めるのが相当
札幌高判平成27年3月26日
として、予備的な措置を講じる注意義務の存在を認定しています。
その上で、
「ひと回りふた結び」の結び方で枝に結ぶと,結び目の輪が枝の先の方にすべり,しなった枝から抜け落ちるおそれのあることは,容易に予見できたというべきであるから・・・ハイマツの枝ではなく,根元に近い幹の部分に荷重がかかると結び目の輪が締まる結び方で結束すべきであったと認められ・・・(ひと回りふた結び)の結束方法では,結び目の輪が枝の先の方にすべり,しなった枝から抜け落ちるおそれがあるし,枝の結び目の輪が抜け落ちると幹が結束していてもストレッチャーが滑落するおそれがあった・・・少なくとも1人の救助隊員がストレッチャーのそばにいるのが困難であった事情はうかがわれない・・・甲が滑落すれば,その引上作業には更にかなりの時間が掛かることは明らかであるから,滑落のおそれがあるにもかかわらず,救助隊員がAのそばを離れなければならなかったとは認め難い・・・丁によるハイマツへの結束方法及び己が到着する前にストレッチャーのそばから離れた乙,丁及び戊のその後の行動は,明らかに合理的とは認められないといわざるを得ない・・・したがって,本件滑落2発生時(ストレッチャーのハイマツからの滑落時)における上記の救助活動は,国家賠償法上違法と評価されるというべきである
札幌高判平成27年3月26日
とひと回りふた結びをハイマツへ結束方法としたこと、およびストレッチャーのそばに誰もいない状況を作出したことについて、注意義務違反に基づく過失を認定しています。
そして、このストレッチャーがハイマツから滑落した時点の救助隊員の過失行為に、国家賠償法上の違法性を認定し、損害賠償請求を認めています。
1審と控訴審認定の相違
控訴審は、Aの凍死という結果から時間的に遡るように、救助隊員の後の行為から順に過失の検討をおこなっている点が1審と異なります。
控訴審では、ストレッチャーがハイマツから滑落した時点の救助隊の行為に過失を認定したことから、それ以前の行為である雪庇の踏み抜き、あるいは更にその前のA救助場所から雪上車方向へ移動させた際の救助隊の行為については、違法性(過失)の検討をしていません。
1審と控訴審の判断枠組みの相違
11)積丹岳遭難事故では、
㋐A発見場所からの移動開始時
㋑雪庇踏み抜きによる滑落時
㋒ストレッチャーのハイマツからの離脱・滑落時
㋓ストレッチャー滑落後の捜索・救助活動中止時
の救助隊の(決定)行為の過失が争点となっていました。
この事故の訴訟上の損害と考えられるのはAの凍死により生じた各種損害ということになりますので、Aの凍死時点から近い順に、時間を遡るようにして、㋓~㋐の時点の救助隊員の各行為に過失が存在したかを、㋓㋒㋑㋐の順に検討していくという思考順序が合理的とも考えられます。
しかし、一方、因果の流れからしますと、㋑の雪庇の踏み抜きがあったからこそAが滑落し、滑落したAを稜線に引き上げるためストレッチャーに乗せることになり、乗せたからこそストレッチャーの離脱・滑落事故が生じた(雪庇の踏み抜きがなければAはストレッチャーには乗せられていなかったと思われます。)とも考えられ、そのように考えると、因果関係の起点となる時間的に早い行為、㋐の時点の行為から㋑㋒㋓と順に、過失該当性の検討をおこなうのが筋であるともいい得ます。
段階的過失の問題について
これは、段階的過失の問題ともいわれており、過失の実行行為をどう特定するかの問題で、とくに刑事事件において問題とされてきました。
この問題に関しましては、複数の過失行為の併存を認める過失併存説が通説であると考えられているようですが、結果に最も近接する一個の過失行為に限定されるとする直近過失一個説も有力に主張されているようです。
11)積丹岳遭難事故では、1審判決は過失併存説、控訴審判決は直近過失1個説に親和的であるとも言えそうです。
1審と控訴審の判決内容の比較
この事故の1審と控訴審の判決を見ますと、救助隊員に救助義務を認定した上で、具体的状況において合理的と認められない方法をとったか否かで過失の有無を判断するという基準を採用しているという点では大きく変わりません。
また、救助隊員の具体的行為に過失を認定し、甲に対する損害賠償請求を認めていることにも変わりはありません。尚、1審では8割の過失相殺を認定、控訴審では7割の過失相殺としており、その過失相殺の割合の差が1審と控訴審の損害賠償認容額の相違となっています。
更に、判決の結論には大きな影響はありませんが、1審と控訴審では救助隊員の上記㋐~㋓のいずれの時点の行為に過失を認定しているかという点に相違があります。
1審は、㋐のA発見場所から雪上車方向への移動開始時の過失は否定し、㋑の雪庇踏み抜きによる滑落時の行為に過失を認定し、㋒及び㋓時点の行為は㋑の行為により決定された因果の流れの一局面に過ぎないとし、個別の行為とはとらえていないものと考えられます。
一方、控訴審は、㋓のストレッチャー滑落後の捜索・救助活動中止時点の過失を否定した上で、㋒ストレッチャーのハイマツからの離脱・滑落時の行為に過失を認定しています。
そして、㋒および㋓(㋐の時点の行為の判断に際しては㋑も)の時点の行為を捨象した場合、㋐および㋑の時点の行為に過失が成立し得るかについては判断をしていません。
この点は、直近過失1個説に親和的な判決内容であるといい得ます。
しかし、控訴審が1審と異なる時点の行為に過失を認定したのは、上記の理論的な立ち位置の相違によるものではないと思われます。
㋒の時点のストレッチャーの固定方法あるいは落下防止の予防的措置の不備という行為と、㋑の時点の雪庇の踏み抜き行為を比較しますと、前者の行為の方が外的要因の影響が少なく、過失の検討に際し、不確実要因を考慮する必要性が後者の場合より低く(雪庇の踏抜きに注意義務違反を認めることが出来るかは、雪庇の状況、気象条件など外的要因に大きく影響されます。)、過失の認定が安定すると考えられます。
遭難者の状態、気象状況、遭難者の保護後の移動開始時間などを考えますと、雪庇の踏み抜きという行為は、ストレッチャーの固定不備の原因行為に比べると、雪庇の状態、気象条件によっては、必ずしも過失の程度が高いと認定しうるものではないと考えられます。
このように、㋑の時点の行為より、㋒の時点の行為を過失行為と認定した方が、過失の認定が安定すると考えられます。
そこで、控訴審は㋒の時点の行為を過失行為と認定するために、直近過失1個説に親和的な判断枠組みを採用したのではないかと思われます。
積丹岳遭難事故判決の位置付けについて
尚、11)積丹岳遭難事故の判決から、山岳遭難者救助時の救助者の行為にも過失が成立し得るという結論を一般化することは適切ではないと思われます。
救助義務の認定に際して具体的な法律の条文を指摘していること、過失相殺が1審で8割、控訴審でも7割認定されていることからすると、11)積丹岳遭難事故の判決は、あくまでも警察・消防の救助隊の隊員に対する過失認定の裁判例と考えるべきと思われます。