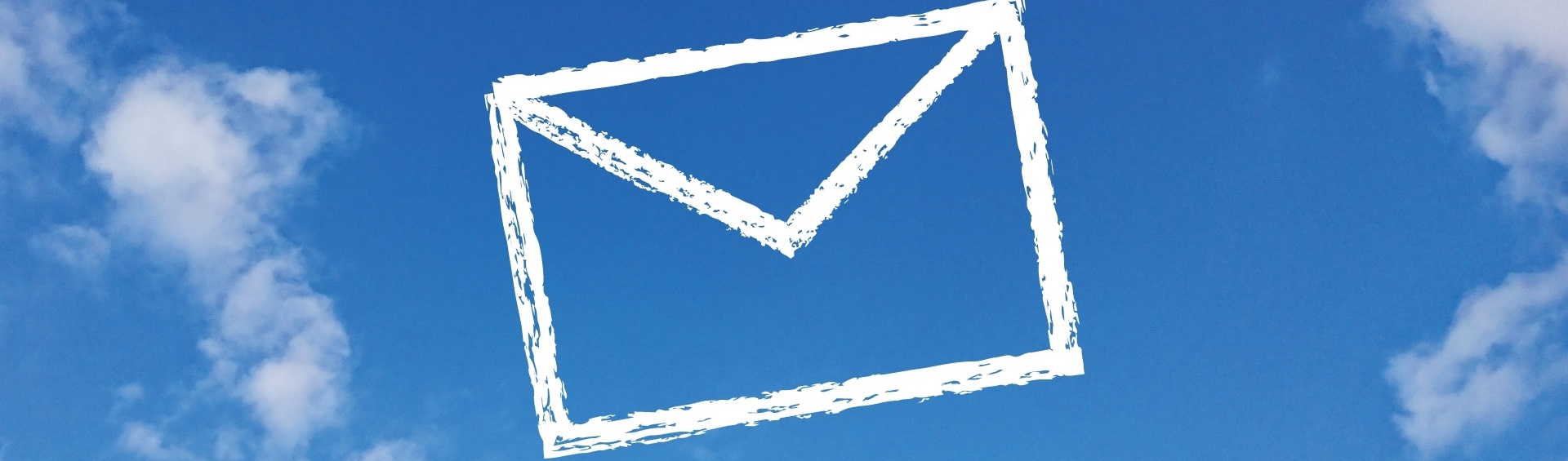今回は、審級で裁判所の判断が異なった、高等専門学校登山部の山行時に発生した雪崩事故である木曽駒ケ岳雪崩事故の裁判(一次訴訟)をとおし、引率教員の過失認定、および高等専門学校の設置者である地方公共団体の国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任についてみていきます。
木曽駒ケ岳雪崩事故の概要
ここでは、審級で過失認定が異なった登山事故として、18)木曽駒ヶ岳雪崩事故(一次訴訟)を取り上げてみます。
この事故は、3月末に学生7名、OB1名と教員2名の計10名からなる高等専門学校登山部のパーティーが、西駒山荘内にテントを張り宿泊した翌日、乙とOBによる朝の偵察の結果を受け、将棊頭山頂から約100m下方の伊那側山腹の森林限界を胸突尾根へ向かうルートを選択し、正午過ぎに下山を開始したものの、下山開始から約1時間半後、樹林の途切れた沢の上部をトラバースしはじめたところで表層雪崩が発生、学生7名中6名、およびOB1名の計7名が雪崩に巻き込まれ圧死したものです。
この事故をうけ、被害者学生のうちのひとり(死亡した学生6名のうちの1名、以下「A」といいます。)の遺族が、乙および丙に
- 事故当日のような悪天候下では下山すべきではなかったのにもかかわらず下山決定をして下山したこと
- 雪崩発生の危険性が極めて高いルートを下山ルートに採用した上、雪崩に対する周到な配慮を欠いて下山したこと
に過失があるとし、当該高等専門学校の設置者である地方公共団体(以下「甲」といいます。)に対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めて提訴しました。
1審裁判所の判断について
1審は、乙らの下山決定に関し、
一般に春山の気象変化は周期性があり、悪天も短い間に去つてその後は山岳行動に支障のないような好天になるものであるとされていることが認められる。そして、本件の場合も、三月三一日(注:事故当日)は天候が一段と悪化したが、四月一日になつてこれが回復したことは当事者間にほぼ争いがない・・・が・・・が三月三〇日午前九時一五分放送の漁業気象通報を聴いて作成した天気図に基づき九州西方に前線を伴う低気圧があり、それが時速約三五キロメートルで東進していることが判明したところから、これによつて今後ますます天候が悪化すると判断し・・・三一日は更に天候が悪化し、四月一日にもその影響が残るかもしれないと判断したことが認められる。しかし、・・・春山といえども、悪天の期間が常に一日とか一日半で終わるという保証はなく、二、三日にわたることもあるし、また前記低気圧の進行方向の太平洋上に高気圧があつた本件にあつては、これが障害となつて右低気圧の速度が純ることも十分考えられることであるから、入山中に作成した天気図と、前記春山の気象変化についての周期性のみから変化の激しい山岳気象を一日先、二日先まで的確に予測することを一般登山者である乙らに要求することは無理というべきで・・・乙らの天候予測と客観的な事実との間に右の程度のズレがあることをもつて、過失があるものと断ずることはできない
東京地判昭和59年6月26日
と、「乙らの天候予測と客観的な事実との間に右の程度のズレがあることをもつて、過失があるものと断ずることはできない」として乙らの天候推移の予測には過失がなかったとしています。
そして、
・・・西駒山荘に滞在するについて食糧及び燃料に当面不安はなく、また山荘の構造自体が特に雪山の山荘として構造上の危惧があつたわけではないことが認められる。しかし、・・・西駒山荘内には破れた窓や板壁の隙間から大量の雪が吹きこんでおり、その中に冬用テントを張つて内張りをしているという状況で、昼間でも寒く且つうす暗かつたことが認められ・・・はつきりした目処なく停滞を続けることは学生(特に初心者)の精神的不安をひきおこし統率がとれなくなる心配もあると考えられたこと、計画表のなかで予備日が明確にされていなかつたところから下山が遅れる場合には学校・家庭に心配をかける結果になること、停滞後、心身共に疲労した状況で下山する場合の滑落、転倒、雪庇の踏み抜き等の危険性をも考慮すると、これ以上天候が悪化する前に、しかも学生が元気で志気も高いうちに、安全に下山できるルートがあれば下山した方がよいというのが乙らの気持ちであつたものと認められる。・・・原告は、雪山では「悪天候下では動くな」との原則があるところ、本件はまさにそのような場合であつたと主張するけれども、停滞した場合にも既にみたような種々の問題点があり、しかも、前記・・・のとおり、九州西方の低気圧が接近してこれからますます荒模様になることが十分予想される本件の場合にあつては、低気圧の本体につかまる前に早く安全な場所へ逃避するため、安全なルートを見つけて下山するというのも一つの許される判断であるということができる
東京地判昭和59年6月26日
と、「荒模様になることが十分予想される本件の場合にあつては、低気圧の本体につかまる前に早く安全な場所へ逃避するため、安全なルートを見つけて下山するというのも一つの許される判断である」として、下山を選択したことについても過失を否定しています。
更に、下山ルートの選定に関し、実際に選択し、事故が発生したルート以外の下山ルートを採用することには問題があったことを述べた上で、
乙は、五万分の一の地図からすれば、あとの二本はおそらくはるか下方にあり・・・沢筋の上方を迂回できるであろうと考え・・・森林限界には多少吹きだまりの雪はあつたが、初心者にはかえつて足元が固定されて歩きやすいと判断し・・・本件ルートによる下山を決定したのであるが・・・客観的には雪崩の危険性をはらんだ下山ルートであつたものと言わなければならない。・・・当時はまだ二万五〇〇〇分の一の地図・・・は発行されておらず、本件パーティーの持参していた五万分の一の地図・・・によれば、未確認の沢筋がどこから始まるか不明であつたし、また前記偵察の際三ツ岩から下方を見おろしても・・・下方の沢の存在を確認することはできず・・・右の沢を認識することは不可能であつた・・・未確認の沢は稜線下五〇〇ないし六〇〇メートル下方から始まつており・・・沢のはるか上方を迂回することができ、沢筋に踏み込んで雪崩を誘発することなしに下山することができるのではないかと考えた・・・判断はやや希望的観測に傾いたきらいがないではなく、特に、右五万分の一の地図上では分明でなかつた三本の沢の一本は殆んど西駒山荘直下まで突き上げていることが偵察の結果判明していたことに照らせば、未確認の二本の沢についてももう少し稜線近くまできていることを警戒する余地があつたのではないかとも考えられないではないが・・・乙らの判断がルートの偵察までした上での・・・ことに思いを至せば、このような判断をしたことに過失があるとすることにはなお躊躇をおぼえるものがある。また・・・雪崩の構造や発生原因については未だ科学的な解明が尽くされているとは言えない段階であつて、当裁判所としても到底これについて確たる判断を示すことはできないし、現に本件においても本件事故現場の沢筋に至るまでの吹きだまりでは雪崩は発生していないのであるから、本件山腹ルート一帯がおよそ通つてはならないと言えるほど雪崩の具体的な危険性をはらんでいたとまで断ずることはできないものというほかはない。かえつて・・・稜線直下では尾根筋からしばしば急に強風が吹き、アイスバーン化しているため滑落の危険性が極めて高いし・・・山腹をトラバースすることは適切な選択と言えるという見解もある程であり、加えて、乙らが、森林限界では雪崩が発生しても樹林帯によつてその規模・速度が緩和され、また樹木につかまつて雪崩を回避できると考えたことは、発生した雪崩の規模にもよるが一応常識的な判断であるとも考えられ・・・乙らの判断を荒唐無稽な考え方であるとする原告の非難は当らないものと考える
東京地判昭和59年6月26日
と、
- ルート偵察の上での選択であることからしても過失があるとすることには躊躇をおぼえること
- 山腹ルート一帯について、通行不可といえるほど雪崩の具体的危険性が存在していたと断ずることができないこと
- 稜線直下は強風、アイスバーンなどにより滑落の危険性が高く、山腹のトラバースルートを選択するのは適切との見解もあること
- 雪崩が発生しても樹林帯で規模・速度が緩和され、また樹木につかまり雪崩を回避できると考えたのも一応常識的な判断であるとも考えられること
などから、下山ルートの選定に関する乙らの過失も否定しています。
その上で、
・・・乙は雪崩等の危険箇所に備えてキスリングの上にザイルをセットさせるなどの対策を構じているし、初心者に対しては顧問らを信頼して慎重に行動するようにとの説明をしていることに照らせば、初心者に過度の不安を与えないためにあえてこれを話さなかつたというのも一応うなずけ・・・らによつて発見されたクラックは必ずしも本件事故の雪崩の予兆であるとは言えないこと、本件事故現場が沢筋であると認識することは進行中には不可能であつたことを考えると、仮にそれ以上に雪崩の危険につき説明・注意をなし、途次の異常を乙らに伝達するよう指示がなされていたとしても、必ずしも本件事故を防ぐことができたとは言えないから、いずれにしても右の説明や指示がなかつたことをもつて乙らの過失ということはできない・・・がその登山歴や実力からしても乙に次ぐ位置を占めていたことからすれば、そのような・・・が先頭にたつことも山岳パーティーの隊列の組み方としては一般にとられることのあるものであり何ら異とするに足りない・・・隊列の順番自体に問題があつたとは言えない・・・隊列が一定の充分な間隔を保つていれば、たしかに本件のごとき大量遭難を防ぐことができたとは言えるであろう。しかし・・・森林限界付近に到達するまでは・・・雪崩より滑落の危険があつたこと、森林限界付近は・・・初心者の後ろで経験者が補佐をする必要もあつたこと・・・視界は森林限界沿いでは大体二〇メートル前後、本件事故現場付近で一〇ないし二〇メートルであつたからパーティーのメンバーを見失わないようにする必要もあつたこと、夕刻までに大樽小屋に辿り着くためにはある程度の速さで進まなくてはいけないことという事情があつた・・・雪崩発生の危険のある箇所に到達したときには、事故予防のため下山を中止し退却、退避し、または一人ずつザイルでトラバースさせるなどの状況に応じた適切な処置をとるべきことは当然ではあるが・・・本件事故現場が危険な沢筋であることの予見可能性がなかつた以上・・・右のごとき処置をとるべきことを要求することは不可能であつた
東京地判昭和59年6月26日
としています。
ここでは、
- 指導教員から、学生らへの雪崩の危険性に関する説明や指示がなかったことをもって過失とはいえないこと
- 下山時のパーティーの隊列の順番に問題があったとはいえないこと
- 隊列が一定の間隔を保っていなかったことも、滑落の危険があったこと、メンバーを見失わないようにする必要があったこと、ある程度の速さで進まなければならなかったなどの事情からやむを得ないものであったこと
- 事故現場が危険な沢筋であることの予見可能性はなく、事故予防のため下山を中止、退却、退避し、または一人ずつザイルでトラバースさせるなどの処置をとるべきことを要求することは不可能であつたこと
などから下山行動過程にも過失がなかったとしています。
このようにして、乙および丙の
- 天候推移の予測の過失
- 下山選択の過失
- 下山ルート選定の過失
- 下山行動過程の過失
を否定し、甲への請求を棄却しています。
控訴審の判断について
しかし、控訴審では、まず、学校行事の特殊性として、
一般に、登山活動には山岳コース自体の危険性のほかに、天候急変、落石、雪崩など自然現象による危険の発生、あるいは体力、登山技術の限界などに伴う危険が存在することは公知の事実であり、登山パーティーのリーダーは、常にかかる危険の存在に注意を払い、極力その危険を回避してパーティー構成員の安全を確保すべき注意義務があることはいうまでもないところであるが・・・学校行事として行われる登山については、特にその安全の確保が要求され、これが各学校の関係者に周知されていることにかんがみると、学校行事としての登山は、一般の冒険的な登山あるいは同好の士による登山とは異なり、より一層安全な枠の中で行うべきことが要求され、その危険の回避については、より一層の慎重な配慮が要求されているというべきである
東京高判昭和61年12月17日
と、学校行事の登山については、一般の登山以上に安全に配慮する必要があるとしています。
そして、危険回避に関しても、よりいっそう慎重な配慮が要求されるとし、高度な危険回避義務が課されることに言及しています。
その上で乙らには、引率・指導者として、
傾斜三〇度ないし五〇度の樹木のない場所・・・沢筋及び沢を登りつめた山腹部分、稜線下の風下の吹き溜り部分などは雪崩の危険区域であり、特にクラストした雪の上に新雪が積もつている場合、降雪直後の新雪の不安定な時期、日中の気温上昇時などに雪崩が発生し易く、また強風による風圧、雪庇の落下、雪斜面の横断ラッセルなどの外部的要因によつて雪崩が誘発される危険が大きく、雪上にクラックが生じる場合は雪の状態が不安定であることを示しており雪崩の一前兆である(ので)・・・登山パーティーのリーダーは、右のような雪崩の発生し易い状況が存在するときには雪崩の危険地帯には近づかないようにし・・・右のような危険に遭遇した場合には危険状態が解消されるまで停滞、あるいは退却すべきであること、やむを得ず右のような危険な場所に近づく場合には、先頭には経験者を配置し、雪質、雪の安定度、クラックや吹き溜りの存在などに細心の注意を払い、斜面の横断ラッセルなどは厳に慎み、万一、右のような場所を横断する場合にはザイルによる確保をした上で一〇ないし一五メートルの間隔を開けて一人ないし二人ずつトラバースすべきであること、そして万一に備えて雪紐を着用すべきであることが認められ(る)
東京高判昭和61年12月17日
と、
- 雪崩の発生しやすい状況が存在するときには雪崩の危険地帯には近づかないようにすべきであること
- 雪崩の危険状態が解消されるまで停滞、あるいは退却すべきであること
- やむを得ず雪崩の危険な場所に近づく場合、先頭には経験者を配置し、雪質、雪の安定度、クラックや吹き溜りの存在などに細心の注意を払うとともに、斜面の横断ラッセルは避けるべきこと
- 万一、雪崩の危険のある場所を横断する場合は、ザイルにより確保し、十分な間隔をあけ1~2人ずつ、雪崩紐を着用してトラバースすべきであること
などの安全確保のための注意義務が存在したとしています。
そして、
本件事故現場は稜線の風下に当たつていたところから雪の吹き溜りが生じるなど雪崩の発生し易い状態にあつたものと認められ・・・特別の理由がない以上、本件ルートに立ち入ることを避けるべきであつた・・・本件ルートが右沢筋にかからず、その上部を迂回して胸突尾根に至るものであると速断することは軽率であり・・・沢筋の上部も雪崩の危険地帯であることにかんがみると、右偵察の結果によつて本件ルートが安全なコースであると判断することはできないというべきで・・・乙らが西駒山荘に停滞せず、本件ルートにより下山を強行したことは、本件パーティーの引率・指導者として負つていた前記安全確保の義務に違反した過失がある
東京高判昭和61年12月17日
として、乙らが西駒山荘に停滞せず、本件ルートにより下山を強行したことは、上記の1および2の注意義務に違反したものであるとして、乙らに過失を認定しています。
また、
・・・仮に本件ルートを下山する場合であつても・・・生徒らに対し事前に雪崩に対する注意を与え、進行中に雪面のクラックなど雪崩発生の危険を感じさせるような異常が発見された場合には直ちにリーダーに報告させるなど万全の措置をとるとともに、パーティーの先頭あるいはこれに準じた位置に立ち、常に雪質、クラック、雪の吹き溜り及び沢筋、沢のくぼみなどの危険箇所の存在に細心の注意を払い、沢のつめ部など雪崩の危険の高い箇所を横断する場合にはラッセルを中止し、一人一人の間隔を開けて身体をザイルで確保しながら横断すべきであつたというべきである・・・しかるに、乙らは・・・生徒に対して雪崩についての注意を与えず、本件パーティーの最後尾につき、積雪斜面を掛け声をかけラッセルをしながら一団となつて本件事故現場に向かつて行つたのであるから・・・乙らの右行為は前記雪崩に対する注意義務を怠つた無謀な行為というべきであり、しかも右進行中に・・・らが二回にわたつてクラックを目撃したにもかかわらず、これが乙らに報告されず、乙ら自身もこれに気が付かないまま、漫然とラッセル進行を継続し、雪崩の危険の大きい本件事故現場に突入したのであるから、乙らには雪崩に対する注意義務を欠いた過失があるというべき
東京高判昭和61年12月17日
として、乙らが上記の3および4の注意義務にも反し、その点にも過失が認定できるとしています。
その上で、
Aが本件事故に遭遇して死亡したのは乙らが雪崩に対する注意を怠り、生徒に対する安全確保の義務に違反した過失によるものというべきである
東京高判昭和61年12月17日
として、乙らの1~4の注意義務違反に基づく過失とAの死の結果との間の因果関係を認め、甲に対する損害賠償請求を認容しています。
その後、上告されましたが、上告は棄却され、高裁の判決は確定しました。
1審と控訴審の判断が異なった理由
控訴審の判断が1審から変更された主な理由は、事実認定の相違ではなく、過失の認定という法的評価が異なったことによるものです。
そして、1審と控訴審の過失認定が異なった主な理由は、控訴審が、
①学校行事としての登山は、一般的な登山より、パーティー構成員の安全を確保するためにいっそう慎重な行為をおこなう注意義務があるとした上で
②上記の1~4の注意義務違反を認定
したことにあります。
1審と控訴審では、ルート選択に係る事実関係・諸事情、およびルートの通過方法に関する事実関係の認定の点では大きな違いはありません。
過失の認定が異なるに至ったのは、主に、①の注意義務の程度に関する1審と控訴審の認定の差によるものだと思われます。
1審判決では、注意義務の程度に関し、とくに言及していません。
また、上記に引用しましたように、1審判決では、
現に本件においても本件事故現場の沢筋に至るまでの吹きだまりでは雪崩は発生していないのであるから、本件山腹ルート一帯がおよそ通つてはならないと言えるほど雪崩の具体的な危険性をはらんでいたとまで断ずることはできない
東京地判昭和59年6月26日
として乙らの過失を否定するなど、1審はかなり緩い基準を用いて過失の検討をおこなっているように感じられます。
この点につきましては、高等専門学校の特殊性も影響しているとも考えられます。
本サイトでも教育活動の登山事故の判決に関する記事において触れていますが、高校生までと大学生とでは、学校の生徒・学生の安全に対する注意義務・安全配慮義務の程度は異なります。
大学生に対する注意義務は、一般社会人のパーティー登山の場合とあまり変わらない程度となり得ます。
しかし、高等専門学校には、高校1年生から短期大学2年生に対応する年齢の学生が在学し、実際に木曽駒ヶ岳雪崩事故のパーティーでも、1年生から4年生(短期大学1年生に相当)までの学生が参加しています。
控訴審では、参加していた学生の年齢、登山歴を考慮し、高校の課外活動に近い注意義務の程度を引率者である教員に求めたのではないかと考えられます。
もし、参加者が4年生と5年生のみであれば、あるいは大学に近づけた基準となり、1審の判断は控訴審でも変わらなかった可能性もあり得るのではないかと思われます。
ただし、雪崩の危険性は相当程度あったことから、大学に近づけて考えても、必ずしも引率者の過失が否定されるとまでは言い得ないと思われます。