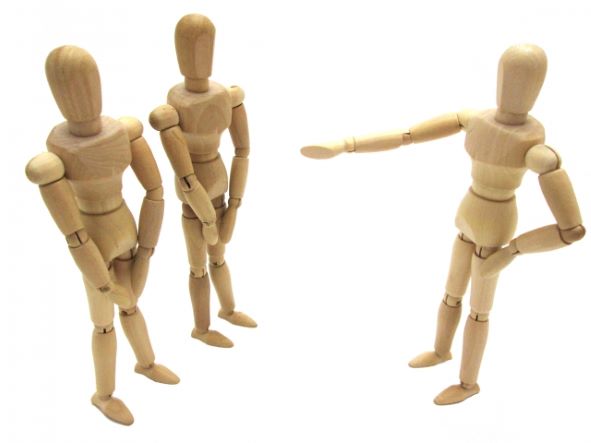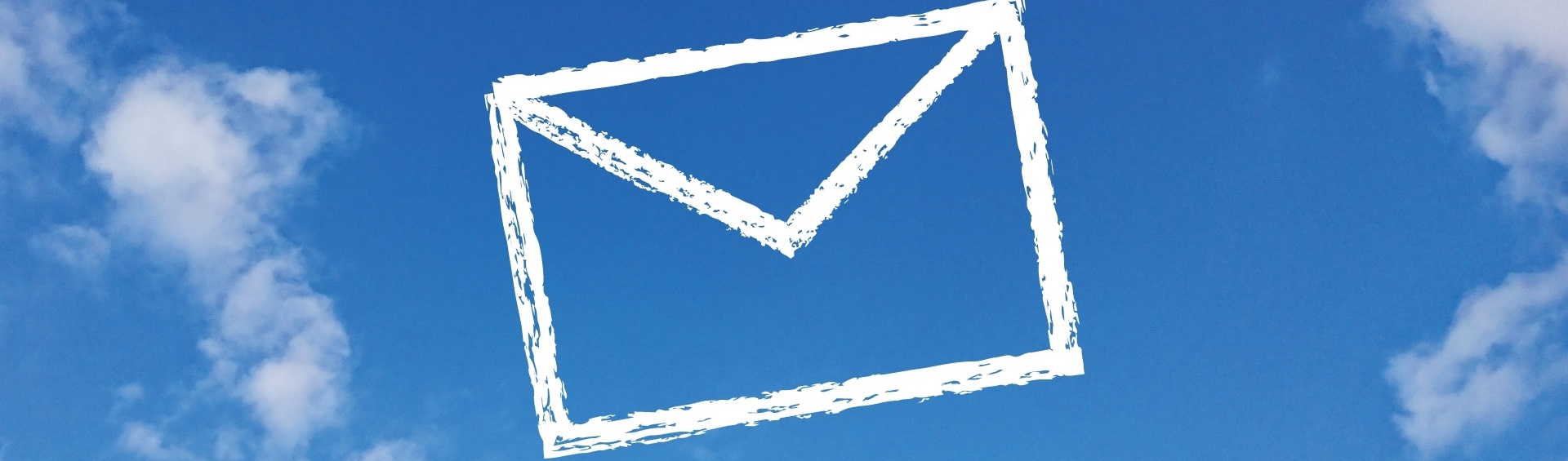解雇予告を30日前におこなう際、30日という日数をどのように数えるのでしょうか。
また、暦の上では2日にわたる夜勤時、労働基準法上の一日の労働時間はどのように計算するのでしょうか。
労働基準法の日にちと時間の計算方法について説明した上で、解雇予告の30日前の数え方と夜勤時の労働基準法上の一日の労働期間の計算方法について解説します。
目次
解雇予告における30日前の数え方について
労働基準法20条1項により解雇通知をする日について
労働基準法20条1項は、
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
労働基準法20条1項
と解雇予告について規定しており、その第1文では、会社が従業員を解雇する際には「30日前」までに解雇することを予告しなければならないとしています。
この30日前とはどのように数えるのでしょうか。
たとえば、9月30日付で解雇しようとする場合、いつまでに解雇を予告すればよいことになるのでしょうか。
労働基準法は、とくに日の計算方法について規定していないことから、まずは、労働基準法において日数をどのように計算すればよいのかが問題となります。
解雇予告の日数が関係した裁判例
この点につきましては、試用期間中の従業員の解雇予告の日数が問題となった福岡地決昭和29年12月28日では、
・・・試用期間中の従業員を解雇する場合には、この斯間中に解雇の意思表示をすれば足るのであるが・・・労働基準法等にむいて期間の計算につき民法と別異の規準によるべき特段の理由は何等存しないのであるから、右予告は所定の三十日に一日不足する瑕疵ある・・・右解雇予告即ち解雇の意思表示は右瑕疵により無効であるといわなければならない・・・
福岡地決昭和29年12月28日
と判示し、労働基準法が日の計算方法について規定していないことをもって、日の計算については民法の計算方法に従うことになるとしています。
尚、法律上の期間、期限については、下記の記事でも扱っております。
解雇予告はいつまでにしなければならないのでしょうか
このように労働基準法の日数の計算方法は、民法で定められた日数の計算方法に準ずると考えられています。
ところで、民法140条では、日数の計算では、初日不算入とされています。
そこで、上記の労働基準法20条1項の「・・・解雇しようとする場合・・・少くとも三十日前にその予告をしなければならない」とされている30日の計算においても、民法140条に従い初日不算入となり、解雇を言い渡す日は日数の計算上含まれないこととなります。
また、民法141条では、期間は、「その日の終了」をもって満了すると規定しています。
そこで、解雇予告に際しても、解雇予告日の翌日から30日目の日が終了した時に30日の期間が満了したこととなります。
したがいまして、9月30日の満了をもって解雇しようとする場合、遅くとも8月31日には9月30日の満了をもって解雇するとの予告をする必要があることとなります。
尚、30日前までに解雇予告しない場合でも、30日に足りない日数分の平均賃金を解雇予告手当として支払えばよいとされています(労働基準法20条2項)。
尚、解雇予告および解雇予告手当については下記の記事でも解説しています。
夜勤時の一日の労働時間の計算方法について
労働基準法32条2項の1日の労働時間の上限について
次に、労働基準法32条2項では、
使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
労働基準法32条2項
と規定されていますが、ここでいう1日の労働時間はどのように計算するのでしょうか。
たとえば、8月31日の0時から24時までに勤務していた時間を、8月31日の労働時間と考えますと、8月31日の21時から9月1日の7時まで連続10時間勤務した場合でも(ここでは、事案を単純化するため、休憩時間については考慮しないこととします。)、8月31日の労働時間は3時間で9月1日の労働時間も7時間ということになります。
1日の労働時間に関する基発
この点につきまして、昭和63年1月1日基発第1号では、
1日とは、午前0時から午後12時までのいわゆる暦日をいうものであり、継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「1日」の労働とすること。
昭和63年1月1日基発第1号
としています。
この基発からしますと、上記の例のように8月31日の21時から9月1日の7時まで勤務した場合、その間の10時間の労働はすべて、当該勤務の開始時刻である8月31日の21時が属する日である8月31日の労働ということになります。
しかし、そのような労働条件は、労働基準法32条2項の1日の労働時間の上限8時間を超え、同項に抵触することとなります。
そこで、このような勤務シフトを導入する場合、労働基準法32条の2の変形労働時間制などの制度を採用して対応する必要があります。
尚、労働基準法32条の2は、
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第一項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。
労働基準法32条の2
と規定しています。
夜勤時の労働時間の上限と割増賃金の考え方
上記のように、夜勤のように2日にわたって連続勤務する場合、労働基準法上、1回の全労働時間は勤務開始日の労働時間として扱われることとなります。
そこで、夜勤1回の勤務時間が8時間を超えるような労働契約を締結する場合、労働基準法32条2項の1日の労働時間の上限に抵触し、違法となる可能性がでてきます。
その場合、変形労働時間制などの採用により解決を図ることとなります。
また、夜勤時の22時から翌5時の時間帯の労働に対しては深夜労働の割増賃金が支払われることとなるほか、1回の夜勤の労働時間が8時間を超えるような場合、8時間を超えた部分については時間外労働の割増賃金の対象となります。