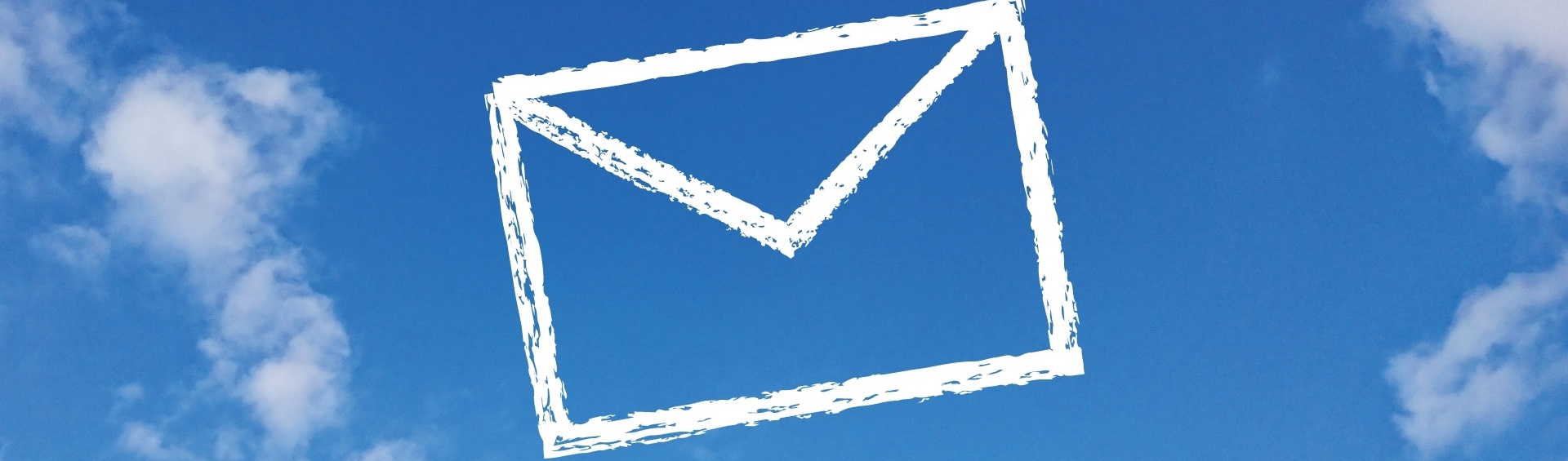公務員の注意義務違反により損害を被った人は、国あるいは公共団体に対して国家賠償法1条1項に基づき損害賠償請求をなし得ますが、公務員個人に対しては損害賠償請求できないのが原則とされています。
しかし、同法1条2項により、国または公共団体が、公務員個人に対して求償をなし得ることがあります。
ここでは、この国家賠償法1条2項の求償権の法的性質について判例をみながら解説します。
目次
国家賠償法1条1項の賠償義務の帰属
下記の記事において、公務員である教員の過失が認定された登山事故を扱っています。
この事故のように、公務員の注意義務違反により事故が生じたような場合、被害者が、当該公務員が属する国または地方公共団体等に対し、国家賠償法1条1項に基づき損害賠償請求をおこなうことがあります。
上記の記事でも触れましたが、公務員の過失行為が問題となるケースでは、国家賠償法1条1項に、
第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
国家賠償法1条1項
と規定されていることもあり、原則として損害賠償義務を負うのは国または地方公共団体であり、直接、公務員個人が損害を受けた人への損害賠償義務を負うことはないとされています。
国家賠償法1条2項の求償権について
しかし、国家賠償法1条2項では、
② 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
国家賠償法1条2項
と規定されており、損害を被った人へ損害賠償をおこなった国、地方公共団体は、「公務員に故意又は重大な過失」ある場合には、公務員個人への求償をおこなうことが可能であるとしています。
しかし、実際には、同項により求償がなされるケースは少ないとされています。
同項の前提となる国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求事件において、過失が普通の過失なのか、重過失なのか、あるいは故意まで認定し得るのかという違いは、訴訟の結論としての損害賠償請求権の存否、金額への影響が大きいものではありません。
そこで、原告としても、過失の軽重あるいは故意の存否まで争点化して立証をおこなうことは少なく(重過失、故意を主張、立証するためには、その分、原告の立証負担が増加しますし、訴訟の長期化を招きかねない上に、場合によっては、過失の存在の認定にまで不利益を被りかねません。そのこともあり、重過失、故意の主張・立証を回避しようとする誘因が働くことは否定できません。)、その結果、国家賠償法の損害賠償請求訴訟において、重過失、故意まで認定されることは多くはありません。
このようにして、国家賠償法1条2項の公務員個人への求償権行使の要件となる、公務員個人の故意あるいは重過失が認定されることが少ないこともあり、結果として、同項の求償権の行使がなされるケースが少なくなると考えられます。
住民訴訟による求償権行使
住民訴訟の事例
このように、国家賠償法1条2項の求償権行使が少ないこともあり、求償権行使を求める住民訴訟が提起されることがあります。
比較的近時のものとしては、前市長に対する求償権を行使するよう、現市長を被告として提訴された住民訴訟(東京地判平成22年12月22日)などがあります。
国家賠償法1条1項の法的性質と2項の求償権
この国家賠償法1条2項の法的性質は、なぜ公務員の過失に国または地方公共団体が損害賠償義務を負うのかという、1条1項の法的性質と関係して説明されることもあります。
国家賠償法1条1項の国または地方公共団体の損害賠償義務に関しましては、大きく分けますと、
- 公務員個人の責任を国または地方公共団体が代位(肩代わりする)すると考える「代位責任説」
- もともと公務員の行為は国または地方公共団体に帰属しているからだとされたり、公務の執行には元々危険が内在していることから、危険を引き受けた国または地方公共団体が責任を負うのだとする(その他にも理由付けには諸説あります)「自己責任説」
があり、「代位責任説」が一般的であるとされています。
国家賠償法1条2項の求償権の性質は、「代位責任説」からは、不当利得返還請求的なものととらえれば容易に説明がつくとされ、「自己責任説」からは、公務員の国または地方公共団体に対する債務不履行的な性質と考えるとされています。
求償権の範囲に関しましては、この2つの説の法的性質との関係では、代位責任説を採用した方が、自己責任説を採用した場合より広くなるとも考えられていました(代位責任説、自己責任説のいずれを採用するかと、求償権の範囲は、直接リンクしていないとする説もあります。)。
判例に見る国家賠償法1条1項と2項の法的性質
この関係については、近時、最判令和2年7月14日において触れられています。
この裁判は、県教育委員会の職員らが、教員採用試験で受験者の得点を操作するなどの不正をおこない、県が不合格となった受験者らに対して損害賠償金を支払った事件で、住民らが、県知事に対し、不正に関与した者に対する求償権を行使するよう求めた住民訴訟の上告審です。
この裁判では、元々の不正行為を働いた公務員が複数存在し、その不正行為を共同不法行為と認定できる場合、求償権は、不正を働いた人それぞれに分割され、分割請求権となるか(たとえば、不正行為を働いた人がXとYの2人で、県が負担した損害賠償金が100万円であった場合、県はXとYに対し各々50万円ずつ請求できるのか)、あるいは、不法行為者間の連帯債務となるのか(XとYに対し、合計100万円の範囲で、どちらにも100万円まで請求できるのか)という点が争点となりました。
この点につき、最高裁は、
国又は公共団体の公権力の行使に当たる複数の公務員が,その職務を行うについて,共同して故意によって違法に他人に加えた損害につき,国又は公共団体がこれを賠償した場合においては,当該公務員らは,国又は公共団体に対し,連帯して国家賠償法1条2項による求償債務を負うものと解すべきである。なぜならば,上記の場合には,当該公務員らは,国又は公共団体に対する関係においても一体を成すものというべきであり,当該他人に対して支払われた損害賠償金に係る求償債務につき,当該公務員らのうち一部の者が無資力等により弁済することができないとしても,国又は公共団体と当該公務員らとの間では,当該公務員らにおいてその危険を負担すべきものとすることが公平の見地から相当であると解されるからである。
最判令和2年7月14日
と、故意の認定される場合には連帯債務になると判示しています。
そして、この判決では、宇賀裁判官が補足意見の中で、上記の国家賠償法1条1項の法的性質についても触れていますので、長文ですが引用します。
私は法廷意見に賛成するものであるが,原審が国家賠償法1条1項の性質について代位責任説を採用し,そこから同条2項の規定に基づく求償権は実質的に不当利得的な性格を有するので分割債務を負うとしていることについて,補足的に意見を述べておきたい。同条1項の性質については代位責任説と自己責任説が存在する。代位責任説の根拠としては,同法の立案に関与された田中二郎博士が代位責任説を採ったことから,立法者意思は代位責任説であったと結論付けるものがある。しかし,同博士が述べられているように,同法案の立法過程において,ドイツの職務責任(Amtshaftung)制度に範をとって,「公務員に代わって(an Stelle des Beamten)」という文言を用いることが検討されたものの,結局,この点については将来の学説に委ねられたのであり,立法者意思は代位責任説であったとはいえない。
最判令和2年7月14日 宇賀裁判官補足意見
また,代位責任説と自己責任説を区別する実益は,加害公務員又は加害行為が特定できない場合(東京地判昭和39年6月19日・下民集15巻6号1438頁,東京地判昭和45年1月28日・下民集21巻1・2号32頁,岡山地津山支判昭和48年4月24日・民集36巻4号542頁)や加害公務員に有責性がない場合(札幌高判昭和53年5月24日・高民集31巻2号231頁)に,代位責任説では国家賠償責任が生じ得ないが自己責任説では生じ得る点に求められていた。しかし,最高裁昭和51年(オ)第1249号同57年4月1日第一小法廷判決・民集36巻4号519頁は,代位責任説か自己責任説かを明示することなく,「国又は公共団体の公務員による一連の職務上の行為の過程において他人に被害を生ぜしめた場合において,それが具体的にどの公務員のどのような違法行為によるものであるかを特定することができなくても,右の一連の行為のうちのいずれかに行為者の故意又は過失による違法行為があったのでなければ右の被害が生ずることはなかったであろうと認められ,かつ,それがどの行為であるにせよこれによる被害につき行為者の属する国又は公共団体が法律上賠償の責任を負うべき関係が存在するときは,国又は公共団体は,加害行為不特定の故をもって国家賠償法又は民法上の損害賠償責任を免れることができないと解するのが相当」であると判示している。さらに,公務員の過失を組織的過失と捉える裁判例(東京高判平成4年12月18日・高民集45巻3号212頁等)が支配的となっており,個々の公務員の有責性を問題にする必要はないと思われる。したがって,代位責任説,自己責任説は,解釈論上の道具概念としての意義をほとんど失っているといってよい。
本件においても,代位責任説を採用したからといって,そこから論理的に求償権の性格が実質的に不当利得的な性格を有することとなるものではなく,代位責任説を採っても自己責任説を採っても,本件の公務員らは,連帯して国家賠償法1条2項の規定に基づく求償債務を負うと考えられる。
ここで、興味深いのは、国家賠償法1条1項の法的性質の構成が、判例の蓄積により、実務上の重要性を失っていったということです。
しかし、その判例が蓄積される過程では、学説上の論争が意識されていたと思われることから、学説の重要性が失われたと考えるべきではないと思われます。
学説が問題意識を醸成し、判例が実務的な拠り所を築いていったという軌跡を、この事件では、控訴審と上告審の判断の差異および宇賀裁判官の補足意見の中で見て取ることが出来るかと思われます。