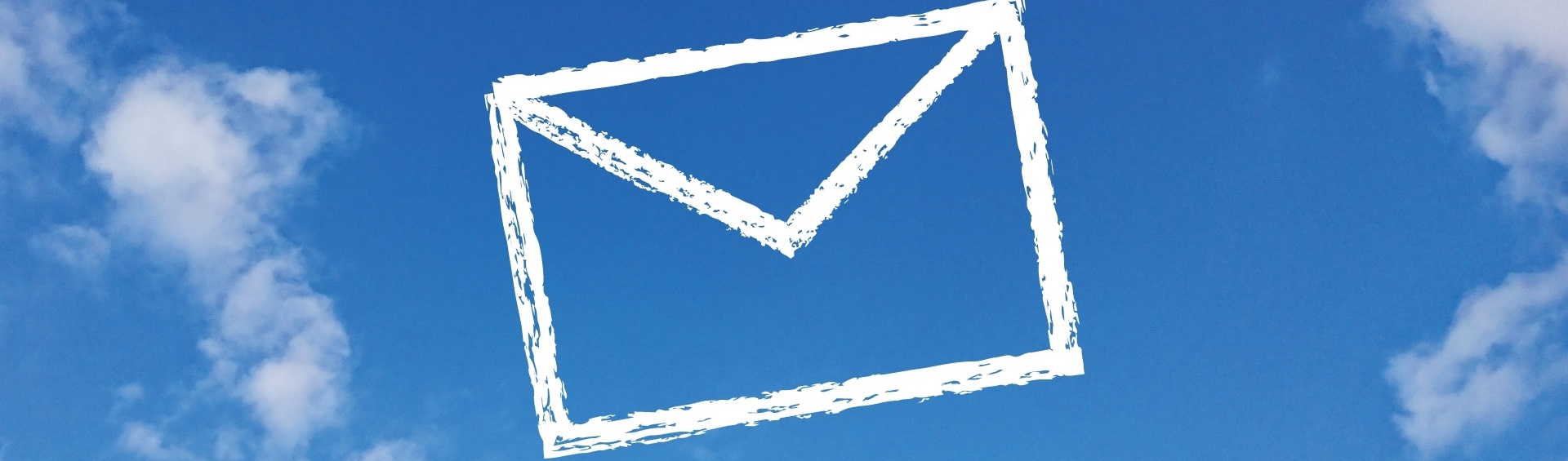羊蹄山ツアー登山遭難事故の概要
今回は、26)9月下旬の参加者(客)14名と旅行会社の添乗員1名の計15名による羊蹄山ツアー登山において、参加者2名(以下「A」及び「B」といいます。)が凍死した事故(以下、凍死した2名を「A」及び「B」、遭難事故を「羊蹄山ツアー登山遭難事故」といいます。)をみてみます。
この羊蹄山ツアー登山遭難事故では、ツアー登山を募集・催行した旅行会社(以下「X社」といいます。)において、登山ツアーの企画立案、およびツアー客の引率等の業務に従事していた同社のサブマネージャー(以下「甲」といいます。)が、凍死した2名に対する業務上過失致死により起訴され、札幌地方裁判所において禁固2年執行猶予3年の有罪判決が下され(判決言渡日:平成16年3月17日)、判決が確定しています。
民事訴訟としては、A及びBの遺族が損害賠償請求訴訟を提起しましたが、和解したようです。
尚、この事故の裁判を契機として、業界団体により「ツアー登山運行ガイドライン」が制定されることとなりました。
ツアー登山の概要と事故当日の状況
このツアーは出発地が大阪であり、55歳~71歳の16名が参加していましたが、ツアー参加者の内2名は事故当日の羊蹄山登山を断念し入山しなかったため、事故当日の羊蹄山登山は上記のとおり、参加者14名と甲の計15名でおこなわれました。
登山コースは、比羅夫登山口から山頂までを往復するものでしたが、事故当日の午前3時頃に北海道磯谷郡付近を台風が通過し、午前5時45分に大雨・洪水・暴風警報、午前7時25分には暴風警報、大雨・洪水注意報、同日午後零時15分には強風注意報が発令されていました。
羊蹄山は標高1898mの独立峰で、比羅夫登山口は標高350mであることから、事故当日の登山コースの標高差は1500m以上で、それ程容易なツアーではなく、それなりの体力を要するものであったといい得ます。
尚、実際に実施されたかは不明ですが、ツアーの募集要項では、羊蹄山登山の前日にニセコアンヌプリを登る予定となっていました。
羊蹄山は、北海道の山ということもあり、森林限界は低く、9合目あたりで森林限界を超えます。
また、独立峰なので風雨の影響を受けやすいともいい得ます。
そして、事故当日未明には台風が羊蹄山の近くを通過したことから、事故当日は強風が続くことが予想されており、また、降雪時期が近付く9月下旬で気温も低かったこともあり、体感温度は相当低くなることが予想される状況であったといえます。
そのようなコンディションで、参加者が全員55歳以上というパーティーでのツアー登山を決行したことが妥当であったか、疑問ではあります。
実際に、登山開始後、続々と登頂を断念し、山頂に到達した参加者は入山した14名のうち9名に過ぎません。
事故当日の添乗員と参加者の行為
判決で認定されている事故当日の甲およびツアー参加者の行動は次のとおりです。
Ⅰ 午前7時50分頃に比羅夫登山口を出発し、甲は11時30分ころに9合目付近に到達しています。
尚、9合目までは一本道ですが、9合目より上はガレ場や登山道の分岐が続くこととなります。
この9合目に到着するまでに、参加者14名のうち3名が登頂を断念し下山しています。
Ⅱ 9合目付近では、AとBおよびCとDの4名は、甲らの集団(甲および参加者7名の計8名からなる集団、以下この甲を含む8人の集団を「第1集団」といいます。)から遅れ、離れた状態になっていました。
しかし、甲は、Aらは後からついてくるものと考え、Aらを待つことなく、第1集団の参加者7名とともに9合目の分岐から左手の登山道(時計回りに周回するルート)を進みました。
Ⅲ 第1集団は、火口を囲む外輪山を周回する登山道(以下、この登山道を「周回ルート」といいます。)を時計回りに進み、羊蹄山の山頂に到達しています。
第1集団が山頂付近に到達して間もなく、遅れてCとDも山頂に到達し、第1集団に合流しました。
しかし、AとBはこの時点で山頂付近に到達しておらず第1集団に合流していません。
尚、事故当日、山頂付近は濃霧で視界は10~30m程度、体感風速も10m以上あったようです。
Ⅳ 甲は、AとBの到達を待たずに、第1集団の参加者のうち脚が痙攣した1名に付き添い、登頂時と同じルートで下山を開始しました。
その他の登頂した参加者は甲と同行せず、別々に登頂時と同じルートで下山を開始しました。
Ⅴ 山頂付近に遅れて到達したCは、下山開始後の行動について、
・・・山頂から1人で下山途中の⑪の山頂側手前(注:北山三角点の手前の山頂からコースタイムで30分程度の地点)で,外輪山の外側下方約29メートルの地点の霧中にA及びBを発見して傍まで下り,若い男性から教示された9合目に出る下山道に向かっているとして納得しないAを更に下方に連れて行って道を間違っていることを確認させ,Aらの発見から約30分後に漸くA及びBを伴って登山道に戻ったが,折からの視界不良やAらがついてくる精神的圧迫もあって⑧の分岐点(注:北山三角点先の9合目へ向かう登山道と旧小屋跡へ向かう登山道の分岐点)を見付けられなかったために9合目に辿り着けず,被告人らとの合流を期待しながら山頂を目指し,⑬手前(注:旧小屋跡から北山を左手に見て山頂方向へ進むルートが周回ルートと合流する地点と京極ルートが周回ルートと合流する地点の中間あたり)で食事を取り,遺体発見現場となった岩陰でBらを休憩させて1人で山頂に到達したが徒労に終わり,当日午後3時30分ころにBらの休憩場所に戻って救援を待ちながら野営したが,やがてA及びBが死亡した
札幌地判平成16年3月17日
旨を裁判で供述しており、裁判所は、Cの供述を信用性が高いものと認定しています。
尚、翌日午前中にⅤのビバーク地付近において、Cは発見され、生存が確認されています。
因果関係の中断の問題
この事故の裁判では、甲の注意義務違反と、AおよびBの死の結果との間の因果関係が問題となりました。
後述のように、9合目付近で第1集団から遅れていた参加者が合流するのを、甲が待たなかったことを注意義務違反行為としていることから、上記のⅡの時点の行為が注意義務違反の実行行為となります。
しかし、時間的にはⅡの後となるⅤの時点のCの関与も、AおよびBの死の結果に対し、影響を与えているようにも思われます。
つまり、甲の注意義務違反の実行行為とAおよびBの死の結果の間に、被告人である甲以外の第三者の行為が関与していたと評価でき、そのため、AおよびBの死の結果は、甲のⅡの時点の注意義務違反の実行行為によるものではないともいいえ、因果関係が否定され得るのではないかということです。
このように、被告人の実行行為後、第三者の行為または自然力が介入した場合には、実行行為と結果の因果関係は中断し、因果関係が否定されるとするのを「因果関係の中断」といいます。
注意義務違反の実行行為
この因果関係の中断に関する裁判所の判断をみる前に、実行行為である注意義務違反に関する裁判所の判断をみてみます。
まず、注意義務に関し、裁判所は、
・・・羊蹄山・・・は,独立峰のために気象状況が変化しやすく,同山麓地域では,(事故当日)午前3時ころに北海道磯谷郡e町付近を通過した台風18号の影響を受け・・・同日午前5時45分に大雨・洪水・暴風警報,同日午前7時25分に暴風警報,大雨・洪水注意報,同日午後零時15分に強風注意報が発令されたが,事前に羊蹄山の比羅夫登山道から京極ピーク(・・・以下「山頂」という。)に至る下見をして登山道,標識,ケルン等の状況を確認していた被告人は・・・途中で脱落して下山した・・・や遅れてついてくるA,B,C及びDを生じさせながらも,その余の7名と自集団を形成して同日午前11時30分ころに9合目に到着したが,当時降雪時期直前を迎えていた9合目より上は・・・避難小屋付近では,同日午前9時30分に雨で体感風速も歩行にやや支障を来す毎秒15メートル,同日午後4時30分に雨で風速毎秒10メートル,翌26日午前9時30分計測の最低温度計の表示も3度で,風を考慮した体感温度としては零度を下回ったことからしても,強風低温等の悪天候が続くことが見込まれ,また,9合目から山頂にかけての概ね高い樹木のないガレ場続きには・・・複数の分岐点があり,白ペンキ書き方向指示の岩,木製標識,石積みケルン,低位張りロープ等が各所に存在していたとはいえ,当時の視界状況が濃霧で約10メートルから約30メートルであった関係上・・・これらが見落とされて登山道をたどる明確な目標物とはなりえないおそれがあり,現に,証人・・・が⑫の標識に全く気付かなかったことなどが認められ・・・被告人としては,ツアー客が被告人と離隔して独自に9合目付近から山頂に向かえば,被告人による適切な引率を受けることができないままに悪天候の中での不安・焦燥・誤解等も重なって状況判断を誤り,無意識的又は意識的に別道を辿るなどした末に山頂付近を迷走するなどし,体力消耗・強風冷気等の悪条件から凍死等で死亡することを十分に予見することができ,かつ,その死亡を回避するためにツアー客が自集団に合流するのを待って適切な引率を続けることも容易であったというべきであるから,被告人には,9合目付近でツアー客が自集団に合流するのを待ち,その安全を図るべき注意義務があったことは明白である。
札幌地判平成16年3月17日
として、上記Ⅱの時点の甲の行為を注意義務違反の実行行為と認定しています。
因果関係について
続いて、問題となった因果関係に関し、裁判所は、上記で引用したCの供述部分に続いて、
・・・Cと出会う前に⑳の旧小屋跡で撮影されたA及びBの写真の存在をも総合すると,A及びBは・・・9合目から地点・・・又は⑥の分岐を右折して⑳の旧小屋跡に到着し,その後,Cに発見された⑪付近の外輪山の外側下方に至ったことが認められるが,地点・・・の分岐は,左方向と右方向の道幅は右方向がやや広く,右方向の傾斜が山頂への接近を誤解させるようにも考えられる上・・・の供述によれば,⑥の分岐の「噴火口廻り道←左」「右→小屋」と読み取ることができる標識が同人の到着時に倒れていたことからすれば,A及びBが山頂への登山道を見失った結果⑳の旧小屋跡に向かったということがあり得る反面,地点Aの分岐では山全体を見渡すことができれば⑥に向かって左方向に進行するのが通常であること,⑥の分岐の「旧小屋跡」ではなく「小屋」に向かうことを誤解させかねない標識,⑳の旧小屋跡で写真撮影されたA及びBの比較的元気な様子等からすれば,A及びBが,意図的に⑳に向かった可能性も完全には排斥できないが,少なくとも,Cに発見された時点では,既に登山道を見失っていたことに疑いない。
札幌地判平成16年3月17日
そして,因果の経過に関する予見可能性としても,その細部にわたって予見が可能である必要はなく,被告人の適切な引率を受けられずに状況判断を誤った結果として死亡するという程度の基本的部分について予見が可能であれば足りるというべきであり,その予見可能性も認められる。
また,Cは,既に迷走状態に陥っていたA及びBを発見して下山を誘導しようとしたが,自らも確実に下山道を辿れなくなり,共に野営を余儀なくされたものであるが,これも被告人がCに9合目より上における前記注意義務と同様の落ち度で単独下山を許したことに誘発されたものであるから,このようなCの介在も被告人の過失とA及びBの凍死との間の因果関係を肯定するに妨げない。
そうすると,被告人の過失とA及びBの凍死との間に因果関係がある。
と判示して、因果関係を認定しています。
尚、この引用箇所の後半部分の「Cは・・・A及びBを発見して下山を誘導しようとしたが・・・下山道を辿れなくなり,共に野営を余儀なくされた・・・が,これも被告人がCに・・・前記注意義務と同様の落ち度で単独下山を許したことに誘発されたものであるから,このようなCの介在も被告人の過失とA及びBの凍死との間の因果関係を肯定するに妨げない。」とする箇所は、前述のCの行為が関与したことによる因果関係の中断を否定した部分です。
裁判所は、CがAおよびBと合流した後に下山ルートを見失い、ビバークを余儀なくされた点について、そもそも、甲がCを単独で下山させなければ、Cも単独でAおよびBの誘導をおこなう必要もなく、また、下山ルートを見失うようなことも起こり得なかったのだから、この点に関しても、元をたどれば原因は甲の行為にあるとして、因果関係の中断を否定しています。
この遭難事故の特殊性は、登山パーティーが途中で複数のグループに分かれたことから、引率者の指示が届かない場所において事故が発生することとなったこと、および事故発生までの事実経過を把握していたのは、死亡した被害者のみであるということです。
この遭難事故を業務上過失致死事件としての側面からみますと、主要な事実経過は、
ⅰ)Ⅱの甲による注意義務違反行為
ⅱ)甲がⅣの時点において、登頂した参加者を個別に下山させたこと
ⅲ)9合目付近からCと合流するまでの間のAとBの行動
ⅳ)AとBAとBがCと合流した後の行動
ⅴ)AとBの死亡の結果
に分けて考えることが出来ます。
しかし、このうち、ⅴ)は結果ということになります。
そこで、理屈の上では、実行行為とされるⅰ)の行為の後、ⅱ)~ⅳ)の事情がⅴ)の結果に影響を与えていると考えることができます。
ⅱ)の事実に関しては、甲およびC以外の登頂した参加者が目撃・経験していることであり、証明は比較的容易です。
しかし、ⅲ)に関しては、AおよびBが死亡していることから、事実関係を特定することは困難です。
この事故では、残されたカメラから旧小屋跡を通過した事実がわかっているだけであり、A及びBの行動は詳細には分かっておらず、また、証明することも困難です。
次にⅳ)の事情に関しては、Cが目撃・経験していることなので、Cの証言により、事実経過の特定および証明は可能ではあります。
しかし、判決でも「Cは,ともすればA及びBの死亡について何らかの責任を追及されかねない立場にあるが」と述べられているように、Cは、A及びBの死亡事故に関し、一定の利害関係を有しているともいい得ることから、Cの供述の信用性に関しては慎重に検討する必要があります。
このⅲ)の事実経過については、判決では、上記引用のように、「少なくとも,Cに発見された時点では,既に登山道を見失っていたことに疑いない」と抽象的な事実として認定することで、ⅰ)の行為の影響が継続していたことを認定しているとも考えられます。
更に、ⅳ)の経緯に関しては、C証言の信用性の状況証拠となり得る事実を積み重ねることにより、その経緯を認定するとともに、Cが下山ルートを見失った点についても、甲のⅱ)の行為の落ち度に原因があるとしています。
しかし、Cが下山ルートを見失ったことはⅱ)の甲の行為の落ち度によるものですが、ⅰ)とⅱ)は時間的・場所的に間隔があることから、ⅰ)とⅱ)の行為を同一の行為とは言い難いように思われます。
そうしますと、甲のⅱ)の落ち度が、甲のⅰ)の行為とⅴ)の結果との間の因果関係が中断しないことに、何故関係するのか多少疑問が残る所ではあります。
この点は、民事訴訟であれば、ⅰ)の行為とⅱ)の行為を一体のものとしてとらえ、9合目以上のⅰ)及びⅱ)のパーティーを分離した行為をひとつの注意義務違反行為ととらえれば、説明が容易となると思われます。
しかし、刑事事件では、訴因特定のため、過失行為も特定することが要求されますので、ⅰ)とⅱ)の行為を一体のものととらえるのは困難であったのかもしれません。
本記事の位置付け
この遭難事故の背景事情に関しましては、遠方からのツアー登山という性質から、天候が悪化しても登山を中止しづらかった、百名山ブームが影響している等多くの分析がされていますが、ここでは、主に法的な観点からの特殊性、問題点に触れてみました。