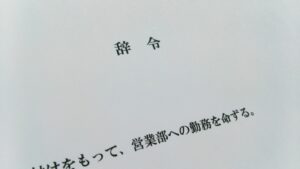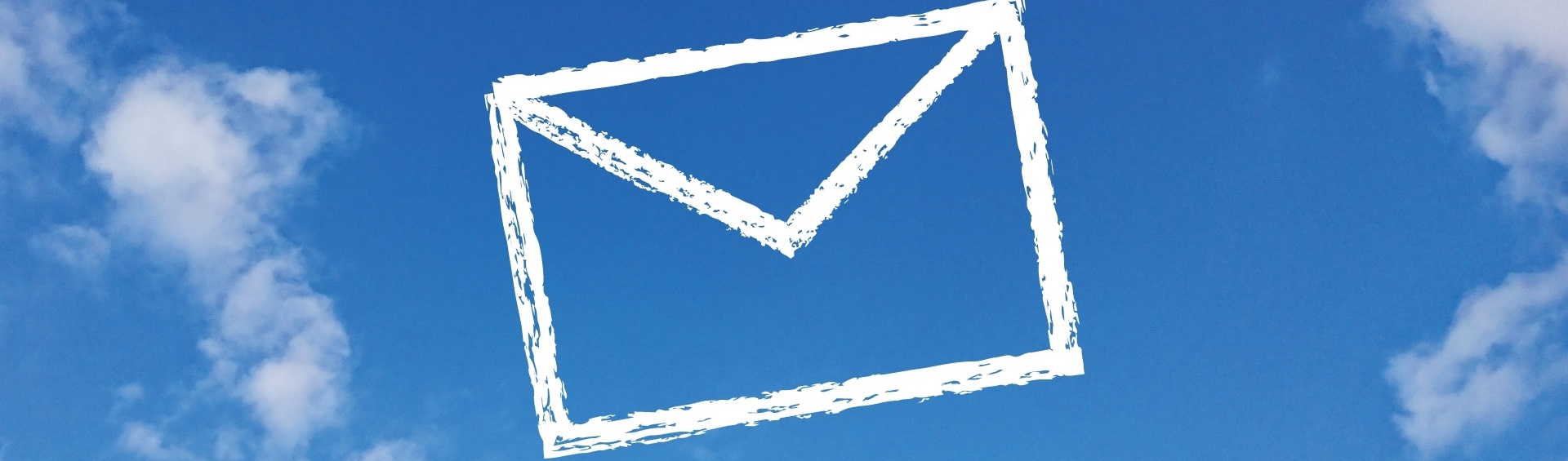- 解雇は、一般的には、普通解雇、懲戒解雇、整理解雇に分類されます。
- 会社は、退職勧奨をなし得ますが、限度を超えると不法行為となり得ます。
- 普通解雇をおこなう際には、会社は解雇日より30日以上前に解雇予告をするか、解雇予告手当を支払う必要が原則としてあります。
- 一定の事由により労働基準監督署長の解雇予告除外認定を受けた場合、解雇予告なく解雇できますが、解雇予告除外認定をうけていても即時解雇が違法と判断されることはあります。
- 従業員は、解雇予告された場合、解雇理由証明書を遅滞なく交付するよう請求できます。
- 一定の場合、解雇制限により解雇は出来ません。
目次
解雇の類型と有効性判断
解雇の分類
解雇は、一般的には、
Ⓐ普通解雇
Ⓑ懲戒解雇
Ⓒ整理解雇
に分類されます。
Ⓐ普通解雇は、Ⓑ懲戒解雇とⒸ整理解雇以外の解雇を意味しますので、解雇の問題に直面し、その問題がどの解雇に該当するかを考える際には、まず、Ⓑ懲戒解雇なのか、Ⓒ整理解雇であるかを意識することとなります。
解雇が無効となった場合の法的効果
会社も従業員を自由に解雇できるのではなく、特定の解雇が法的には無効とされる場合があります。
解雇が無効とされれば、雇用関係は継続していたこととなり、解雇を告げられ賃金が支払われなくなった日からの賃金を未払賃金として請求することが可能となります。
この解雇が無効となるかの判断(解雇の有効性判断)は、一般的には、Ⓐ~Ⓒの類型で異なった判断基準を採用する場合が多いことから、解雇の有効性を考えるにあたっても、解雇をⒶ~Ⓒの類型に区分して把握する実益があるといえます。
解雇通知書と解雇理由
解雇の類型については、解雇の際に解雇通知書(解雇予告通知書)を渡されていれば、その中に解雇理由も記載されていますので、Ⓐ~Ⓒのどの解雇に形式的に該当しているのかは分かります。
しかし、その場合でも、Ⓑ懲戒解雇は、就業規則に定められた懲戒解雇事由に該当する場合にしか有効になし得ないのが原則ですので、会社は、Ⓑ懲戒解雇と同時にあるいは懲戒解雇に代えてⒶ普通解雇とすることもあります。
また、解雇の有効性が裁判で争われた場合、会社がⒷ懲戒解雇としていても、懲戒解雇としては無効である場合、懲戒解雇の意思表示には普通解雇の意思表示も含まれているとして、普通解雇として有効であるかという検討がされることがあります。
退職勧奨
また、解雇を回避するために、いわゆる「肩たたき」により、会社が従業員に退職を促すことがあります。
このように、肩たたきにより退職を促すことを、「退職勧奨」といいます。
この退職勧奨は、形式的には、自主的な退職の形態をとりますので、解雇のカテゴリーには属さないこととなります。
しかし、実質的には解雇と異ならないような場合もあり、解雇の脱法的な行為として用いられることもあります。下記の記事でも触れましたが、会社も、従業員の退職に対する自発的な意思形成を害しない程度であれば、退職勧奨を適法になし得ますが、退職への働きかけが限界を超えたような場合は、不法行為となる余地もあります。
普通解雇について
普通解雇
それでは、まず、普通解雇についてみていきます。
普通解雇についても、一般的には就業規則に解雇事由が記載されています。心身の障害、勤務不良、事業の縮小などが挙げられているのが一般的です。
解雇予告と解雇予告手当
会社が、従業員を解雇する場合には、原則として、30日以上前に従業員に対して「解雇予告」をする必要があります(労働基準法20条1項)。
ただし、30日以上前に解雇予告をしなくとも、解雇予告をした日が実際の解雇日より30日より短い日数分の平均賃金以上の金額を「解雇予告手当」として支払うことにより解雇は有効となります(労働基準法20条2項)。
たとえば、解雇予告をした日が解雇日の20日前であった場合、労働基準法20条1項で定められた30日-20日=10日分の平均賃金を支払うことにより、有効に解雇できることになります。
例外として、天災事変などにより事業継続不可能な場合、従業員の帰責に基づく解雇の場合(労働基準法20条1項但書参照)、解雇対象者が日々雇用労働者、短期労働者(同21条参照)に該当する場合、解雇予告手当の支払いなく、即時解雇をなし得ることとなります。
しかし、その場合、労働基準監督署長の解雇予告除外認定が必要となります。この認定を欠いて即時解雇をしますと、刑事罰に処される可能性もあります(労働基準法119条1号)。
解雇予告の日数計算方法
この日数の計算については、民法の原則が適用されることから(法律上の日数の計算方法については、下記の記事で触れていますので参考にしてください。)、解雇予告をした日は日数の計算には含まれず、期日の末日の終了(末日の深夜12時)をもって期間が経過することとなります。
そこで、解雇予告手当を支払わない場合は、中30日を開けて解雇予告をする必要があります。例えば、4月30日の終わりをもって解雇をしようとする場合(4月30日までは雇用契約を継続する場合)、3月31日までに解雇予告する必要があります。5月1日までではありません。
解雇予告手当
もし、5月1日に解雇予告する場合には、少なくとも1日分の平均賃金を、GW開けの5月9日に解雇予告するのであれば、少なくとも9日分の平均賃金を、解雇予告手当として支払わなければなりません。
解雇予告手当の平均賃金の計算については、直前3ケ月間に支給された賃金総額を日数で割った金額が1日分の平均賃金とされています。
日数計算には、休日も含まれますが、数年前に解雇予告する等、解雇日よりあまりにも早い解雇予告は、労働契約法14条等との関係で無効とされる余地もあり得ることから注意が必要です。
尚、解雇予告手当の支給が必要でありながら、会社が支給しなくても、裁判では、解雇予告から30日後に解雇自体の効力は生じると判断される場合があり得ます。
解雇予告除外認定
上記のように、労働基準監督署長の解雇予告除外認定を受け、解雇予告手当を支給せず即時解雇することがあります。
しかし、この解雇予告除外認定は、解雇予告除外事由に該当する事実の有無を確認する労働基準監督署長の認識とされ、私法上の解雇予告手当不支給による即時解雇の有効性判断に影響を与えるものではないとされ、裁判上、そのような解雇が違法と判断されることがあり得ます。
解雇予告除外認定については、下記のブログ記事で説明しておりますので、参考にしていただければと思います。
解雇理由証明書
従業員は、解雇予告をされた場合、退職日までの間は、会社に対して解雇理由を記載した書面(解雇理由証明書)を遅滞なく交付するよう求めることが出来ます。解雇理由について疑義がある従業員は、解雇理由証明書の交付を求めることとなります。
この解雇理由証明書は、解雇の有効性を争う場合にも意味を持つこととなります。
解雇制限と解雇無効
次に解雇の有効性についてみてみます。
まず、
㋐業務上の負傷・疾病の療養のための休業期間およびその後30日間
㋑産前・産後の休業期間およびその後30日間
は解雇制限期間として解雇できないのが原則です(労働基準法19条)。
更に、解雇も会社が自由になし得るものではなく、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」には解雇は無効とされます(労働契約法16条)。
解雇が無効とされた場合、解雇された従業員は、上記に述べたように雇用契約は継続していたこととなり、未払い賃金を請求し得ることとなります。