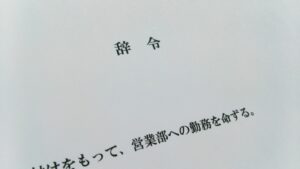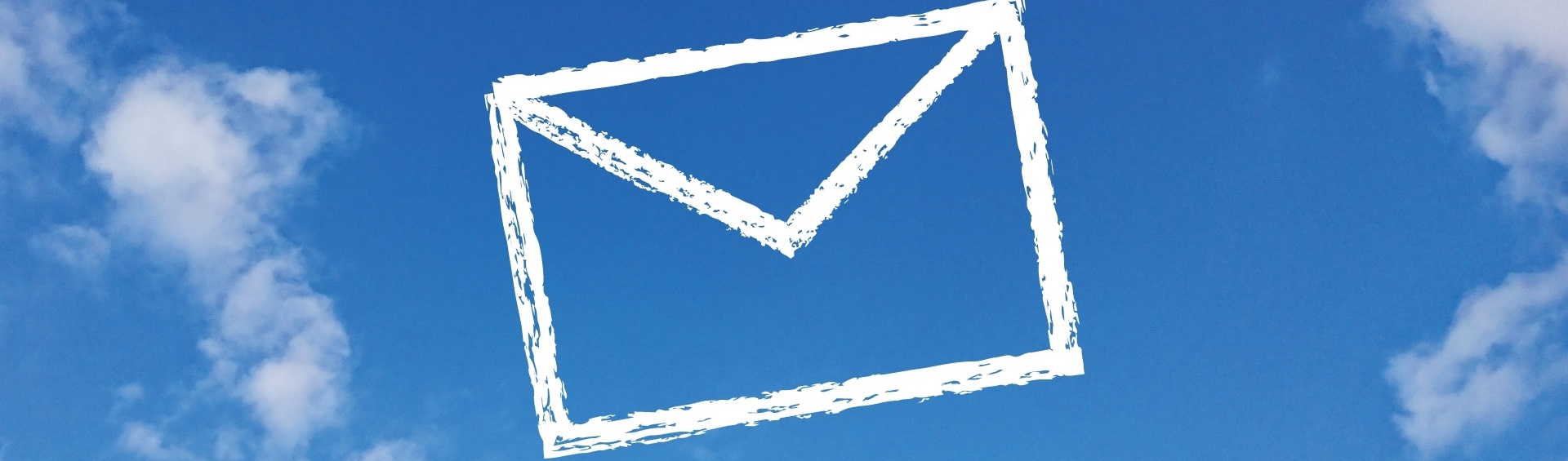遭難者救助時の事故の問題
今回は、(e)遭難者の救助時の事故において、救助者に対し責任を追及した登山事故について考えてみます。
このようなケースでは、遭難した登山者の救助時、救助者の落ち度が疑われるような事情により、遭難者が新たな事故(二重事故)に巻き込まれた場合、救助者にいかなる法的責任が生じるのかが問題となります。
尚、パーティーでの登山中、メンバーのひとりが骨折等の負傷により自力での下山が困難となり、他のメンバーが負傷者を背負って下山を試みたところ、バランスを崩し、背負っていた負傷者を背中から落とし、負傷していたメンバーを更に負傷させたようなケースは、通常のパーティー登山の過失、安全配慮義務違反の問題に含まれると考えられます。
そこで、ここではその類型の事故は取り扱わないこととします。
ここでは、遭難者の同行者ではない救助者の法的責任について考えることとします。
救助者の類型について
遭難者の同行者ではない救助者は、大きく分けると、
①警察官・消防隊員等の公務員の救助隊員
②山岳遭難防止対策協会(遭対協)、山小屋関係者(前記と重なるケースも多いと思われます)等の民間人
に分類することができます。
しかし、訴訟において救助者の責任が問題とされたのは、確認できる範囲では、前者①の救助者による二重事故のケースです。
これは、
- ①公務員の救助隊員と②民間の遭対協の救助隊では、求められる注意義務・救助義務に違いがあること
- 二重事故が生じるような山岳遭難の救助活動には、公務員である救助隊員が出動するケースが多いと思われること
- ①の場合、救助者は公務員であることから、国家賠償法に基づく損害賠償義務を負うのは国・公共団体であり、救助者である公務員個人は損害賠償義務を一般的には負わないこと(国家賠償法1条2項参照)などの事情が、被害者あるいはその親族の訴訟提起に対する心理的抵抗感を低くすると考えられること
等が理由であるように思われます。
裁判に発展した事故の具体例
この類型の裁判にまで発展した登山事故としては、
11)厳冬期の積丹岳にバックカントリーのスノーボードを目的として入山した人が遭難、一度は警察の山岳遭難救助隊に発見・保護されたものの、下山活動開始直後に発生した滑落等により、救助活動が成功せず、遭難者が凍死した積丹岳遭難事故(札幌地判平成24年11月19日、札幌高判平成27年3月26日、最判平成28年11月29日)
12)12月初旬の富士山山頂付近からの下山中に滑落した遭難者を救助するよう要請を受け、ヘリコプターで救助に向かった消防航空隊が、高度3500m付近において遭難者を吊り上げ機内に収容しようとしている最中に、遭難者が空中から落下し、胸部および頭部損傷兼寒冷死により死亡した富士山ヘリコプター事故(京都地判平成29年12月7日)
があります。
この2つのいずれの事故におきましても、遺族の方は、救助隊員に過失があったとして、救助隊員が所属する地方公共団体に対し、国家賠償法に基づく損害賠償を求め、訴訟を提起しました。
このうち、
11)積丹岳遭難事故の訴訟では、1審で請求が一部認容され、控訴審で認容額が拡張、上告後に控訴審判決が確定しました。
一方、
12)富士山ヘリコプター事故の訴訟では、一審で原告の請求は棄却されています。
このように2つの事故の裁判の結果は異なっています。
尚、2つの事故の裁判につきましては、下記の記事で詳しく扱っています。
2つの救助時事故の過失認定について
この2つの遭難者救助時の事故のうち、12)富士山ヘリコプター事故は、㋐独立峰である富士山の3500m付近での冬季の日没間近という過酷な条件下での、㋑救助用ヘリコプターの性能限界を超えたとされる高度での救助活動中に発生した事故でした(県警の救助ヘリコプターが同じ遭難事故による他の負傷者の救助をおこなった関係で、消防航空隊のヘリコプターに対しては、冬季の午後3時過ぎに正式救助出動要請されたという事情がありました。)。
それらのことから、救助者に要求された注意義務の水準は相当程度低いものであったと考えられます。
このこともあり、裁判では、救助者の過失は否定されました。
一方、11)積丹岳遭難事故も厳冬期における吹雪の中の救助活動であり、救助隊員も、遭難者発見前に相当時間壺足で登高し遭難者を捜索していたことからすると、体力消耗もあり、救助隊員に要求された注意義務の水準はそれ程高いものではなかったとも考えられます。
ところで、11)積丹岳遭難事故では、①雪庇の踏み抜きにより滑落した時点の行為と、その後の②ハイマツに固定していたストレッチャーが滑落した時点の救助隊員の行為の2つの行為について過失が問題となりました。
1審では、①雪庇の踏み抜きにより滑落した時の行為に過失を認定しましたが、控訴審では、②ハイマツに固定していたストレッチャーが滑落した時点の救助隊員の行為に過失を認定しています。
この2つの行為を比較しますと、救助者のストレッチャーの固定行為上の不備という、外的要因の影響が比較的少ない行為の方が、雪庇の踏み抜きという外的要因の影響の大きい行為より、過失の検討に際し不確実要因を考慮する必要性が低く、過失の認定が安定するようにも思われます。
また、遭難者の状態、気象状況、遭難者の保護後の移動開始時間などを考えますと、雪庇の踏み抜きという行為は、ストレッチャーの固定不備の原因行為に比べると、雪庇の状態によっては、必ずしも過失の程度が高いと認定しうるものではないと考えられます。
このような過失認定の安定性の問題もあり、控訴審では雪庇の踏み抜き時点ではなく、ストレッチャーが滑落した時点の行為を過失行為と認定したとも考えられます。
11)積丹岳遭難事故および12)富士山ヘリコプター事故の過失の認定からもわかりますように、山岳遭難者の救助活動においては、遭難発生地点の地形、あるいは発生時および救助行動時の気象条件が厳しいことも多く、外的要因の影響が大きい事故類型といえます。
そのこともあり、過失を検討する際に、不確実要因の考慮が必要なケースが多く、救助者の注意義務の水準は高いものとはならず、過失は認定され辛いものとなります。
2つの判決から考えられること
11)積丹岳遭難事故の判決と12)富士山ヘリコプター事故の判決からしましても、遭難者救助時の登山事故においては、一定の法律上の救助義務を負う救助者が、救助に際して明らかに合理的と認められない方法をとった場合に過失が認定される可能性があります。
しかし、過失認定において救助者に求められる注意義務の水準は、具体的な状況により変わると考えられています。
このようなことからも、救助者の過失が問題となる登山事故が発生し、救助者の過失について検討する際に、11)積丹岳遭難事故と12)富士山ヘリコプター事故の判決文を参考にする場合、検討を加える事故における救助者の属性、救助時の具体的な状況など諸事情と、11)積丹岳遭難事故および12)富士山ヘリコプター事故における、それらの事情の相違を十分に意識する必要があります。