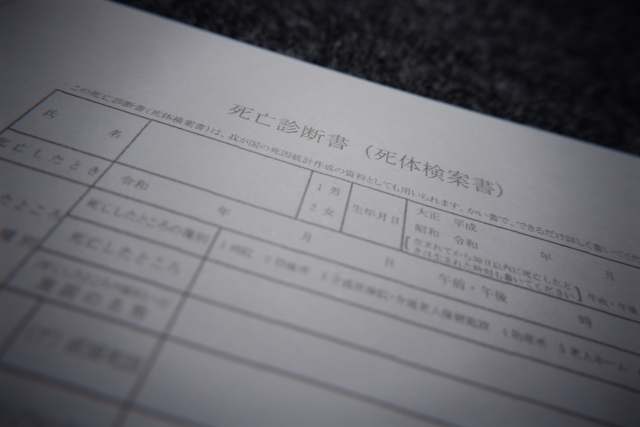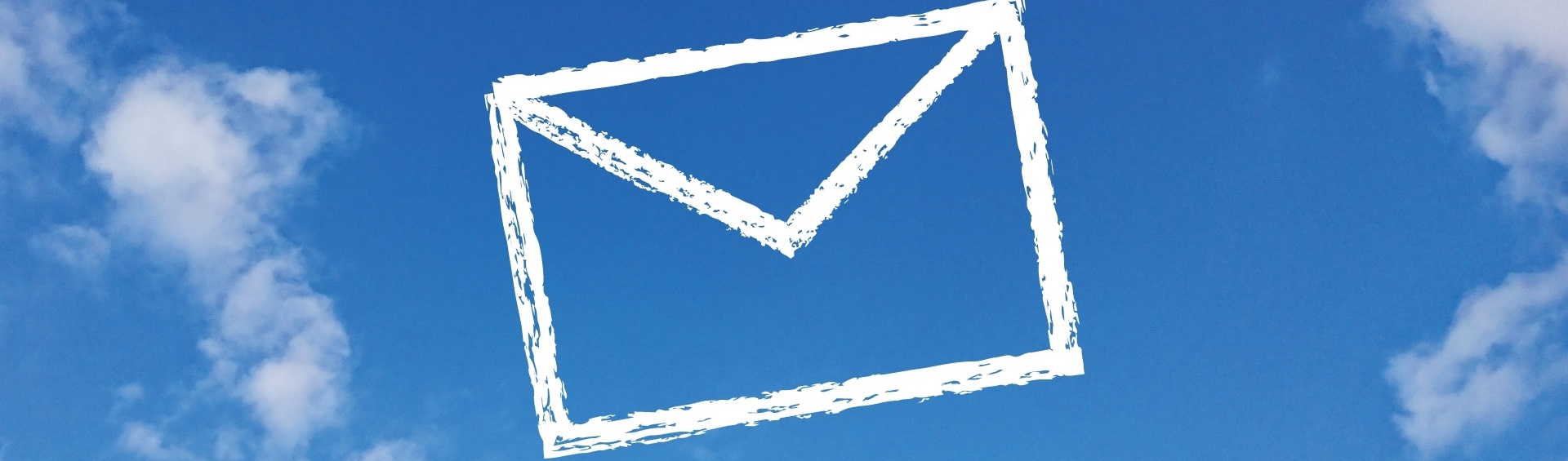相続が開始しますと、原則として、被相続人の財産(相続財産)と相続人の財産が相続人のもとで一体のものとなります。
そのため、相続の発生により、被相続人の債権者あるいは相続人の債権者は、保有する債権の回収に関して不利益を被ることがあります。
これを回避するための方法として、民法には、財産分離の制度が用意されています。
ここでは、この財産分離とはどのようなものなのか、どのような場合に認められるかについて、条文、判例などをみながら解説します。
目次
財産分離とは
相続により不利益を受ける債権者の存在
相続が開始しますと、被相続人の財産(相続財産、遺産)と相続人の固有の財産が一体となり、混合することとなります。
しかし、相続財産にも、相続人の固有の財産にも、プラスの財産(以下「資産」といいます。)と共に、債務が存在することもあります。
たとえば、相続人がひとりの場合において、下記の3つのケースにおいて、相続が開始した場合を考えてみます。
尚、ここでは、抵当権、質権などは考えないこととします。
ケース1
・相続財産として資産が300万円、債務が100万円(債権者はA1名)
・相続人の固有の財産として、資産が300万円、債務が100万円(債権者はB1名)
ケース2
・相続財産として資産が300万円、債務が100万円(債権者はC1名)
・相続人の固有の財産として、資産が100万円、債務が500万円(債権者D1名)
ケース3
・相続財産として資産が300万円、債務が500万円(債権者はE1名)
・相続人の固有の財産として、資産が100万円、債務が50万円(債権者F1名)
ケース1では、相続開始後の相続人の資産は600万円、債務は200万円となります。
このため、相続開始後も、被相続人の債権者(以下「相続債権者」といいます。)であるAも、相続人の債権者であるBも、計算上は債権回収が可能です。
次に、ケース2では、被相続人は、生前は資産の方が多く、被相続人の債権者Cは、計算上、債権の全額回収が可能でした。
相続開始後は、被相続人の債務も相続人が相続することから、Cの債権の債務者も相続人へと変わります。
しかし、ケース2では、相続人は、相続開始前から債務超過の状態にあり、相続開始後も資産が400万円、負債が600万円と債務超過の状態が続きます。
相続開始前は、被相続人は資産の方が多く、相続債権者Cは、計算上は債権の全額回収が可能でした。ところが、相続開始後は、計算上一部しか回収できなくなります。
ケース3では、被相続人は、資産より債務の方が多い債務超過の状態となっていました。そして、相続開始後は、相続人の資産は400万円、負債は550万円となります。
しかし、相続開始前は、相続人は資産の方が多く、相続人の債権者Fも、計算上は債権の全額回収が可能でした。ところが、相続開始後は、計算上、一部しか回収できなくなります。
この場合、相続人が相続放棄するケースが多いものと思われますが、ここでは、相続放棄は考慮しません。
このケース1では、相続の開始によって、被相続人の債権者Aも相続人の債権者Bも、計算上は、不利益を特に被ることとはなりません。
しかし、ケース2では、相続の開始により、相続債権者であるCは、債権の回収が困難になるという不利益を被ることとなります。
また、ケース3では、相続の開始により、相続人の債権者であるFは、債権の回収が困難になるという不利益を被ることとなります。
財産分離とはどのようなものでしょうか
財産分離とは、上記のケース2およびケース3のように、相続が開始し、被相続人の残した相続財産と相続人の固有の財産が相続人のもとで混合することにより、不利益を被ることを防止するために、相続債権者、相続人の債権者、または受遺者による家庭裁判所への請求によりなされる、相続財産と相続人の固有の財産を分離して清算する制度のことです(民法941条~950条)。
この財産分離の制度としては、相続開始により、
①上記のケース2のように、相続債権者(被相続人(相続財産)の債権者)が損害を被る場合に、相続債権者、または受遺者から請求がなされる第1種財産分離
②ケース3のように、相続人の債権者が損害を被る場合に、相続人の債権者から請求がなされる第2種財産分離
があります。
第1種財産分離について
上記のように、相続債権者、または受遺者から請求がなされる第1種財産分離については、民法941条1項、2項に次のように規定されています。
(相続債権者又は受遺者の請求による財産分離)
民法941条
第九百四十一条 相続債権者又は受遺者は、相続開始の時から三箇月以内に、相続人の財産の中から相続財産を分離することを家庭裁判所に請求することができる。相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、その期間の満了後も、同様とする。
2 家庭裁判所が前項の請求によって財産分離を命じたときは、その請求をした者は、五日以内に、他の相続債権者及び受遺者に対し、財産分離の命令があったこと及び一定の期間内に配当加入の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
(3項省略)
そして、この第1種財産分離の効果については、942条および947条において、
(財産分離の効力)
第九百四十二条 財産分離の請求をした者及び前条第二項の規定により配当加入の申出をした者は、相続財産について、相続人の債権者に先立って弁済を受ける。(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
民法942 条、947条
第九百四十七条 相続人は、第九百四十一条第一項及び第二項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。
2 財産分離の請求があったときは、相続人は、第九百四十一条第二項の期間の満了後に、相続財産をもって、財産分離の請求又は配当加入の申出をした相続債権者及び受遺者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。
と規定されています。
このように、第1種財産分離の請求または配当加入の申出をした相続債権者および受遺者は、相続財産から優先的に弁済をうけることができます。
しかし、第1種財産分離の請求または配当加入の申出をした人が相続財産から全額の回収ができなかったような場合、未回収分については民法948条に次のような規定がおかれています。
(相続人の固有財産からの弁済)
民法948条
第九百四十八条 財産分離の請求をした者及び配当加入の申出をした者は、相続財産をもって全部の弁済を受けることができなかった場合に限り、相続人の固有財産についてその権利を行使することができる。
これにより、相続財産から全額の弁債が受けられなかった相続債権者は、相続人の債権者への弁済後、未回収分について、相続人の固有の財産から弁済を受けることができることとなります。
相続人固有の財産からは、従前からの相続人の債権者が優先して弁済を受けることとなります。
第2種財産分離について
相続人の債権者から請求がなされる第2種財産分離については、民法950条において次のように規定されています。
(相続人の債権者の請求による財産分離)
民法950条
第九百五十条 相続人が限定承認をすることができる間又は相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、相続人の債権者は、家庭裁判所に対して財産分離の請求をすることができる。
2 第三百四条、第九百二十五条、第九百二十七条から第九百三十四条まで、第九百四十三条から第九百四十五条まで及び第九百四十八条の規定は、前項の場合について準用する。ただし、第九百二十七条の公告及び催告は、財産分離の請求をした債権者がしなければならない。
同条の1項では、第1種財産分離の場合の941条1項と同様、相続人の債権者が、家庭裁判所に第2種財産分離の請求をすることができることを規定しています。
そして、第2種財産分離の効力については、950条2項において、相続の限定承認に関する規定、第1種財産分離に関する一部の条文が準用されています。
これらの準用により、第2種財産分離にも、第1種財産分離とほぼ同様な効果が生じることとなります(若干の相違はありますが、ここでは詳述しません。)。
第1種財産分離が認められる要件の問題
相続債権者あるいは受遺者からの第1種財産分離の請求は、家事審判として申し立てられることとなります(家事事件手続法39条、別表1の96参照)。
家庭裁判所は、審判により財産分離を命ずることとなります。
そこで、どのような場合に、家庭裁判所が財産分離を命ずる審判ができるのかという点が、債権者は、どのような場合に財産分離により優先的に弁済を受けることができるかという点と関連して問題となります。
この点が問題とされる背景のひとつとして、学説上、家庭裁判所は財産分離の審判を、
①民法941条1項の要件をみたすときには命ずる必要があるとする「絶対説」
②941条1項の要件とともに、財産分離の必要性が認められるときに命ずることができるとする「裁量説」
の2つが唱えられていたことがあります。
財産分離に関する裁判について
事件の概要
相続分離の審判を家庭裁判所がどのような場合になし得るかという問題が争点となった事件としては、最決平成29年11月28日があります。
この事件は、保佐人か選任されていた被相続人が、後見開始となった後、死亡したところ、後見事務の費用を立替えていた後見人が第1種財産分離を請求したものです。
1審家裁の審判
この事件の第1審(大阪家裁審判平成29年2月15日)では、
・・・債権者としては,保佐人であった・・・が保佐事務において立て替えた費用及び報酬につき請求権を有しているほか,被相続人が生前に委任した弁護士が被相続人が当事者となっている民事訴訟に関する弁護士報酬等の請求権を有していると考えられ・・・被相続人の財産を生前から事実上管理していた相続人・・・は,後見人が職務上,被相続人の財産の開示,引渡し等を求めても応じることはなく,被相続人が・・・に死亡したことにより,前記被相続人の債権者の債権の引当てとなるべき被相続人の財産と相続人が被相続人の相続開始前から有する固有財産(債権の引当てとなる固有の財産を有すると認めることはできない。)とが混合するおそれが生じ・・・相続財産の分離に関する処分申立て事件については,分離することを相当と認め,上記経緯に照らし被相続人の相続財産につき財産管理人を職権で選任することとし,主文のとおり審判する。
大阪家裁審判平成29年2月15日
としています。
抗告審の判断について
この審判に対し、2名いた相続人のうち、1名が抗告を申し立てました。
その抗告審(大阪高決平成29年4月20日)は、
・・・第1種財産分離は,相続人の固有財産が債務超過の状態にある場合(もしくは近い将来において債務超過となるおそれがある場合)に相続財産と相続人の固有財産の混合によって相続債権者又は受遺者の債権回収に不利益を生じることを防止するために,相続財産と相続人の固有財産を分離して,相続債権者又は受遺者をして相続人の債権者に優先して相続財産から弁済を受けさせる制度で・・・申立人の相続債権,申立期間といった形式的要件が具備されている場合であっても,上記の意味における財産分離の必要性が認められる場合にこれを命じる審判をなすべきものと解するのが相当である・・・(が)本件においては,抗告人及び相続人・・・について,その固有財産が債務超過の状態(もしくは近い将来において債務超過となるおそれがある状態)にあるどうかは明らかではなく,財産分離の必要性について審理しないまま,財産分離を命じた原審の判断は相当でなく,この点について原審においてさらに審理を尽くす必要があるというべきである。
大阪高決平成29年4月20日
として、原審判を取消し,原審への差戻しの決定を下しています。
許可抗告審の判断
この抗告審の取消決定に対する許可抗告審(最決平成29年11月28日)は、
・・・財産分離の制度は,相続財産と相続人の固有財産とが混合することによって相続債権者又は受遺者(以下「相続債権者等」という。)がその債権の回収について不利益を被ることを防止するために,相続財産と相続人の固有財産とを分離して,相続債権者等が,相続財産について相続人の債権者に先立って弁済を受けることができるようにしたもので・・・このような財産分離の制度の趣旨に照らせば,家庭裁判所は,相続人がその固有財産について債務超過の状態にあり又はそのような状態に陥るおそれがあることなどから,相続財産と相続人の固有財産とが混合することによって相続債権者等がその債権の全部又は一部の弁済を受けることが困難となるおそれがあると認められる場合に・・・財産分離を命ずることができるものと解するのが相当
最決平成29年11月28日
として、抗告審の原審取消し決定を是認しています。
第1審と抗告審および許可抗告審の判断の相違
この事件では、第1審の家裁は、民法941条1項の財産分離の形式的要件の具備から財産分離の審判をしています。
これは、上記の学説では、絶対説に近い考え方を採用したものと考えられます。
一方、許可抗告審は、財産分離を認めるには、民法941条1項の要件に加え、「相続財産と相続人の固有財産とが混合することによって相続債権者等がその債権の全部又は一部の弁済を受けることが困難となるおそれがあると認められる」ことが必要であるとしています。抗告審も同様な判断をしています。
この抗告審および許可抗告審の判断は、上記の学説の裁量説に基づくものといえます。
この許可抗告審である最高裁判所の決定により、実務的には、民法941条1項の要件に加え、財産分離の必要性が認められる場合に、第1種財産分離が認められ、相続債権者は、相続財産から優先して弁済を受け得ることとなると考えられます。
債権者が弁済確保のために財産分離をなしうるケース
上記の最決平成29年11月28日の趣旨は、第2種財産分離についても妥当し得るものだと考えられます。
そこで、上記のケース2のCのような相続債権者、あるいは上記のケース3のFのような相続人の債権者は、民法941条1項あるいは950条1項の要件をみたし、更に、相続開始により、債権の弁済をうけることが困難となるおそれのある場合に、財産分離により、債権の回収を確保し得る余地があることとなります。
そのような場合は、相続開始により不利益を被る恐れのある相続債権者、あるいは相続人の債権者は、財産分与についても検討する価値はあろうかと思われます。