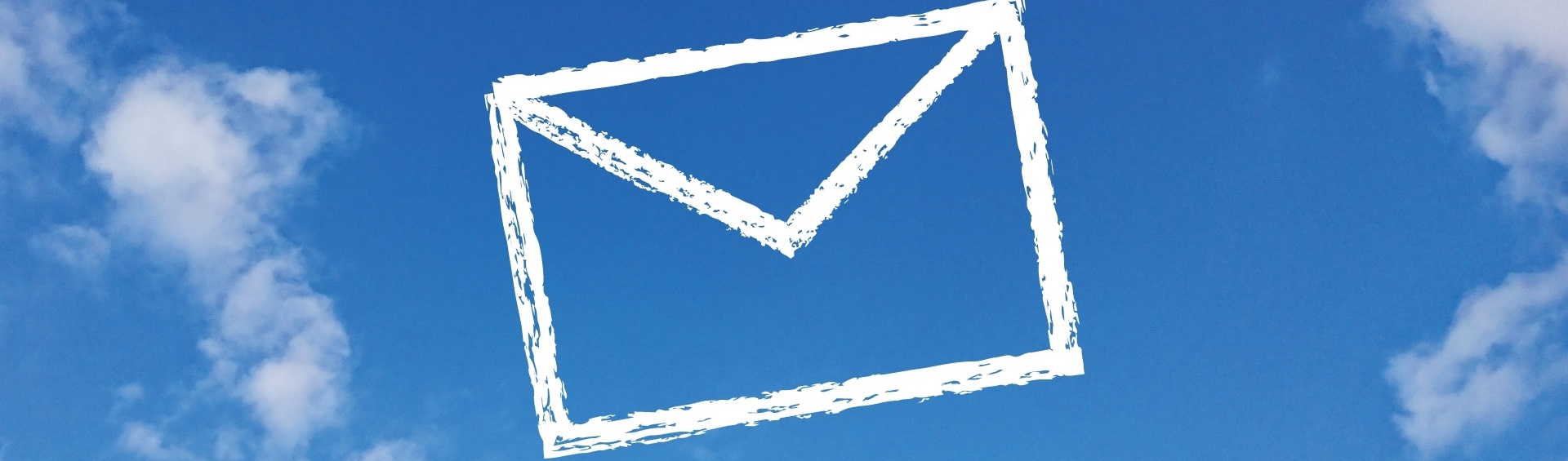民法では、遺言作成時、遺言者に「遺言能力」といわれる一定の能力があることを求めています。
ここでは、民法の遺言能力に関連した条文を確認しながら、その意味、遺言能力の存否が相続に与える影響、遺言能力に疑義がある場合の相続人の争い方、および遺言能力存否の判断基準などについて解説した上で、遺言能力が問題となった裁判例をご紹介し、その判決文において、どのように遺言能力の存否を判断しているかを確認してみます。
目次
遺言能力とはどのようなものでしょうか
遺言能力の問題について
遺言能力とは、一般的には、遺言を単独で有効になしうる法律上の地位、資格のこととされています。
この遺言能力については、民法に規定がおかれていますが、どのような場合に遺言能力が認められるかについては、条文の文言上、明確に規定されているわけではありません。
そのこともあり、遺言時に遺言者が遺言能力を有していたのかが、相続開始後、遺言の有効性の問題として顕在化することがあります。
とくに、高齢者の遺言能力が、認知症との関係で問題となるケースが散見されます。
このこともあり、近時では、年齢が高い方の遺言作成時には、将来の親族間における相続に関する紛争発生の可能性を鑑み、医師の診断書、長谷川式認知症スケールなど、遺言作成時点に遺言者の意思能力に関する資料を収集しておくこともあります。
ただし、遺言能力の存否の争いが裁判にまで発展したとき、医師の診断書、長谷川式認知症スケールが、決め手にならないケースもあることには注意が必要です。
遺言能力に関する民法の規定
遺言能力について、まず、法律上の根拠として民法の規定をみてみます。
民法では、961条~963条において、
(遺言能力)
民法961条~963条
第九百六十一条 十五歳に達した者は、遺言をすることができる。
第九百六十二条 第五条、第九条、第十三条及び第十七条の規定は、遺言については、適用しない。
第九百六十三条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。
として、遺言能力に関する規定をおいています。
この963条から、遺言者には、遺言作成時に遺言能力が必要であることがわかります。
また、961条からは、遺言能力は、15歳以上の者でなければ認められないことがわかります。
更に、962条から、遺言に関して、5条(未成年者の行為能力の制限に関する規定)、9条(成年後見人に関する規定)、13条(保佐人の同意を要する行為に関する規定)、17条(補助人の同意を要する旨の審判に関する規定)の適用を除外していることから、一般的な法律行為とは異なり、未成年者、成年後見人、被保佐人および被補助人も遺言作成をなし得、遺言能力が認められ得ることがわかります。
このように、行為能力は遺言能力の前提とはされていません。
しかし、成年後見人に関しては973条に、
(成年被後見人の遺言)
民法973条
第九百七十三条 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。
2 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。
と規定し、成年後見人が事理弁識能力を一時的に回復したときに、医師2人以上の立会いを要求しています。
このように、一般的な法律行為に比べ、遺言能力は広く認められています。
しかし、意思能力(民法3条の2)は必要とされています。
遺言能力と意思能力、行為能力
上記のように、962条において、行為能力の制限に関する規定を適用除外にするなど、民法は、一般的な法律行為(契約締結など)をおこなう場合に要求される能力と比較し、遺言を作成する遺言能力については、ハードルを低く設定しています。
これは、一般的な法律行為とは異なり、遺言は遺言者の死後に効力を生じるものであり、遺言により遺言者は直接損害を被ることは少なく、遺言者保護の要請が低いからだと考えられています。
また、遺言の性質上、代理が馴染まないことも関係しているとされています。
ただし、意思能力は必要とされています。
遺言能力のない状態で作成された遺言の効力
963条から、遺言作成時に遺言者は、遺言能力を有している必要があります。
遺言能力を欠く状態で作成された遺言は無効となります。
遺言能力を欠く状態で作成されたとして、遺言無効が認定された裁判例は少なくありません。
尚、遺言作成時に遺言能力があれば、その後遺言能力を欠く状態となっても、遺言は無効となりません。
遺言能力は、遺言を作成する時点に存在すれば足ります。
遺言能力の判断方法について
遺言能力が訴訟上で争われた場合、主に、
- 遺言時における遺言者の精神上の障害の存否、内容および程度
- 遺言内容それ自体の複雑性
- 遺言の動機・理由、遺言者と相続人または受遺者との人間関係・交際状況、遺言に至る経緯
などの事情を総合的に考慮して判断するとされています(東京地方裁判所民事部プラクティス委員会第二小委員会「遺言無効確認請求事件を巡る諸問題」判例タイムズNo.1380、pp10-11参照)。
遺言能力を争う場合
遺言の能力を欠く状態で作成された遺言は無効となりますので、相続の手続き上の対応としては、その無効とされる遺言がなかったものとして扱い、遺産分割調停をおこなえばよいこととなります。
しかし、相続人、あるいは遺言能力が問題となっている遺言で遺贈を受けた受遺者から、「遺言は有効だ!」との異論が唱えられ、その紛争の解決が当事者間で困難な場合、遺産分割調停の申立て、あるいは遺言無効確認請求訴訟の提起が検討されることとなります。
尚、自筆証書遺言のみではなく、公正証書遺言に関しても、遺言能力が問題となることがあります。
下記に引用する近時の裁判例(東京地判令和3年10月21日)でも公正証書遺言において、作成時の遺言能力を否定し、遺言を無効と判断しています。
遺言能力が争われた裁判例
上記で触れました、公正証書遺言が遺言能力の問題から無効とされた裁判例として、東京地判令和3年10月21日があります。
この裁判で問題となった遺言書は、一過性脳虚血により意識を消失、脳梗塞を発症、さらに併発した病気の治療のため入院していた被相続人が、一時退院したものの、病気で発熱し再入院、更に退院、一時帰宅後、医師である被告の勤務先である別の病院に入院し、その折に、公証役場において作成されたというものでした。
尚、当該公正証書遺言の立会人として、被告訴訟代理人の弁護士が名を連ねていました。
この事件の判決において、
・・・(遺言者)のHDS-Rの結果は,平成・・・月から平成・・・までは20点以上であったが,同年・・・月以降,20点を下回るようになり,平成・・・月には16点,同年・・・月及び・・・月には14点であったこと,同じくMMSEの結果は,平成・・・月から平成・・・月までは18~22点で推移・・・・月には13点となり,同年・・・月も19点であったこと,特に時間や場所に関する見当識についての質問に答えられないことが多いこと,本件遺言公正証書作成時に公証役場で作成された筆談用質問票には,(遺言者)の自署があるものの,年月日について,平成・・・年と書くべきところを平成・・・年と書き,・・・月と書くべきところを・・・月と書いていることなどが認められる。
東京地判令和3年10月21日
また,・・・・主治医の・・・医師は,平成・・・年,認知症が徐々に進行している旨,脳梗塞後遺症と認知症で自立生活は困難,見守り,介護が必要である旨を指摘していること,看護記録等においても,離棟,見当識障害,記憶障害,便失禁等が繰り返し指摘されていること,特に平成・・・年に入ってからは,・・・既に死亡している弟を探しに行こうとするなどの見当識障害ないし記憶障害を伴うものと思われる行動をとっており,特に本件遺言公正証書作成の翌日にもそのような行動をとったことが認められる。
これらによれば・・・病院入院後,認知症が進行し,本件遺言公正証書作成時において,少なくとも中等度の認知症にり患していたものと認めることができ・・・以上の事実に加え,・・・本件遺言公正証書の内容は・・・遺産のうち・・・市の不動産を原告ら及び被告が3分の1ずつ取得するほかは,全て被告が取得することとする内容となっており,明らかに被告に有利な内容となっていること,・・・本件遺言公正証書の作成過程は,被告夫妻が・・・弁護士に依頼をした上で,(遺言者)と同弁護士らの面談にも同席し,聞き間違い等がある場合には,これを手助けするなどして,公正証書の原案を作成したこと,その際,被告は,(遺言者)が答えやすいように不動産の所在地等を記載した書面・・・を作成したことなどが認められ,これらの作業が被告夫妻の意向が反映される状況下で作業が行われていることからすれば,被告の誘導ないし働き掛けによって本件遺言公正証書の作成作業が行われたものと推認される。さらに,・・・本件遺言公正証書作成時に使用された筆談用質問票が上記書面と似通った形式,内容であったため,遺言能力の有無に関係なく記入することが可能であったことが推測される上,本件遺言公正証書・・・条・・・項の内容は相当に複雑なものであり,(遺言者)がこれを理解することは困難を伴うものと考えられるほか,上記のとおり本件遺言公正証書の作成作業に関わっていた被告自身も同項の内容を正解しておらず・・・この点について・・・弁護士らから(遺言者)に対して具体的な説明等がされたこともうかがわれない。
これらの事実を総合すると,Bについて,本件遺言公正証書作成当時,推定相続人らの取得財産等について検討し,遺言の内容及び意義を理解した上で遺言する能力が失われていたものと認めるのが相当である。
として、公正証書遺言の作成時、遺言者の遺言能力は欠如していたと認定し、遺言を無効と判断しています。
この裁判例では、遺言作成前の遺言者の病状、入院時の言動および認知症の進行状況について検討していますが、これは上記の遺言能力の判断時の考慮要素の1の検討に該当します。
また、「本件遺言公正証書・・・条・・・項の内容は相当に複雑なものであり,(遺言者)がこれを理解することは困難を伴うものと考えられるほか・・・」の部分は、上記の考慮要素の2の検討となります。
更に、被告の勤務する病院に入院していたこと、公正証書遺言の立会人を被告の訴訟代理人が務めていること、被告夫妻の遺言作成関与状況の認定、遺言の内容が被告に有利なものであったことなどは、上記の考慮要素3といえます。
公正証書遺言に関しては、公証人が遺言者本人と面接するのが遺言作成時1回のみであることも多く、公証人が遺言者の遺言能力を判断するのにも一定の限界があります。
そのこともあり、この事件のように、公正証書遺言が無効とされることもあります。