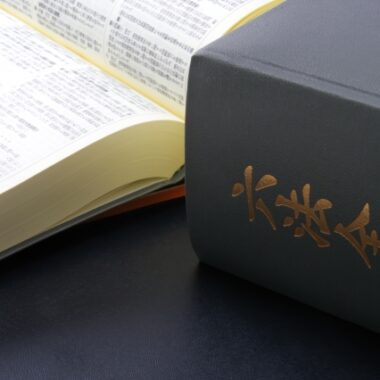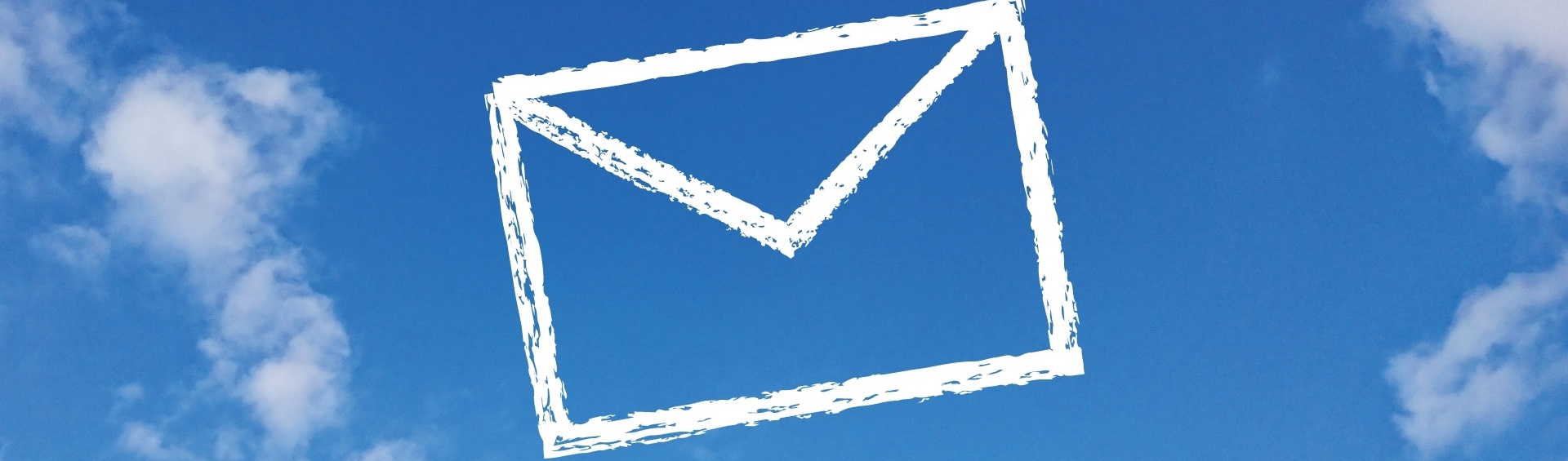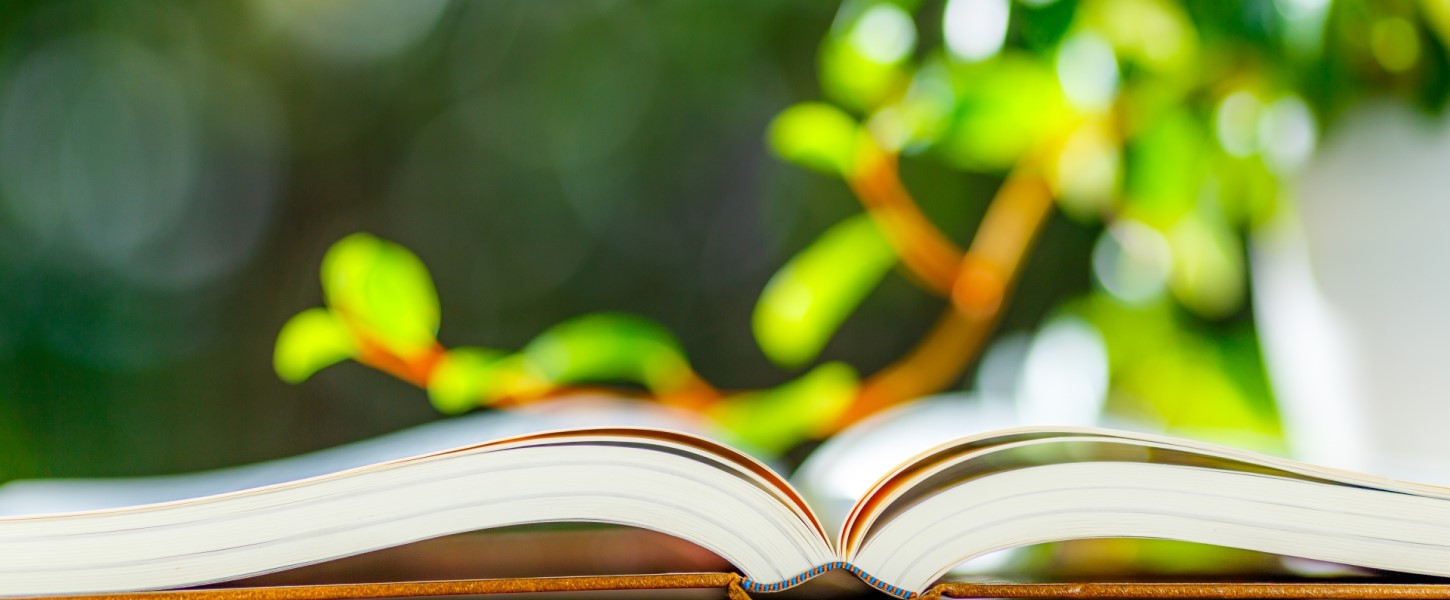ここでは、産業財産権、特に特許権を中心に各権利の制度内容を確認し、類似の権利ととらえられている特許権と実用新案権との相違を確認します。
目次
産業財産権の4つの権利について
産業財産権は知的財産権の一部、下記の4つの権利の総称となります。
①特許権
②実用新案権
③意匠権
④商標権
尚、産業財産権、知的財産権の概要につきましては、下記の記事で取り扱っています。
産業財産権4つの権利の概要
特許権とは
特許権は、主に特許法に規定されています。
業として特許発明を排他的独占的に実施することができる権利です(特許法68条等参照)。
下記引用の特許法2条1項に定義されているように、発明とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」であるとされています。
したがって、自然法則そのもの、あるいは先行する発明などから簡単に考え出すことが可能なもの等は特許法上の「発明」には該当せず、それらの創作では特許権を取得できません。
そして、特許は、
物の特許
方法の特許
物を生産する方法の特許
に分類され、下記引用の特許法2条3項に規定されているように、排他的独占的に実施可能な内容が異なっています。
(定義)
特許法第2条
第二条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
(2項省略)
3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
二 方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為
三 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
(4項省略)
そして、通常ルートとしては、特許出願、方式審査、出願人の審査請求によりおこなわれる実体審査を経て特許査定、特許料の納付、特許権の設定登録がなされると特許権が発生することとなります。
特許出願時の手続きの流れにつきましては、下記の記事でも扱っています。
実用新案権について
実用新案権は、主に実用新案法に規定されています。
業として登録実用新案の実施をする権利を専有できるものです。
そして、「産業上利用することができる考案であつて物品の形状、構造又は組合せに係るもの」が実用新案登録の対象となっています(実用新案法3条1項)。
ここで、実用新案法2条1項に定義されているように「考案」とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作」であり、下記に引用した実用新案法3条から分かるように当該技術分野の通常の知識がある者が容易に考案することができるようなものは要件を欠くこととなります。
実用新案権は、設定の登録により発生することとなり(同法14条1項)、原則、業として登録実用新案の実施をする権利を専有することとなります(同法16条)。
(実用新案登録の要件)
実用新案法第2条
第三条 産業上利用することができる考案であつて物品の形状、構造又は組合せに係るものをした者は、次に掲げる考案を除き、その考案について実用新案登録を受けることができる。
一 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた考案
二 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた考案
三 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された考案又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた考案
2 実用新案登録出願前にその考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる考案に基いてきわめて容易に考案をすることができたときは、その考案については、同項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。
そして、通常ルートとしては、出願、基礎的要件の審査、方式審査を経て設定登録がなされると実用新案権が発生することとなります(尚、登録料は出願時に出願料と同時に納付することとなっており、方式審査後に納付するものではありません。)。
尚、設定登録前に実体審査はおこなわれません。
このこともあり、無断で実用新案権を第三者が実施するような権利侵害がなされた場合、実用新案権者が特許庁の審査官が評価した「実用新案技術評価書」を提示して警告をおこなう必要がある等、紛争・疑義が発生した段階で実際に「進歩性」の有無等の実体的な判断がなされる構造となっています。
意匠権とは
意匠権は、主に意匠法に規定されています。
業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有できるものです。
そして、物品の形状、模様、色彩等、建築物の形状、画像等で視覚を通じて美感を起こさせるものが意匠権の対象となっています(意匠法2条1項参照)。
意匠を創作した者が、意匠登録出願、方式審査、実体審査を経て登録査定を受け登録料を納付、設定登録がなされると意匠権が発生します(意匠法20条1項等参照)。
商標権とは
商標権は、主に商標法に規定されています。
指定商品、指定役務について登録商標の使用をする権利を専有できるものです。
業として商品を生産、譲渡する者等が商品に使用、あるいは業として役務提供等をおこなう者が役務に使用する人の知覚により認識可能な文字、図形、記号、立体的形状、色彩、音などが商標権の対象となります(商標法2条1項参照)。
商標登録出願、方式審査、実体審査を経て登録査定を受け、登録料を納付、設定登録がなされると商標権が発生します(商標法18条1項等参照)。
特許権と実用新案権の主な相違点について
類似点について
特許権と実用新案権は、共に「自然法則を利用した技術的思想の創作」である点が類似し、登録に求められる要件もほぼ同じとなっています。
対象の相違
しかし、上記のように特許権の対象は「発明」であり「自然法則を利用した技術的思想の創作」のうち「高度」なものに限定されます。
一方、実用新案権の対象は「考案」であり、高度である必要はありません。高度とは言い難いものでも対象となり得ます。むろん高度のものも対象となりえます。
このように、特許権は、創作のうち高度のもののみを対象としているのに対し、実用新案権は高度のものではなくとも対象となり得るという点に違いがあります。
登録までの手続面およびそれからくる相違について
上記のとおり、特許は出願後、登録前に実体審査がなされますが、実用新案では出願後登録前に実体審査はおこなわれません。
このことから、手続面から、実用新案権が保護要件を充たしているか、たとえば「進歩性」を有するかは不透明であるということになります。保護要件を充たしていない、たとえば進歩性が認められない考案に関しても、考案者が出願してしまうと、出願後の実体審査がないことからチェックが働かず、要件を充たしていない考案でも実用新案権が発生しうることとなるからです。
そこで、特許権に関しては、特許権を侵害する行為があった場合、下記に引用した特許法103条により、その侵害行為には過失が推定されますが、実用新案法にはそのような推定規定は設けられていません。
(過失の推定)
特許法第103条
第百三条 他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。