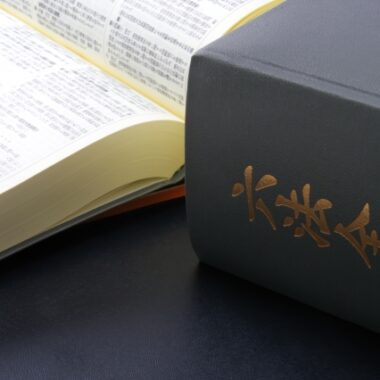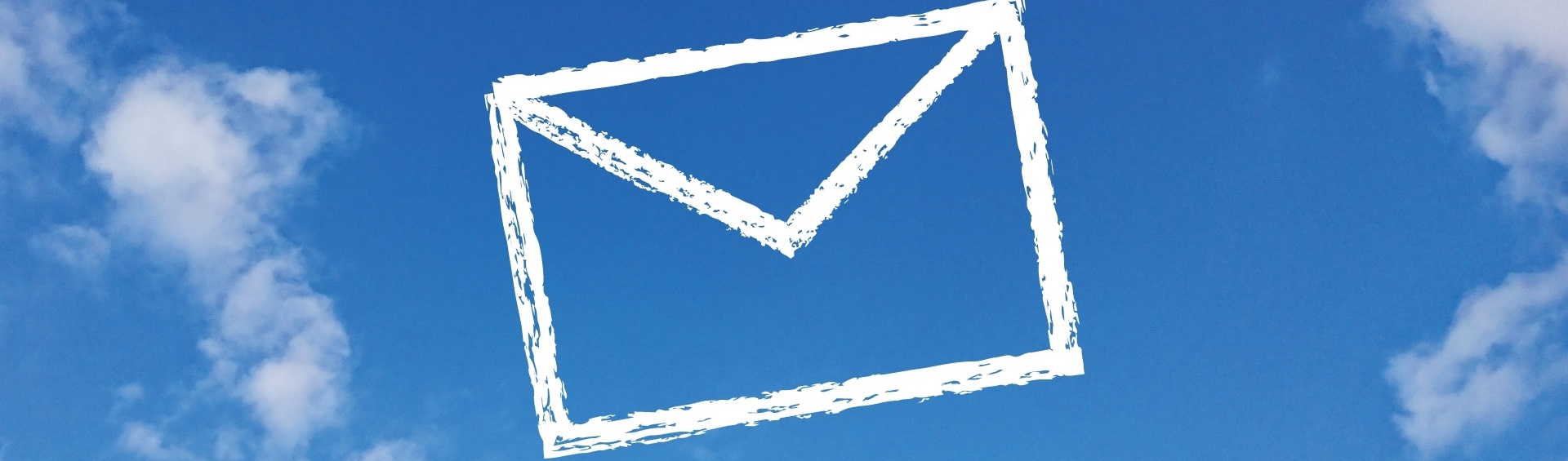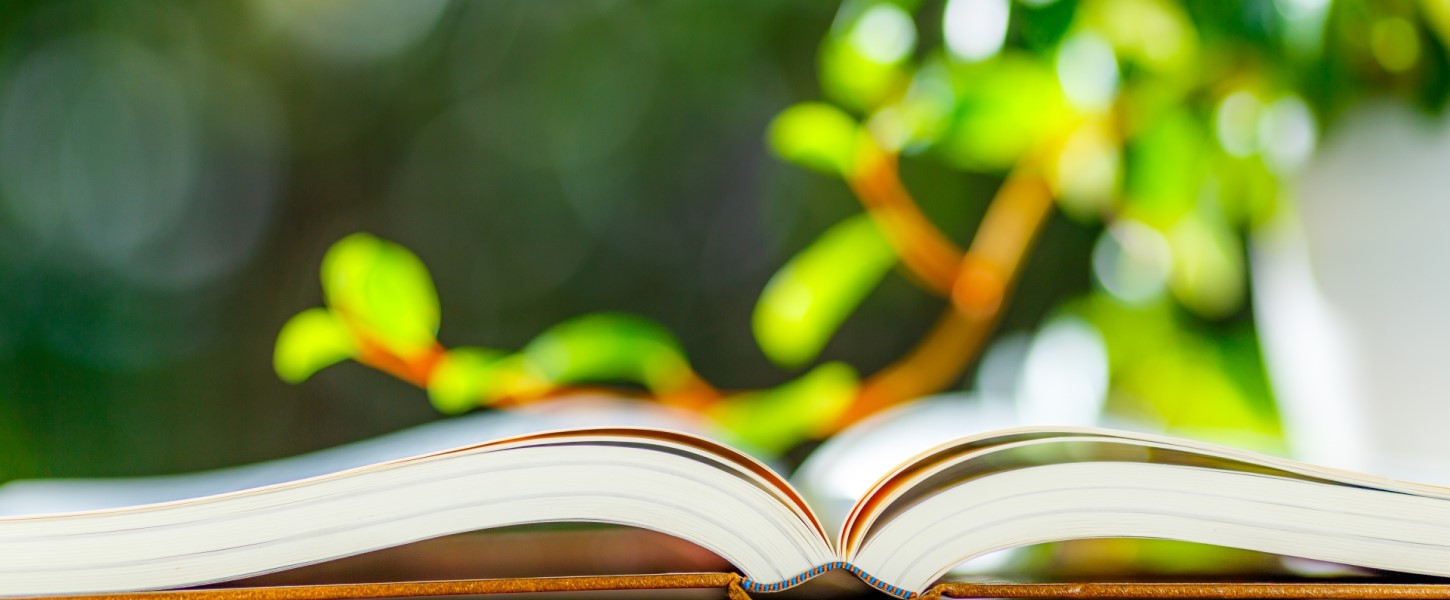発明者が特許出願をしますと、方式審査、実体審査を経て特許査定、特許料の納付、特許権の設定登録がなされると特許権が発生することとなります。
しかし、実体審査において拒絶理由があると判断されると拒絶査定がなされます。
ここでは、拒絶査定がどのような場合になされるか、拒絶査定に対する不服申立方法を確認した後に、知財高裁まで争われた事件を通じ手続きを確認してみます。
目次
特許出願後の主な手続の流れについて
審査について
通常問題がなければ、①特許出願、②方式審査、③審査請求によりおこなわれる④実体審査を経て⑤特許査定、⑥特許料の納付、⑦特許権の設定登録がなされ特許権が発生します。
しかし、期間内に③審査請求がなされないとみなし取下げとなります。
また、④実体審査において拒絶理由があると判断されると⑧拒絶査定がなされ特許権は取得できません。
拒絶査定不服審判について
この拒絶査定に不服がある場合、⑨拒絶査定不服審判を請求することができます。
この⑨拒絶査定不服審判において拒絶査定の理由が妥当と判断されると⑩拒絶審決が下されます。
審決取消訴訟について
更に⑩拒絶審決に不服がある場合、東京高等裁判所(知財高裁)へ⑪審決取消訴訟を提起することができます。
⑪審決取消訴訟の請求認容の判決が確定されると拒絶審決が取り消され、⑨拒絶査定不服審判へ差し戻されることとなります。
尚、高裁において請求棄却となった場合、上告も可能です。
出願したものの特許査定がなされないケース
方式審査で却下されるケース
方式審査とは、出願書類が形式的、手続的要件を充たしているかを確認するものです。
不備がある場合、補正が求められ、補正をおこなわないと出願を却下されることとなります。
実体審査で却下されるケース
特許出願後、3年以内に審査請求をおこなわないと出願を取り下げたものとみなされます。
その前に特許出願がなされると審査官による実体審査がおこなわれることとなります。
実体審査において拒絶理由が発見されないと特許査定がなされます。
一方、拒絶理由が発見されたとき、出願人へ拒絶理由通知がおこなわれ、出願人は拒絶理由を解消するため意見書、補正書を提出することができます。
補正書を提出しない場合、あるいは提出しても拒絶理由が解消されない場合、拒絶査定がなされます。
拒絶理由、特許要件について
下記引用の特許法51条の文言からも、「拒絶理由」の有無が、実体審査における審査官の特許を認める「特許査定」と認めない「拒絶査定」の判断を決定する要素であることがわかります。
(特許査定)
特許法第51条
第五十一条 審査官は、特許出願について拒絶の理由を発見しないときは、特許をすべき旨の査定をしなければならない。
「拒絶理由」とは、充足していない「特許要件」を意味することから、特許要件を充たしていない場合、拒絶理由が認められ、特許査定がなされないこととなります。
その特許要件としては下記のものを挙げることができます(カッコ内は当該要件が規定されている特許法の条文番号)。
・発明に該当すること(29条1項柱書)
・出願人が特許を受けることができる者であること(29条1項柱書、33条)
・産業上の利用可能性があること(29条1項柱書)
・新規性があること(29条1項1号~3号)
・進歩性があること(29条2項)
・先願であること(29条の2、39条)
・不特許事由(公序良俗違反)がないこと(32条)
拒絶査定への拒絶査定不服審判での拒絶審決に対する審決取消請求事件において認容判決が下された事案
ここでは、拒絶査定への拒絶査定不服審判での拒絶審決に対する審決取消請求事件において請求認容され審決が取り消された事件の判決を通じ、手続きの流れを確認するとともに審決取消訴訟において裁判所の審理がどのようにおこなわれるかをみてみます。
事案の概要
この事件(知財高裁判決令和4年5月31日)は、公開特許公報に記載された発明および公報に記載された周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたことから進歩性は認められないとして拒絶査定がなされた後、出願人が拒絶査定不服審判を請求したところ拒絶理由通知書の送付を受けたため、特許請求の範囲を補正したものの拒絶審決がなされたことから、これを不服として東京高等裁判所(知財高裁)へ審決取消訴訟を提起したものです。
尚、本件のような拒絶査定に関する拒絶審判の取消訴訟においては、原告は出願人、被告は特許庁長官となります。
裁判所の判断
裁判所は、この事案において、下記のとおり、審決において認定されている本願発明と引用発明の6つの相違点について検討を加え、うち3つの相違点に関しては、引用発明、周知技術に基づいて本願発明の構成を容易に想到し得たものとはいえないとし、進歩性を欠くとの審決の判断は誤りであるとし、審決を取り消しています。
主文
1 特許庁が不服・・・・号事件について令和・・・・日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は、被告の負担とする。事実及び理由
知財高裁判決令和4年5月31日
・・・・
3 本願発明と引用発明との一致点及び相違点の認定について
前記1及び2で検討したところによれば、本願発明と引用発明との一致点及び相違点は、本件審決が認定したとおり・・・であると認められる(この点については、原告も争っていない。)。
4 周知技術
・・・・・・・・・・・
(5) 認定される周知技術
上記(1)ないし(4)によれば、本件原出願日の時点における・・・の技術分野においては・・・・ことは周知技術であり、その結果として・・・・されることも周知技術であったと認められる。
5 容易想到性に関する判断
(1) 相違点1、2及び5について
ア 相違点1及び2に係る容易想到性
・・・・・以上によれば、甲1公報に接した本件原出願日当時の当業者が、相違点1及び2に係る本願発明の構成を想到することは容易であったというべきである。
イ 相違点5に係る容易想到性
・・・・以上によれば、甲1公報に接した本件原出願日時点の当業者が、相違点5に係る本願発明の構成を想到することは容易であったというべきである。
・・・・・
以上検討したところによれば、本件原出願日当時の当業者は、相違点1、2及び5に係る本願発明の構成を容易に想到し得たものと認められる。
(2) 相違点3、4及び6について
ア 相違点3に係る容易想到性
・・・・・・このように、引用発明においては、本願発明と共通する課題が本願発明とは異なる別の手段によって既に解決されているのであるから・・・引用発明に上記周知技術を適用することには阻害要因があるというべきであるから・・・・本件原出願日当時の当業者が、引用発明及び上記周知技術に基づいて、相違点3に係る本願発明の構成を容易に想到し得たものとはいえない。
イ 相違点4に係る容易想到性
相違点4に係る本願発明の構成は、相違点3に係る本願発明の構成である・・・を含むものであるところ、上記アで検討したところによれば・・・・本件原出願日当時の当業者が、引用発明及び上記周知技術に基づいて、相違点4に係る本願発明の構成を容易に想到し得たものとはいえない。
ウ 相違点6に係る容易想到性
相違点6に係る本願発明の構成は、相違点3に係る本願発明の構成である・・・・を含むものであるところ、上記アで検討したところによれば、本件原出願日当時の当業者が、引用発明及び上記周知技術に基づいて、相違点6に係る本願発明の構成を容易に想到し得たものとはいえない。
・・・・
オ 小括
以上検討したところによれば、本件原出願日当時の当業者は、相違点3、4及び6に係る本願発明の構成を容易に想到し得たものとは認められない。
(3) まとめ
以上によれば、本件原出願日当時の当業者は、相違点1、2及び5に係る本願発明の構成を容易に想到し得たものと認められるが、相違点3、4及び6に係る本願発明の構成を容易に想到し得たものとは認められない。
したがって、本願発明について、引用発明に対する進歩性を欠くとした本件審決の判断は誤りであるから、原告が主張する取消事由は、理由がある。
6 結論
よって、原告の請求は、理由があるからこれを認容することとして、主文のとおり判決する。