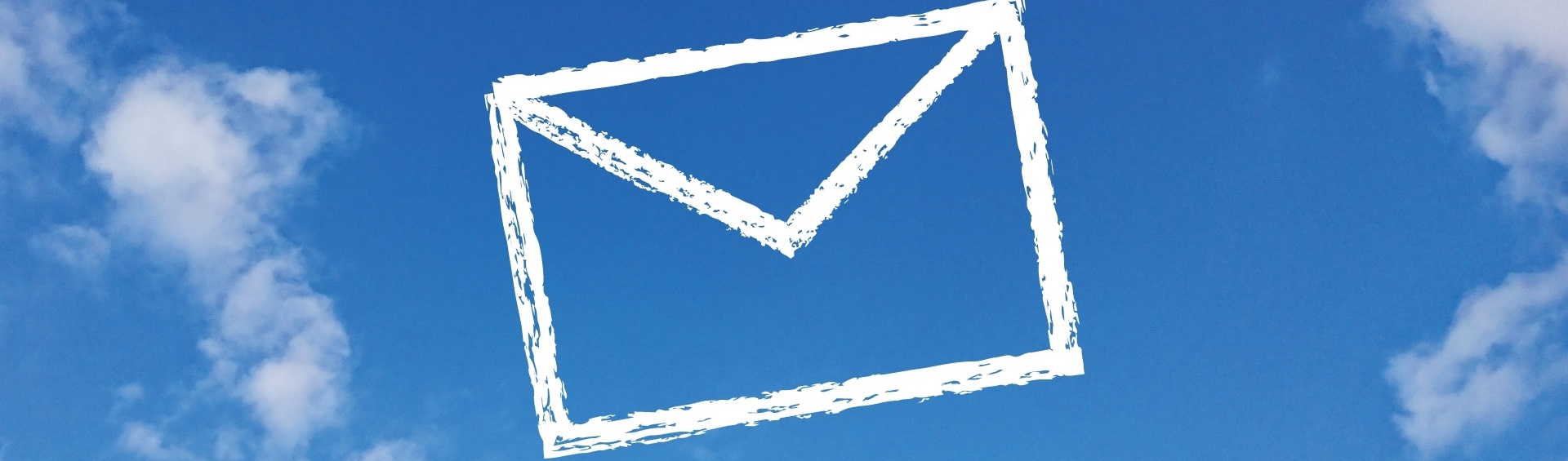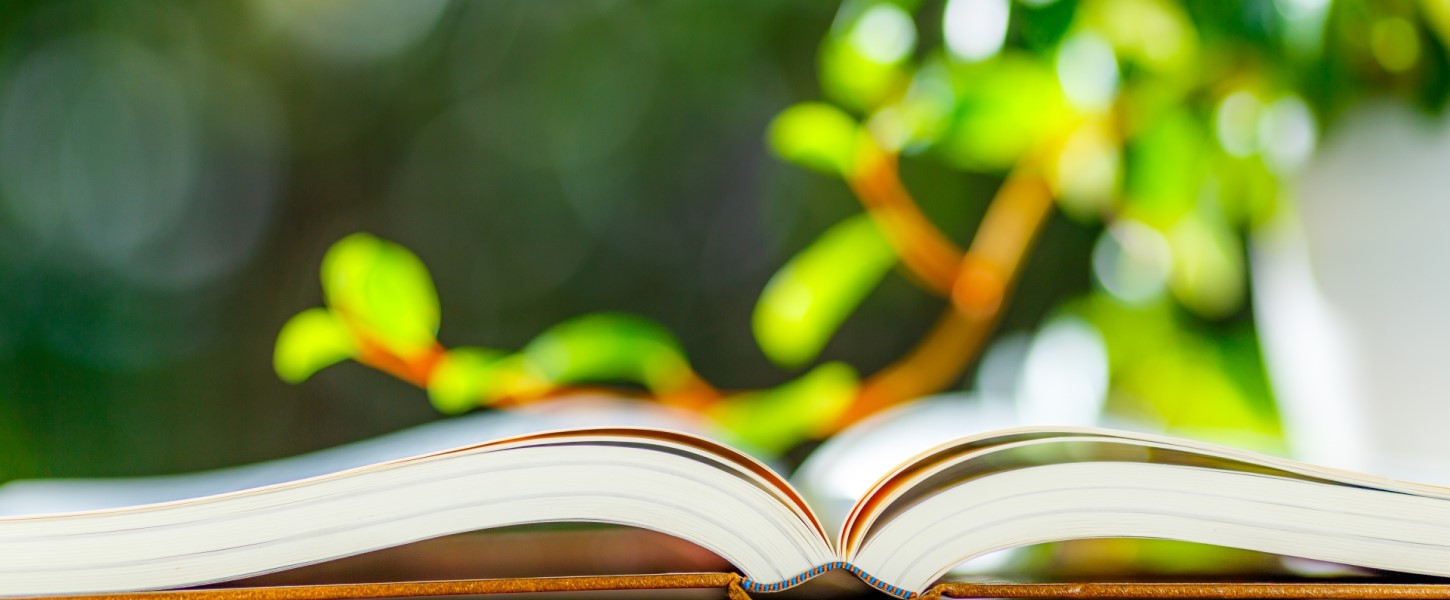ここでは、特許権の及ぶ範囲、どのような行為が特許権の侵害行為とされるのかを確認したうえで、特許権の保護として、侵害行為に対する救済手段としてどのような方法をとり得るのかを確認してみます。
目次
特許権の保護と特許権の侵害行為について
特許権の保護を考えるにあたっては、いかなる行為が特許権の侵害行為かを特定していく必要があります。その上で、当該侵害行為に対しどのような救済手段が用意されているかを確認していくこととなります。
特許権の侵害行為とは
そこで、どのような行為が侵害行為に該当するかを確認することとします。
ところで、下記に引用した特許法68条から、特許権者は「業として特許発明の実施をする権利を専有する」こととなります。
ここで、「実施」とは、生産、使用、譲渡など下記に引用した特許法2条3項に定義されたもののことです。
また、ここでの「業」としてとは、事業としてといった意味のことです。
そうしますと、この条文からは、正当な権限のない者(専用実施権者等は正当な権限があることが条文からも明らかです。)が「業として特許発明の実施」すれば特許権者の特許権が侵害されたといいうることになります。
尚、「専用実施権者」とは、特許権者から一定範囲の特許発明の実施を排他的独占的におこなうことができる権利である「専用実施権」の設定を受けた者のことです。
これらのことから分かるように、業としてではなく、個人的にあるいは研究のために第三者が特許発明の実施をしても特許権を侵害したことにはなりません。
(特許権の効力)
第六十八条 特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。(定義)
特許法
第二条
(1、2項省略)
3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
二 方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為
三 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
(省略)
特許権侵害については下記の記事でも扱っています。
特許権の及ぶ客観的範囲について
次に、特許権の及ぶ客観的範囲が問題となり得ますが、この特許権の及ぶ客観的範囲は、特許発明の「技術的範囲」といいます。
この技術的範囲は、下記に引用した特許法70条から分かりますように、願書に添付した明細書の記載、図面を考慮し、特許請求の範囲の記載に基づいて定められます。
そして、この範囲については「特許庁に対し、判定を求めることができ」(特許法71条)ます。
(特許発明の技術的範囲)
特許法第70条
第七十条 特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。
2 前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。
3 前二項の場合においては、願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。
どのような行為が特許権への侵害行為となるのでしょうか
3つの侵害行為
上記のように、正当な権限のない者が業として特許発明の実施をすることが特許権の侵害行為に該当することがわかります。
しかし、特許法の第4章第2節は標題が「権利侵害」とされており(尚、第4章の標題は「特許権」となっています。)、その第2節の101条では特許権の範囲である技術的範囲とは無関係な一定の行為についても特許権を侵害するものとみなすと規定しています。
このようなこともあり、侵害行為には間接的な行為も含まれ、侵害行為としては下記の3つに分類されます。
・文言侵害
・均等侵害
・間接侵害
文言侵害について
「文言侵害」とは、正当な権限のない者が、業として、願書に添付した特許請求の範囲の記載とおりの製品、方法等(このように特許権の侵害が問題となる製品、方法等を、以下「対象製品等」といいます。)を実施することによりおこなわれる特許権の侵害のことです。
均等侵害について
対象製品等が、願書に添付した特許請求の範囲の記載とおりの製品ないし方法ではなく「文言侵害」に該当しないものの、特許請求の範囲の記載の構成と均等なものである場合、「均等侵害」として特許権の侵害となります。
間接侵害について
上記で触れましたとおり、特許法101条は特許権の範囲である技術的範囲とは無関係な行為について特許権を侵害するものとみなしていますが、この101条に該当するものを「間接侵害」といいます。
特許権の侵害行為に対する救済方法について
3つの救済方法について
特許権は、業として特許発明を排他的独占的に実施することができる「権利」であることから、その侵害行為に対しては民法上の請求が可能となります。
また、特許権法は、第4章第2節「権利侵害」において、差止請求権を認めています。
したがって、特許権の侵害に対する救済方法としては次に3つの権利の行使が考えられます。
・差止請求権
・損害賠償請求権
・不当利得返還請求権
差止請求権について
下記引用の特許法100条のように、特許権への侵害者に対しては、侵害の停止を請求することができ、侵害するおそれのある者に対しては侵害の予防を請求することができます。また、侵害行為の組成物の廃棄、侵害行為に供した設備の除却、その他予防に必要な行為を同時に請求することもできます。
これらの請求は、特許権者のみならず特許権者から専用実施権者にも認められています。
(差止請求権)
特許法第100条
第百条 特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2 特許権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(物を生産する方法の特許発明にあつては、侵害の行為により生じた物を含む。第百二条第一項において同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
損害賠償請求について
特許権侵害により特許権者に損害が生じた場合、特許権者、専用実施権者等は、その損害を侵害者に対し不法行為責任に基づく損害賠償請求(民法709条)をすることが可能となります。
尚、特許法103条は「他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。」との過失の推定規定を設けています。
不当利得返還請求権について
上記の損害賠償請求に代え、不当利得返還請求権(民法703条等)を行使して損害額の返還を求めることも可能となります。
しかし、上記のとおり民法709条の不法行為責任に基づく請求をおこなう場合でも侵害者の過失が推定されることから、あえて不当利得返還責任により請求する実益あまり考えられません。
ただし、消滅時効が異なることから、不法行為責任の消滅時効が問題となる場合、不当利得返還請求権を行使する実益があり得ます。