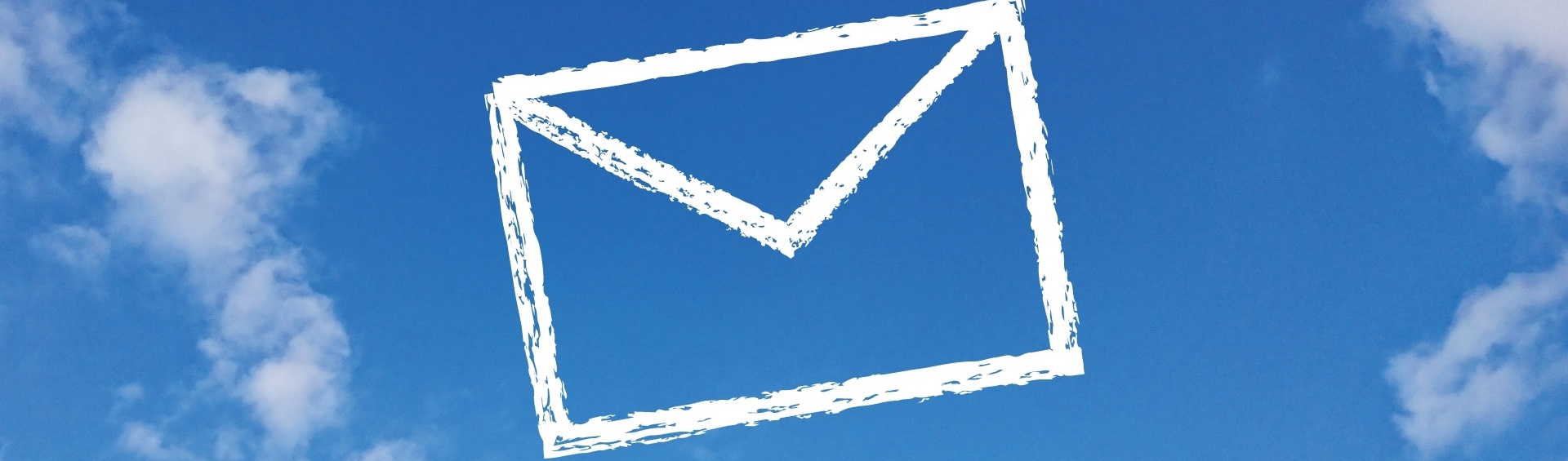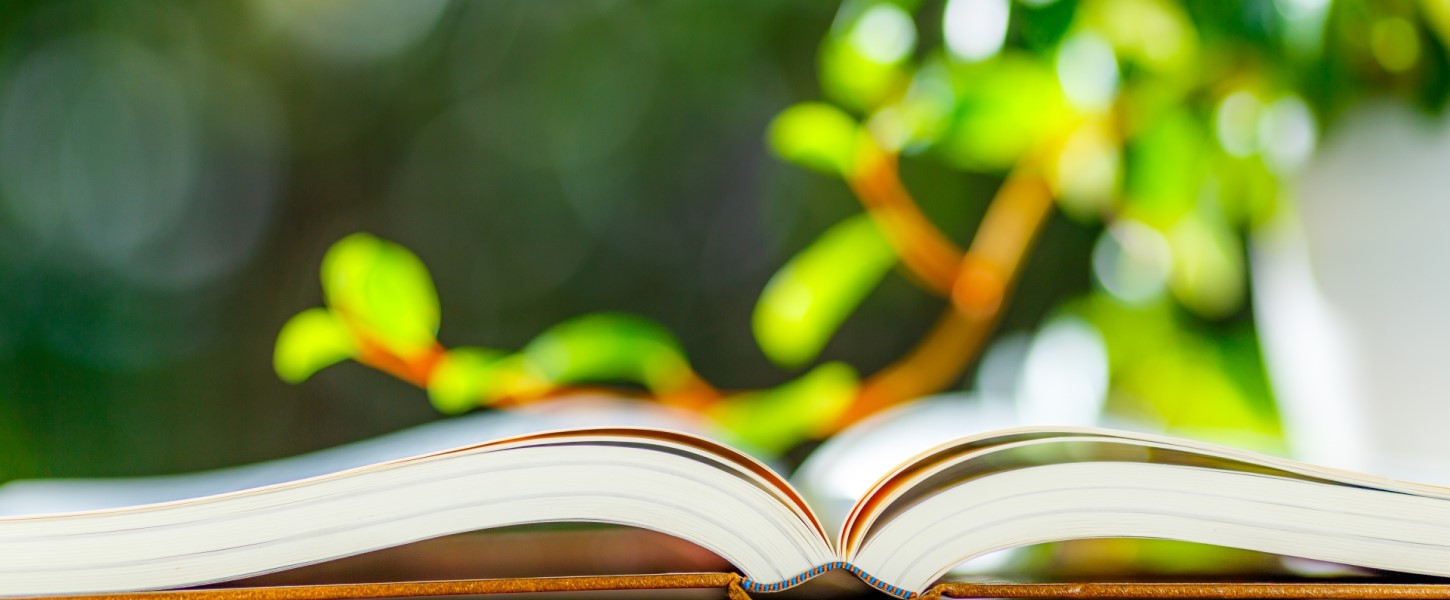特許権侵害には、文言侵害、均等侵害、間接侵害がありますが、これらはどのような場合、どのような行為について認められるのでしょうか。
各々の侵害行為の認定において問題となり得る点に触れた後、特許権侵害に関する裁判例をみながら、特許権侵害に関する訴訟において裁判所がどのような判断枠組みで結論を導いているのかを確認してみます。
目次
特許権侵害について
有効な特許権が成立している場合、Ⓐ正当な権限のない者の業としてのⓐ特許発明の実施、ⓑ特許請求の範囲の記載の構成と均等なものの実施、およびⒷ直接的に特許権を侵害する行為を誘発する恐れが高いとして特許法101条に規定された各行為は、特許権侵害に該当します。
これらの特許権侵害行為は下記の通り分類されます。
・文言侵害(Ⓐのⓐ)
・均等侵害(Ⓐのⓑ)
・間接侵害(Ⓑ)
特許権侵害に関しては下記の記事でも扱っています。
ところで、有効な特許権が成立するためには、まず特許出願が必要となりますが、特許出願には下記書類の提出が必要となります。
・願書
・明細書
・特許請求の範囲
・図面
・要約書
文言侵害とその判断について
文言侵害とは
文言侵害とは、正当な権限のない者が、業として、特許発明を実施することによりおこなわれる特許権の侵害行為です。
特許権の客観的範囲について
特許権の客観的範囲は技術的範囲とされ、その技術的範囲は特許出願時に提出する願書に添付した明細書の記載、図面を考慮し、特許請求の範囲の記載から決せられます。
尚、特許請求の範囲には、出願が複数に分けられる場合は複数の請求項に分けて請求ごとに構成(発明の課題を解決するために講じられた手段)を説明します。
この技術的範囲を確定する際には、明細書の記載、図面が考慮されることとなります。
明細書には、技術分野、背景技術、先行技術文献の記述に続き、「発明の概要」として、発明が解決しようとする課題である従来技術の問題点、課題を解決するための手段として特許請求の範囲に記述した構成の説明、更に発明の効果として従来技術に対して有利な効果を記述します。
文言侵害の判断について
上記のとおり、正当な権限のない者が、業として、特許発明を実施することが文言侵害となります(特許権の侵害が問題となる製品、方法等をここでは「対象製品等」といいます。)。
そこで、文言侵害に該当するか否かの判断では、対象製品等の実施がなされた場合、
・実施した者が正当な権限を有しているのか
・業として実施したのか
・特許発明を実施したのか
等が問題となります。
ここで、「特許発明を実施したのか」という点は、対象製品等が「特許発明の技術的範囲に属する」のか否かで判断されることとなります。
上記で述べたことなどから、対象製品等の構成と特許請求の範囲に記載された構成とを対比するなどし、特許発明の技術的範囲に対象製品等が属するかは判断されることとなります。
均等侵害とその判断について
均等論と均等侵害について
特許請求の範囲の記述(クレーム)は、上記のように技術的範囲を画するものであり、特許公報などで公開されるものでもありますから、技術的範囲を公示する機能も有しているといえます。
そこで、特許請求の範囲の記述を超えた範囲にまで特許権侵害を認めると、第三者の予測可能性を奪うこととなりかねません。
しかし、対象製品等の構成が特許請求の範囲の記載と一部異なっているとしても、実質的に同一であると評価される場合、技術的範囲に含まれると考える「均等論」という理論があります。
この均等論に基づき、対象製品等は文言侵害に該当しないが、特許請求の範囲の記載の構成と均等なものと評価される場合、特許権の侵害と考えることとなり、この侵害が「均等侵害」です。
均等侵害の判断について
均等侵害は、最判平成10年2月24日から、次の5つの要件すべてを充たすときに認められるとされています。
・異なった部分が特許発明の本質部分でないこと
・異なった部分を対象製品等の構成と置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の効果作用を奏すること
・異なった部分を対象製品等に置き換えることを、当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が、対象製品等の製造時において容易に想到することができたものであること
・対象製品等に使用されている技術が、特許発明の出願時における公知技術と同一または当業者が容易に推考できたものではないこと
・対象製品等に使用されている技術が、特許発明の出願手続きにおいて特許請求の範囲から意識的に除外されたものにあたるなどの特段の事情もないこと
間接侵害とその判断について
上記の文言侵害、均等侵害に該当しない場合において、特許権侵害を誘発する可能性が高い態様の行為類型を特許法は101条の1号~6号として6つ列挙し、これらを特許権侵害行為とみなしています。
この101条に該当するものを「間接侵害」といいます。
そこで、下記に引用した特許法101条の1号~6号への該当性により間接侵害の判断がなされることとなります。
(侵害とみなす行為)
特許法第101条
第百一条 次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
一 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
二 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
三 特許が物の発明についてされている場合において、その物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為
四 特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
五 特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
六 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為
特許権侵害行為が問題となった事件について
特許権侵害の救済方法としては、侵害差止請求、損害賠償請求、不当利得返還請求があります。
ここでは、特許権等侵害差止および損害賠償を求め提訴され、文言侵害と均等侵害が争点となった事件(大阪地判令和6年11月14日)判決を判断枠組みを中心にみてみます。
事案の概要
特許権を有する原告が、被告製品が特許権侵害であるとして、特許法100条1項に基づき、被告製品の製造等の差止めおよび同条2項に基づき被告製品等の廃棄、並びに損害賠償請求を求めたものです。
裁判所の判断
第4 当裁判所の判断
大阪地判令和6年11月14日
1 被告製品の構成(争点1)について
証拠(甲3、乙1ないし5)によれば、被告製品の構成は次のaないしi記載のとおりであると認められる。
a竿体(11)の先端部に取付け取り外し可能で先端先鋭状の・・・(12)を突設したキャップ部と、約1メートルの長さの1本の塩化ビニル製パイプ(KCビニルパイプ)からなる所定長さの竿体(11)と・・・・・・・・・場合には、作業者(A)は・・・一方の手で竿体(11)の基端側部を把持し・・・するように構成した
2 文言侵害の成否(争点2)について
(1)本件明細書の記載
本件明細書には、以下の記載がある。・・・・
(2)構成要件A(・・・)の充足性
ア 特許請求の範囲請求項1には「伸縮自在の所定長さの竿体」との記載があるところ(構成要件A)、その文言から、「竿体」が「伸縮自在」である構成が示されているものと当業者は理解できる。
また、本件明細書をみると、本件発明が解決しようとする課題は、要するに、非力な者であっても・・・簡単かつ確実に・・・できるようにすることである・・・。このような課題を解決するため、竿体を伸縮自在に構成することで・・・調整できるようにし・・・という効果が得られる・・・。
これらによれば、当業者にとって、「伸縮自在の所定長さの竿体」とは、竿体部分の長さそれ自体を変更できる構造の竿体を意味するものと理解されるのであり、固定長の竿体は、含まれないものというべきである。
イ この点、原告は・・・と主張する。しかし・・・同様の効果を実現することは極めて困難であると考えられる。
よって、原告の主張は採用できない。
ウ 以上のとおり、被告製品は構成要件Aを充足しないものと認められる。
(3)構成要件Fの充足性
・・・・被告製品は、構成要件Fを充足しないものと認められる。・・・
(4)構成要件Gの充足性
・・・・そうすると、被告製品は、構成要件Gを充足しないものと認められる。
(5)構成要件Hの充足性
・・・・よって、被告製品は、構成要件Hを充足しない。
(6)小括
以上の次第であり、被告製品は、少なくとも、構成要件A及び構成要件FないしHを充足しない。
3 均等侵害の成否(争点3)について
特許請求の範囲に記載された構成中に相手方が製造等をする製品又は用いる方法(以下「対象製品等」という。)と異なる部分が存する場合であっても、①同部分が特許発明の本質的部分ではなく(第1要件)・・・・かつ、⑤対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないとき(第5要件)は、同対象製品等は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である(最高裁平成6年(オ)第1083号同10年2月24日第三小法廷判決・民集52巻1号113頁参照)。
(1) 第1要件について
ア特許発明における本質的部分とは、特許請求の範囲及び明細書の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であると解すべきであり、特許請求の範囲及び明細書の記載に基づいて、特許発明の課題及び解決手段とその効果を把握した上で、特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が何であるかを確定することによって認定されるべきものである。
前記2(2)ア認定のとおり、本件発明は、非力な者であっても・・・できるようにすることを解決すべき課題とし・・・、このような課題を解決するため、竿体を伸縮自在に構成することで・・・距離を調整できるようにし・・・することができるという効果が得られるというものである。
一方、証拠・・・によれば、本件特許の出願時点で・・・する手段として・・・を用いることなどが知られていたことが認められる。これらの手段は・・・することはできるが、即効性に欠けたり、即効性があっても・・・近づく必要があることから危険を伴ったりするものであった。
そうすると、本件発明は、従来技術である電流を用いた・・・手段を踏まえ、簡単かつ安全確実な・・・手段を提供するものであり、本件発明の構成中の本質的部分は、このような・・・手段を提供する竿体の伸縮構造(構成要件Aの「伸縮自在の所定長さの竿体」)、・・・構造(構成要件F)、・・・の並列構造(構成要件G)・・・に認められるものというべきである。
イ前記2で検討したとおり、被告製品は、少なくとも、構成要件Aの「伸縮自在の所定長さの竿体」の部分、構成要件F及びGを充足しないのであるから、本件発明の構成中、被告製品と異なる部分が本件発明の本質的部分ではないとの均等侵害の第1要件は認められない。
(2)第5要件について
ア証拠・・・によれば、本件特許の出願経緯について、以下の事実が認められる。
(ア)原告は・・・・日、以下の特許請求の範囲で、本件発明について、特許出願をした。
【請求項1】・・・・
(イ)特許庁審査官は・・・日・・・原告に対し、要旨、以下の理由により、原告の出願は拒絶すべきものであると通知した。
a請求項1の・・・が何を指すのかが不明である(明確性要件違反)。
b請求項4の「電源昇圧部・・・等」とあるのは、「各操作部分」を有するものの例示に過ぎず、何の「各操作部分」であるかが実質的に特定されていない(明確性要件違反)。
c進歩性欠如
(ウ)上記拒絶理由通知に対し、原告は、特許請求の範囲を次のとおり補正し、進歩性に関する意見書を提出した。
【請求項1】
先端先鋭状の正電極部となる金属針部を先端に有した所定長さの竿体と、・・・と、・・・と、・・・と、・・・と、・・・とよりなり、・・・するように構成したことを特徴とする・・・用具。
・・・・
【請求項3】
所定長さの竿体は伸縮自在に構成し、基端にグリップ部を形成したことを特徴とする請求項1または2に記載の携行自在な・・・用具。
・・・・
(エ)特許庁審査官は、・・・日・・・、上記補正を検討してもなお、原告の出願は、進歩性欠如を理由に拒絶すべきであるとの査定をした。
(オ)原告は・・・日、上記拒絶査定に対する不服審判を申し立てるとともに、特許請求の範囲を次のとおり補正した。
【請求項1】
先端先鋭状の正電極部となる金属針部を先端に有した所定長さの竿体と、竿体は伸縮自在に構成し、基端にグリップ部を形成し、・・・とよりなり・・・する場合には、作業者は一方の手で竿体のグリップ部を把持し・・・し、・・・作業者は一方の手で・・・竿体の金属針部を突き・・・を形成することにより・・・するように構成したことを特徴とする・・・用具。
【請求項2】ないし【請求項4】
削除
(カ)特許庁審査官は、・・・日・・・、原告の上記補正後の出願に対し、要旨、・・・「竿体は伸縮自在に構成し、基端にグリップ部を形成し」という記載が前後の文章と整合性が取れておらず不明瞭であるとして拒絶すべきものと通知した。そのうえで、請求項を次のとおりにすることでこれらの拒絶理由は解消できるとの補正の示唆を行った。
【請求項1】
先端先鋭状の正電極部となる金属針部を先端に有し、基端にグリップ部を形成した、伸縮自在の所定長さの竿体と、・・・とよりなり、・・・する場合には、作業者は一方の手で竿体のグリップ部を把持し、他方の手で・・・し、・・・することにより・・・するように構成したことを特徴とする・・・用具。
(キ)原告は、・・・日、上記の補正の示唆のとおり、請求の範囲を補正し、平成27年1月5日・・・、特許査定を受けた。
イ 以上の審査経緯に鑑みれば、原告は、当初、竿体の伸縮構造については固定長の竿体も含むものとし・・・状態の構成については・・・のみで・・・に限られないものとし・・・も含むものとして、特許請求の範囲を記載していたが、進歩性欠如及び明確性要件違反を指摘されたことから、拒絶査定を回避するため、現在の特許請求の範囲の請求項1の記載のとおりに限定したのであり、限定により除外された部分は、いずれも本件特許の特許請求の範囲から意識的に除外したものであることが認められる。
そうすると、被告製品と本件特許の特許請求の範囲の請求項1の記載との相違点は、いずれも原告が意識的に除外した部分に該当するから、均等侵害に関するその余の原告の主張を前提としても、対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないときとの第5要件を満たさないというべきである。
(3)したがって、被告製品は、本件発明と均等なものとはいえない。
4以上のとおり、被告製品は、本件発明の技術的範囲に属さないものと認められるから、その余の争点について検討するまでもなく、原告の請求は、いずれも理由がない。
5結論
よって、原告の請求は理由がないからいずれも棄却することとし、訴訟費用の負担について民訴法61条を適用して、主文のとおり判決する。