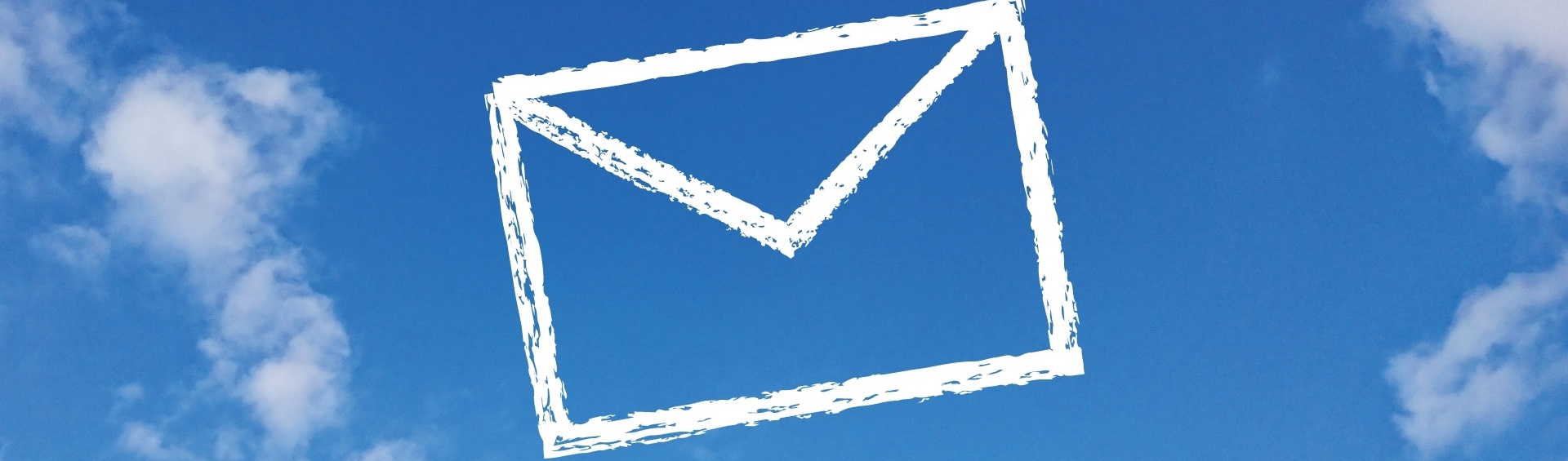目次
事故の概要
ここでは、商業ツアー登山であるⅰ)2006年白馬岳遭難死事件の裁判を見てみます。
尚、この事件は、2012年のゴールデンウイークに、小蓮華山~三国境の稜線界隈で発生した遭難事故とは別の事故によるものです。
ⅰ)の事件は、プロの登山ガイドが個人で主催・ツアーリーダーを務め、5名が参加(他1名ガイド見習いとして同行)した、平成18年10月初旬に祖母谷温泉から白馬岳~朝日岳~栂海新道を経て日本海の親不知へ抜ける、山中3泊4日の北アルプス北部縦走ツアーにおいて、実質的な登山初日である10月7日に、清水岳から前記白馬山荘に至る登山道において、強風、みぞれ、吹雪等にさらされたことにより、白馬岳山荘手前登山道においてツアー参加者3名、白馬岳の山小屋内で1名が低体温症で死亡したものです。
このツアーの参加者は50歳代1名、60歳代4名、計5名の女性で、うち生存者は1名のみでした。
上記のツアーの日程を見れば、下記の記事で扱っていますⅱ)残雪の八ヶ岳縦走遭難事件のツアー日程と比べるまでもなく、相当な体力を必要とするコースであることがわかります。
初日の祖母谷温泉から清水尾根を経て白馬岳山頂下の小屋へ至るコースは、標高差が約2000m、水平距離約14kmとなっています。
しかし、ツアーのチラシでは、対象者は中級者とされています。
尚、被告のツアーにおいては、中級ツアーは「歩行時間五~七時間。岩場がある場合あり。初級の方で元気な方は参加できます」という位置づけとなっていました。
裁判について
このⅰ)の事件は、平成22年に損害賠償請求の民事裁判が提起され、1審判決後、控訴審で和解が成立しています。
また、刑事事件としては、平成26年に業務上過失致死事件として起訴され、1審で業務上過失致死罪の成立が認定され有罪判決が下されました。その後、控訴されたものの、控訴棄却されています。
ここでは、民事事件の1審の判決(以下「民事事件」といいます。)を、刑事事件の判決(以下、刑事事件の1審を「刑事事件1審」、刑事事件の控訴審を「刑事事件控訴審」、刑事事件の1審と控訴審をあわせ「刑事事件」といいます。)を参考にし、あるいは比較しながらみていきます。
本件では、民事事件においても、刑事事件においても、ツアーの主催者でツアーリーダーでもあった者(以下「甲」といいます。)の過失が認定されています。
民事裁判上の請求の法律構成
はじめに民事事件において、どのように損害賠償請求権の存在を認定しているのかを俯瞰してみます。
まず、損害賠償請求の法的構成をみますと、
ⅱ)事件において請求は不法行為に基づく損害賠償請求のみでしたが、
ⅰ)事件の請求は、安全配慮義務違反による債務不履行に基づく損害賠償請求と、不法行為に基づく損害賠償請求を選択的併合しています。
尚、選択的併合とは、本件のように(損害賠償)請求権の成立理由として複数の法律構成が考えられる場合に、裁判所に対し複数の法律構成による請求権の存否の判断を求めるものです。
しかし、仮に請求が認められても(損害賠償)請求権は1つしか認められません。
100万円の損害賠償請求を、安全配慮義務違反による債務不履行と不法行為の2つの法的構成を選択的併合して請求し、この請求が裁判所に認められた場合でも、被告に対する200万円の請求が認められるのではなく、あくまで100万円の請求が認められるにすぎません。
この選択的併合の場合、裁判所はいずれかの法的構成による請求を認容した場合には、残りの法律構成の判断を示す必要はありません。
しかし、請求を棄却する場合には、原告が主張するすべての法的構成について判断を下す必要があります。
尚、ツアー登山事故では、安全配慮義務違反における安全配慮義務の内容と、不法行為責任における過失の前提となる注意義務の内容が実質的には重なることから、いずれの法的構成を採用しても主張・立証はあまり変わりません。
しかし、民法改正前は不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効が3年とされていたのに対し、安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求権の消滅時効は10年でした。
このように、安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求権の方が消滅時効が長かったことから、事件から訴訟提起までの時間的経過によって、不法行為に基づく損害賠償請求権が時効消滅していたような場合、安全配慮義務違反を主張することがありました。
ところが、民法の改正により、生命・身体への侵害に対する損害賠償請求権については、安全配慮義務違反に基づくものも、不法行為責任に基づくものでも、主観的起算点から5年、客観的起算点から20年と同じになりました。
このことから、今後は、安全配慮義務違反の主張が必要となるケースは減少するのではないかと考えられています(ただし、法改正の経過規定に関しては留意が必要です。)。
本件民事事件では、裁判所は不法行為責任について審理をおこない、不法行為に基づく損害賠償請求を認め、安全配慮義務違反についての判断はおこなっていません。
民事事件と刑事事件の注意義務違反の相違
民事事件における過失認定について
次に本件事件の民事事件と刑事事件において認定された過失の内容についてみてみます。
まず、民事事件からみてみます。
本件民事訴訟の判決では、過失の認定について、抽象的義務と具体的義務に関し、項目をわけて判示しています。
まず、
・・・登山は、遭難、事故等により生命の危険を伴うものであるから、登山ツアーを企画実施する者は、参加者の生命身体に危険が生じないような適切な準備や指示、処置をする注意義務を負っているというべきである
熊本地判平成24年7月20日
とした上で、
参加者としては、登山を引率するにふさわしい技術・能力を持ったプロの登山ガイドである被告がガイドすることを前提にし、その技術・能力等を信頼して本件ツアーに参加したといえる
熊本地判平成24年7月20日
と参加者のツアーへの期待についても触れた上で、
したがって、被告は、プロの登山ガイドとして高度の注意義務を負っていたというべきである
熊本地判平成24年7月20日
とツアーリーダーである登山ガイドに高度の注意義務の存在を認定しています。
そして、その注意義務の内容に関し、抽象的ながらやや具体的に、
登山が天候の変化による遭難等の危険を伴うものであること、前記認定のとおり、日本旅行業協会が作成した「ツアー登山運行ガイドライン」に、出発前からの気象変化の予測が重要であると指摘すると共に、引率者として要求されると考えられる能力として、気象に関する知識を挙げていること及び被告が・・・高度の注意義務を負っていることからすると、被告は、プロの登山ガイドとして、出発前から天候に関する情報を収集すべき義務、登山中の天候を予測した上で、登山中の天候が悪天候であると予測される場合には、登山を中止するなど適切な処置をとるべき義務などを負っていたといえる
熊本地判平成24年7月20日
と出発前から天候に関する情報を収集する義務があったことを述べています。
また、登山中の天候を予測した上で、登山中の天候が悪天候であると予測される場合、登山を中止するなど適切な処置をとる義務もあるとしています。
これらの注意義務を導くに際し、「ツアー登山運行ガイドライン」の内容を引用していることに留意が必要です。
ツアー登山事故の過失認定に限らず、過失の認定に際しては、一定の規範性を有するガイドラインから過失認定の前提となる注意義務の内容を認定することがあります。
続いて本件では、事件当時の気象状況とツアーの概要に触れた上で、
被告は、・・・台風又は台風から変わった低気圧が三陸沖を本州沿岸に沿って北上し、冬型の気圧配置となる可能性があるかどうかなどに関し、事前に収集可能な情報を収集すべき義務(以下「事前情報収集義務」という。)を負っていたというべきである。
また、この事前情報収集義務を前提にして、・・・収集した情報を事前に検討し、天候が悪化し、生命や身体に危険が及ぶと予見される場合には、登山を中止するなどの適切な処置等をすべき義務(以下「催行検討義務」という。)を負っていたというべきである
熊本地判平成24年7月20日
として、具体的注意義務として、
- 事前情報収集義務
- (事前情報収集義務を前提とする)催行検討義務
が存在したとしています。
ところで、一般的には、民事訴訟における過失を、損害発生の「予見可能性」があるにもかかわらず、これを回避する行為義務(注意義務)を怠ったこと(違反)であると考える、客観的過失概念を採用しているとされます。
このことから裁判所は、
富山地方気象台及び日本気象協会が・・・(天気)情報を発表して以降に、被告が、同情報を入手していれば、七日の気圧配置が冬型のうちの山雪型の気圧配置になることを予見でき、その結果、本件ツアー中に急な天候の変化による強風や吹雪等の発生を予見することができたということができる(注:カッコ内は筆者加筆)
熊本地判平成24年7月20日
と事前情報収集をおこなっていれば天候の悪化を予見できたとして、予見可能性を認定しています。
そして、
事前情報収集義務を怠った結果、催行検討義務を履行することができなかったということができる。よって、被告には、同義務違反がある
熊本地判平成24年7月20日
として事前情報収集義務違反を認定しています。
その上で、更に、事前情報収集義務違反により催行検討義務を履行できなかったとしています。
しかし、催行検討義務については、上記で引用したように「登山を中止するなどの適切な処置」とされてはいますが、ここでも具体的な内容については触れておらず、その内容は明確ではありません。
刑事事件における過失認定について
次に刑事事件1審判決の過失認定についてみてみます。
この判決では、
本件の争点は,過失の有無,すなわち,被告人に,遅くとも清水尾根の途中において,その後の本件登山を中止して不帰岳の避難小屋に引き返すなどして被害者ら登山客の生命及び身体の安全を確保し,遭難事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務及びこの義務違反が認められるか否かであり,更にはその前提として,本件登山を続行すれば,被害者ら登山客が強風,みぞれ,吹雪,低気温等にさらされるなどして追従,歩行が困難となり,凍死するに至る危険を予見することができたか否かである
長野地裁松本支部判決平成27年4月20日
と引用前半部分において、問題となる注意義務の内容がかなり具体的に示され、後半部分で予見可能性についても民事事件に比べ、かなり具体的に示されています。
その上で、事実経過、参加者の属性等の事情を相当程度詳細に認定した上で、予見可能性について、
結果予見可能性が認められるためには,特定の構成要件的結果及びその結果の発生に至る因果的経過を予見する必要があるものの,現実の因果的経過を逐一予見することまでの必要はなく,ある程度抽象化された因果的経過を予見することが可能であれば十分といえる。そして,具体的にみると,結果の発生に至る因果的経過については,温帯低気圧が発達しながら本州(関東)南岸の海上から東北地方の海岸沿いに北上し,冬型の気圧配置になること,その気圧配置になれば,清水尾根の途中以降,天気が悪化し,被害者らが強風,みぞれ,吹雪等にさらされるおそれがあること,そのおそれが現実化すると,被害者らは体温を奪われて凍死(低体温症による死亡)する可能性があること,という程度のもので足りる
長野地裁松本支部判決平成27年4月20日
とし、続いて、
そこで,被告人の立場に相当する通常人を本件登山当時の状況に置いた上,結果(被害者らの凍死)の発生を予見することが可能であったか否かを,通常人の認識し得た事情(認定済み)を前提に判断すると,本件登山前のテレビ解説による気象情報などを踏まえれば,冬型の気圧配置になることを予見することができ,また,本件登山開始時から降雨の状態が続いていること(本件登山中の天気)に加え,この時期の気象状態(北アルプスの天候)やコースの地形的特徴(本件登山行程等の概略)などに照らせば,清水尾根の途中以降,天気が悪化し,被害者らが強風,みぞれ,吹雪等にさらされるおそれがあることの予見が可能であり,さらに,そのおそれが現実化すれば,被害者らが本件登山中に身に付けていた装備の不十分さなどに鑑み,被害者らは体温を奪われて凍死(低体温症による死亡)するおそれがあることもまた予見可能といえるので,結局,通常人は,前記因果的経過を予見することが可能であったと認められる・・・そして,以上の認定及び判断については,通常人ではなく,被告人を判断基準の主体と位置付けてみても,何ら異ならない
長野地裁松本支部判決平成27年4月20日
と具体的な予見可能性を認定しています。
その上で、「4 結果回避義務及び同義務違反の有無」として、
一般に,決行された登山を気象状態の悪化などから途中で中止することもまれではない・・・ところ,清水岳山頂直下までの時点であれば,登山客らにおいて不帰岳の避難小屋まで引き返すだけの気力及び体力が残っていたこと・・・,清水尾根の途中から不帰岳の避難小屋までは下りで所要時間も短く,樹林帯で風雨を遮ってくれること・・・に照らすと,本件登山を中止して清水尾根の途中から不帰岳の避難小屋に引き返すなどの対応をとっていれば,被害者らが強風,みぞれ,吹雪等にさらされ,体温を奪われて低体温症で死亡することはなかったということができる。このように,被告人には,降雨の状態が続く中,結果(被害者らの凍死)の発生を予見することができた上,結果回避の可能性もあったことから,遅くとも清水尾根の途中において,その後の本件登山を中止し不帰岳の避難小屋に引き返すなどして被害者らの生命及び身体の安全を確保し,遭難事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務があるとともに,この義務を怠って漫然登山客らを不十分な装備のまま引率して本件登山を続行したという同注意義務違反すなわち過失が認められる
長野地裁松本支部判決平成27年4月20日
と過失を認定しています。
このように刑事事件1審では、民事事件より具体的に注意義務の内容を判決で明示していますが、これは、民事訴訟に比べ刑事訴訟の方がより厳格な証明を要することからくるためだと考えられます。
刑事事件控訴審では、予見可能性に関して弁護人側から
原判決の認定のように気象状態の悪化の可能性とそれが現実化した場合に遭難事故となる危険を予見し得たとしても,現に生じたような著しい天候の悪化により移動を困難とするような激しい暴風雪となることまで予見することができない限り,被告人に過失は認められない
東京高判平成27年10月30日
旨の主張がなされたのに対し、控訴審裁判所は、
遭難事故となる危険性のあるような天候の悪化が予見できれば,遭難事故を避けるために登山を中止することが期待できるのであるから,過失判断の前提としての予見の内容としては,「遭難事故となる危険性のあるような天候の悪化の可能性」で足り,それ以上に「現に生じたような著しい天候の悪化の可能性」は予見の対象とならないというべきである
東京高判平成27年10月30日
として、弁護人の主張を退け、
原判決が判示するとおり,被告人には,遅くとも,被害者らの生命,身体に対する危険を生ずる結果を回避することが可能であったと認められる清水尾根の途中において,本件登山を中止して不帰岳山頂直下の避難小屋に引き返すなどの対応をとる義務があったものというべきである
東京高判平成27年10月30日
と注意義務違反を認定するには、被告が当該事件の具体的な事実経過を認識していたことまでは必要とされないということを明らかにした上で、原審判断を維持しています。
民事訴訟の処分権主義と裁判上問題となる注意義務
このように列挙してみますと、民事事件では注意義務のうち、上記民事事件判決でいうところの「催行検討義務」の内容が具体的に摘示されていないようにも思われます。
しかし、民事事件において原告らは、
被告には、七日のコースについて無理な設定をした過失、天候予測及び出発判断を怠った過失、参加者の防寒装備について何らの対応もせず、その確認もしなかった過失、七日の登山時に途中で不帰岳避難小屋に引き返す判断をしなかった過失及び参加者に低体温症が発生するのを防止するための措置を何もとらなかった過失がある
熊本地判平成24年7月20日
と被告の過失行為の内容について相当具体的に主張しています。
これに対し被告は、
本件事故は、被告が予測することがおよそ困難な急激な天候の変化等を原因とするものであり、このような予測不可能な事態によって生じた事故については、被告に過失はない
熊本地判平成24年7月20日
と反論しています。
民事訴訟は処分権主義を採用し、訴訟当事者に審判対象の特定や範囲の限定を原則として委ねています。
そして、過失に関する主張・立証責任は原則として原告にあることから、この原告の主張をベースに裁判所は上記の民事事件の過失判断をおこなっていることになります。
したがって、「清水尾根の途中において,本件登山を中止して不帰岳山頂直下の避難小屋に引き返すなどの対応をとる義務」があったとする原告の主張を裁判所がとくに否定していないことから、裁判所の判断としての「登山を中止するなどの適切な処置等をすべき義務(以下「催行検討義務」という。)」は、原告が主張する当該義務を含むものであろうと考えられます。
そうしますと、刑事事件の「遅くとも清水尾根の途中において,その後の本件登山を中止し不帰岳の避難小屋に引き返すなどして被害者らの生命及び身体の安全を確保し,遭難事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務」と民事事件の注意義務の内容はあまり変わらないものと言えそうです。
注意義務に関する裁判上の認定とその証拠
ところで、ⅰ)事件の民事事件のいうところの「事前情報収集義務」の具体的内容・範囲、および催行検討義務の内容である清水尾根における不帰岳への引返しの必要性の判断等においては、事件山域の気象状況、地形、登山者の装備・服装等の考察が必要となります。
しかし、この考察には一定の価値判断が必要となります。
たとえば、装備に関し、近時では軽量性等から、旧来型の重装備の登山に対するファストパッキングの優位性が主張されることがあります。
最近は、北アルプスでもファストパッキングの登山者は珍しくなく、どこまで重装備にすべきかは一定の経験に根差した判断が必要となります。
降雪の可能性もあるからといって10月初旬に厳冬期の装備で入山する登山者は見かけませんし、一方、防寒対策に不安があるのも問題です。
また、民事事件で被告は、
白馬山荘の直前において急激な雪風を受ける時まで死亡の危険が生じる事態には直面していなかった。そのため、不帰岳避難小屋に引き返す必要はなかった。また、被告は、上記時点以降、D姉妹を介抱したり、白馬山荘に助けを呼びに行ったりしており、その場でできる最善の努力をしていた
熊本地判平成24年7月20日
と主張していますが、清水尾根で引返すほど気候条件が悪かったかという点に関しては、一般論からしますと、一義的に正解があるとまでは言い難いと考えられます。
具体的な場合に引返すほどの必要性が認められるかは、一定の知見に基づき判断せざるを得ないところがあります。
このように、本件事件は、上記のⅱ)残雪の八ヶ岳縦走遭難事件に比べ、一定の知見に基づく判断を要する範囲が広い事件であったと思われます。
この判断のために裁判所が採用した証拠は、公開されている判決文からは一部しかわかりません。
ただし、民事事件においては、コースの難易度および概要に関し「ヤマケイJOY」が証拠として採用されているようです。
一方、刑事事件1審では、山小屋関係者及び複数の山岳ガイドの供述等を証拠として採用しているようです。
以前の記事でも触れましたが、登山事故の場合、一般的な刊行物の他、事件山域の豊富な知見を有する人の証言が、立証において有用であることは、本件事件でもわかります。