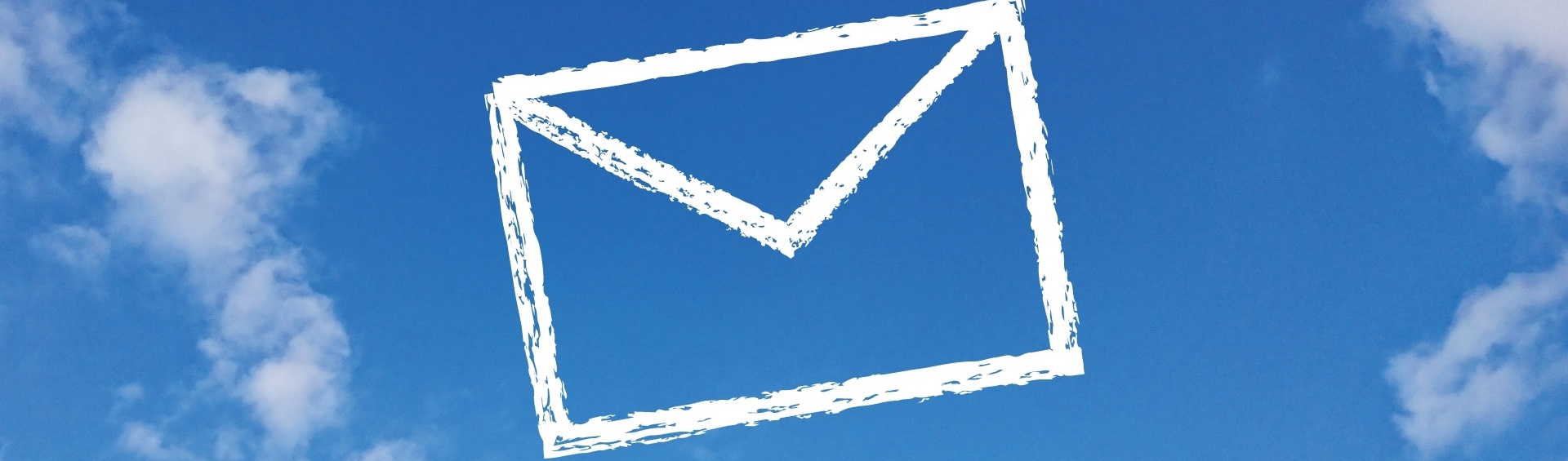大日岳遭難事故について
教育活動の場での登山事故として、ここでは、ⅴ)大日岳遭難事故をみてみます。
下記の記事で扱っていますⅲ)石鎚山転落事故は中学の特別活動の登山事故、ⅳ)朝日連峰熱射病死亡事故は高校の課外活動の登山事故で、共に生徒が通う学校が主催する教育活動での登山時の事故です。
これに対し、ⅴ)大日岳遭難事故は、参加に際し大学の責任者の推薦が必要とされていたとはいえ、ワンダーフォーゲル部所属の大学生が、学外の文部科学省が主催する大学山岳部リーダー研修会リーダー養成講座を受講した際の登山事故であり、学校が主催した教育活動時の事故であるⅲ)石鎚山転落事故、ⅳ)朝日連峰熱射病死亡事故とは異なります。
しかし、ⅴ)大日岳遭難事故も大学のサークル活動の一環、あるいはその延長線上の登山事故とも言い得ます。
大日岳遭難事故の概要について
ⅴ)大日岳遭難事故は、平成12年3月に文部科学省(当時文部省)が主催した大学の山岳部およびワンダーフォーゲル部のリーダーなどを対象とした大学山岳部リーダー研修会の一環の、同年3月3日から4泊5日の予定でおこなわれた実技実習の雪山登山において発生した事故です。
この事故が発生した大学山岳部リーダー研修会実技実習の学生(研修生)および引率者らの一行は、平成12年3月3日に入山、同月5日に前大日岳から早乙女岳~一ノ谷の頭を経て大日岳の手前(北西側)2370mのピークから、大日岳山頂に登頂しました。
一行は、登頂後、大日岳山頂付近の尾根線から北東に伸びた雪庇上で休憩しましたが、その休憩中の午前11時25分ころ、雪庇が崩落、異なる大学のワンダーフォーゲル部から参加していた学生2名(以下「A」および「B」といいます。)がその雪庇の崩落によって発生した雪崩に巻き込まれ死亡しました。
尚、この雪庇は、全体の大きさが40m以上で、大日岳山頂付近から水平距離約27mの地点で崩落し、雪庇の先端から長さ約15mの部分が崩落したことになり、崩落地点における破断面の高さは10m程度であったと推定されています。
裁判の概要
ⅴ)大日岳遭難事故では、死亡したAおよびBの遺族が、国家賠償法に基づく損害賠償、あるいは安全配慮義務違反による債務不履行責任に基づく損害賠償を求め、民事訴訟を提起しました。
この裁判は1審で原告の請求が一部認容された後、控訴されましたが、控訴審で和解が成立しています。
そこで、ここでは1審判決をみていくこととします(以下、とくに断りのない限り、ⅴ)事故の1審の裁判およびその判決を「裁判」または「判決」といいます。)。
裁判所の判断
ⅴ)大日岳遭難事故では、なぜ一行が雪庇の上で休憩を取ることになったのかが、まず疑問となり得ます。
この点について、裁判所は、
講師らは・・・大日岳山頂付近の雪庇の大きさは全体で10m程度であろうと推測していたため・・・雪原の下になっている山稜及びその延長上にある山頂は、山頂方向に向かって左側に見える見かけの稜線上から10m程度右側の称名川側の地点にあるものと想定し、・・・雪庇全体を回避するため、上記見かけの稜線上から十数m程度称名川側の地点に向かって登高ルートを選定した
富山地判平成18年4月26日
と、雪庇を実際の大きさより小さく誤認したため、雪庇の上で休憩を取ることになったと認定しています。
次に、本件登山事故が大学のサークル活動の一環、あるいはその延長線上に位置づけられる研修で発生したものであることから、当該研修の引率者には、ⅲ)石鎚山転落事故、ⅳ)朝日連峰熱射病死亡事故の引率教員に課せられていたような、学校教育活動において教員が生徒に対して負う高度の安全配慮義務、注意義務が課せられていたのかが問題となり得ます。
この裁判においても、この点が争点となり、裁判所は次のように判示しています。
・・・講師らが研修生の生命身体に対する安全を確保すべき注意義務を負っていたことは上記のとおりであるけれども、その具体的内容及び程度は、参加者の年齢、個々の事柄及び具体的状況によって異なるものであるところ、本件研修会の参加者は、成年者またはこれに近い年齢の者であるばかりでなく、いずれも各大学山岳部等のリーダーにふさわしい者として選択された者であるから、その肉体的、精神的発達状況に照らすと、本件研修会が文部科学省(当時は文部省)により主催されたものであることなどを考慮しても、講師らは、中学生、高校生等に対するのと同様な極めて高度の注意義務を負っていたということはできない
富山地判平成18年4月26日
このように、判決では、研修生は大学生であり、その肉体的、精神的発達状況からして、中学生や高校生と異なるのであり、学校教育活動において教員が生徒に対して負うような安全配慮義務は、大学生である研修生の引率者には課されるものではないとしています。
そこで、研修会の引率者は、中学生、高校生の引率教員が生徒に対し負うような極めて高度な注意義務を、研修生に対して負っていたわけではないとしています。
このことからしますと、この事故の引率者の過失については、一般のツアー登山のツアーリーダーと同様に判断されることとなりそうです。
判決では引率者(判決では「講師」といっています。)の注意義務について次のように述べています。
本件事故当時の登山界において、雪庇の吹き溜まり部分は、先端部分と同様に危険であるとまでは認識されていなかったものの、その危険性を指摘する登山家も存在し、構造上の危険を有するものであって・・・その外見からは内部の構造や安定度等を把握することは困難であること、また、実際は、先端部分と吹き溜まり部分とを区別することは極めて難しいことが認識されていたといえ・・・そうすると、本件事故当時の登山界においては、雪庇の吹き溜まり部分についても、先端部分に比べればかなり低いものの崩落する危険性があること、また、先端部分との区別ができないことから、誤って先端部分に進入し、踏み抜きなどにより転落する危険性があることが認識されていたというべきであって、しかも本件研修会の性格を考慮すれば、講師らは、危険を回避するために、原則として、雪庇の先端部分のみならず吹き溜まり部分にも進入しないように登高ルート及び休憩場所を選定すべき注意義務を負っていたというべきである
富山地判平成18年4月26日
この判示をみますと、ⅴ)大日岳遭難事故の判決では、下記の記事でも扱っていますⅰ)2006年白馬岳遭難死事件、ⅱ)残雪の八ヶ岳縦走遭難事件のツアーリーダーと同等、あるいは「しかも本件研修会の性格を考慮すれば」と言及していることから、若干高めの注意義務を引率者についても想定していると考えられます。
そして、「危険を回避するために、原則として・・・吹き溜まり部分にも進入しないように登高ルート及び休憩場所を選定すべき注意義務」を負っていたと認定しています。
その上で、雪庇の規模に関する予見可能性について、
本件事故当時の登山界においては、本件雪庇の大きさを正確に予見することが可能であったということはできない。しかしながら・・・大日岳山頂付近では、従来、全体の大きさが少なくとも25mから30m程度の雪庇が形成されていたことがうかがわれ・・・残雪期に大日岳山頂に登り、大日小屋付近から山頂付近を観察するなどすれば、目測によっても・・・山頂付近では冬期には少なくとも全体の大きさが25m程度の雪庇が形成されることを把握することは十分可能であったし、また、大日岳山頂付近の雪庇のおよその規模については、地元の登山家等の間でも認識されていたから、地元の登山家から情報収集を行うことなどによっても、同様の認識を持つことは可能であったというべきである。
富山地判平成18年4月26日
以上からすると、講師らは、本件事故当時、本件雪庇全体の大きさが少なくとも25m程度あることを予見することは可能であったというべきである
として、「本件事故当時、本件雪庇全体の大きさが少なくとも25m程度あることを予見することは可能であった」と、予見可能性を認定しています。
次に、引率者の過失について、
講師らは、本件事故当時、大日岳山頂付近の雪庇の規模が25m程度あることを予見することは可能であったから、見かけの稜線上から少なくとも25m程度の距離をとって、登高ルート及び休憩場所の選定をすべきであり、講師らの登高ルート及び休憩場所の選定判断には過失があるというべきである
富山地判平成18年4月26日
「見かけの稜線上から少なくとも25m程度の距離をとって、登高ルート及び休憩場所の選定」して雪庇の崩落、踏み抜きなどの危険を回避すべきであったのに、それをせずに登高ルートおよび休憩場所を選定したとしてその回避義務に違反したとして、過失を認定しています。
ここでは、「見かけの稜線上から少なくとも25m程度の距離をとって、登高ルート及び休憩場所の選定しなかった」ことを具体的な過失行為としていることとなります。
そして、この過失行為とAおよびBの死の結果との間の因果関係に関し、
前記当事者間に争いがない事実によれば、本件雪庇は全体の大きさが40m程度であり、先端から約15mの部分で破断し、崩落するに至ったもので・・・講師らが、見かけの稜線上から25m程度の距離をとって登高ルート及び休憩場所の選定をしたとしても、研修生らが本件雪庇の上に進入すること自体は回避できなかったことになるけれども、研修生らが本件雪庇の少なくとも先端から約15mの部分を超えて進入することはなかったというべきで・・・仮に、調査報告書・・・が指摘するように・・・主として自重による曲げモーメント(下方に曲げようと作用する力)により、引っ張り強度を超える力がかかって、先端から約15mの部分で破断し、崩落するに至ったもので・・・講師ら及び研修生らが本件雪庇上に進入したことによって崩落したものではないとしても、本件雪庇の崩落自体は発生したことになるけれども、研修生らが本件雪庇から転落することはなかったから、本件事故の発生は回避できたというべきで・・・見かけの稜線上から十数m程度の距離をとって登高ルート及び休憩場所の選定を行った講師らの判断には過失があり、見かけの稜線上から25m程度の距離をとって登高ルート及び休憩場所の選定を行えば、本件事故は回避できたので、過失と本件事故発生との間に相当因果関係が認められる。
富山地判平成18年4月26日
としています。
ここでは、
- 雪庇は全体の大きさが40m程度で、先端から約15mの部分で破断し、崩落した
- 見かけの稜線上から25m程度の距離をとって登高ルート、休憩場所を選定していても雪庇の上に進入することは回避できなかったことになるが、雪庇の少なくとも先端から約15mの部分を超えて進入することはなかった
- 雪庇が、講師らおよび研修生らが雪庇上に進入したことで崩落したわけではなかったとすると、本件雪庇の崩落自体は発生したことになるが、上記1から、雪庇が崩落したのは先端から約15mの部分であり、上記2から見かけの稜線上から少なくとも25m程度の距離をとって登高ルート、休憩場所の選定をしていれば(過失行為をおこなっていなければ)、雪庇の少なくとも先端から約15mの部分を超えて進入することはなく(雪庇内の先端から約15m以内の部分に立ち入ることはなく)、研修生らが本件雪庇から転落することはなかった
として、見かけの稜線上から少なくとも25m程度の距離をとって、登高ルートおよび休憩場所の選定をしていれば、雪庇から学生らが転落することはなかったとして、過失行為と、AおよびBの死の結果との間の因果関係を認定しています。
ただし、この事故では、第三者からなる事故調査委員会により「北アルプス大日岳遭難事故調査報告書」が作成され、その中では、他の経験豊かな登山家でも、当時一般的に入手できた情報等からは、雪庇の形成および崩落を予見することはできなかったであろうと結論付けられていました。
しかし、判決では、雪庇の形成および崩落の予見は可能であったと認定しています。
このように事故調査委員会の結論と裁判所の判断が異なっていることからしても、引率者の過失に関する判断はそれ程容易なものではなかったと考えられます。
裁判における立証の問題
ⅰ)2006年白馬岳遭難死事件の場合、ツアーリーダーが、事故当日の朝の天気情報から、事故当日に生命の危険が生じかねない程に天候が悪化する可能性があるということを、予見し得たことを立証する必要がありました。
このようなⅰ)事件の過失認定に際しましても、リーダーが天候悪化を予見し得たかについては、事故発生時の客観的状況を認定した上で、一定の専門的知見に基づき判断を下す必要がありました。
ただし、この立証に必要な、当日朝の気象情報、天気予想図および事故当時の天気図といった客観的状況に関する証拠は比較的容易に入手でき、また天候悪化の予見可能性の立証に必要な、専門的知見である気象予想に関する一般的文献も、比較的容易に入手することが出来ます。
しかし、ⅴ)大日岳遭難事故では、事故発生時の客観的状況である、事故発生直前の雪庇の状態、および雪崩の発生状況に関する、客観的な証拠の入手は困難です。
また、専門的知見である雪崩の発生メカニズムに関しては、気象変化に関する研究ほど進んではいなかったこともあり、その発生メカニズムおよび当日の雪崩の発生原因を特定し得る証拠の入手も困難でした。
このような証拠の収集面の問題からしましても、ⅰ)2006年白馬岳遭難死事件以上に、ⅴ)大日岳遭難事故における過失の立証は困難であったであろうと思われます。