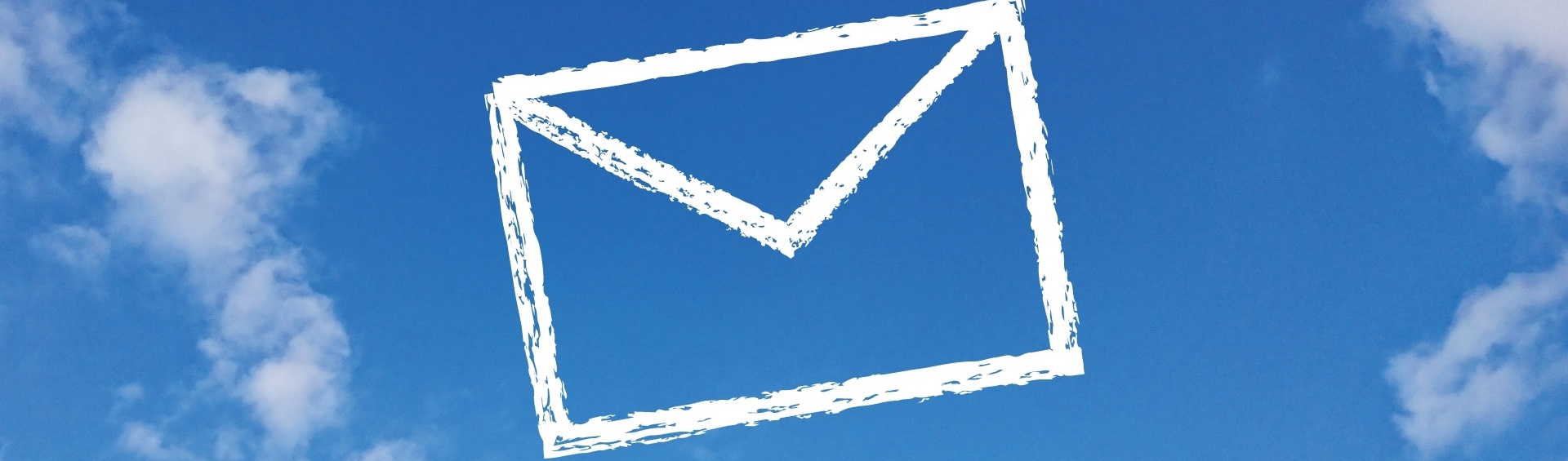目次
木曽駒ケ岳雪崩事故の概要
下記の記事で扱いましたが、18)木曽駒ヶ岳雪崩事故では、学生7名、OB1名と教員2名からなる高等専門学校登山部のパーティーが下山時に雪崩事故にあい、学生6名とOB1名の計7名が圧死しました。
その後、死亡した学生のうち一人(以下「A」といいます。)の遺族が提起した損害賠償訴訟(以下「一次訴訟」といいます。)において、1審は、引率教員(以下「乙」および「丙」といいます。)の過失を否定しましたが、控訴審(東京高判昭和61年12月17日)では、引率教員の国家賠償法1条1項の過失を認定し、上告審も過失を認定しています。
この一次訴訟につきましては、下記の記事で扱っておりますので、参考にしていただければと思います。
一次訴訟の1審判決後、雪崩事故の被害者のうち、Aを除く6名(うち、同高等専門学校のOBである被害者を以下「B」といいます。)の遺族が、学生に対する安全配慮義務違反、およびBを含む被害者に対する国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求め提訴しました(以下「二次訴訟」といいます。)。
二次訴訟は、一次訴訟とは異なり、1審から上告審まですべての審級において、引率教員の国家賠償法1条1項上の過失を認定しています。
尚、一次訴訟上告審と二次訴訟上告審は、同日に判決の言い渡しがなされています。
二次訴訟の疑問点
問題の所在
二次訴訟では、OBであるBとの関係では、安全配慮義務違反の主張はなされていません。
これは、高等専門学校の設置者である地方公共団体(以下「甲」といいます。)は、在学契約関係により、安全配慮義務を在校生である学生との間では負っているものの、OBとの間では在学契約は存在しないことから、安全配慮義務は問題とならないと考えられたからであると思われます。
しかし、ここで問題となるのは、事故の発生した登山においては、OBは、学生と異なり、教員の補佐的な役割も果たしていたことから、引率教員のBに対する注意義務は、学生に対するものとは異なるのではないかという点です。
二次訴訟1審判決
二次訴訟第1審(東京地判昭和63年3月24日)では、引率教員の注意義務に関して、
ところで、一般に、登山活動にはさまざまな危険が存在することは公知の事実であり、したがつて、登山パーティーのリーダーは、常にかかる危険の存在に注意を払い、極力その危険を回避してパーティー構成員の安全を確保すべき注意義務があることはいうまでもないが、右に見たとおり、学校行事として行われる登山については、その教育活動の目的からみて、何にも増して安全を確保すべきことが各学校の関係者に繰り返し指摘されていることに鑑みると、学校行事としての登山の場合は、一般の場合以上に構成員たる生徒らの安全を確保すべきことが求められ、その危険の回避については、学校側に対し、より一層の慎重な配慮が要求されているというべきであつて、したがつて、特に、本件高専山岳部のように一六歳から一九歳の生徒を構成員とする学校行事としての登山を引率する者は、より一層右の構成員の生命、身体の安全を確保すべき注意義務が存するというべきである。
東京地判昭和63年3月24日
と判示しています。
この引用部分でも、「学校行事としての登山の場合は、一般の場合以上に構成員・・・の安全を確保すべきことが求められ・・・特に・・・一六歳から一九歳の生徒を構成員とする学校行事としての登山を引率する者は、より一層右の構成員の生命、身体の安全を確保すべき注意義務が存する」とされているように、二次訴訟第1審の判決でも、木曽駒ヶ岳雪崩事故の引率教員の過失を認定するに際し、16歳から19歳の学生を引率していたことを理由として、引率教員の注意義務を一般のパーティー登山のリーダーより高くした上で、注意義務違反を認定しています。
ここで問題となるのは、
- Bは高等専門学校のOBであり、学生ではないこと
- Bは年齢的にも事故当時24歳であったこと
といった点です。
上記のように二次訴訟1審が、高い注意義務を16歳から19歳の学生を引率していたことを理由に認定していることからしますと、引率教員は、この高い注意義務を24歳のOBであるBとの関係では負っていないようにも思われます。
この点に関し、二次訴訟1審では、
・・・Bは・・・OBとして本件合宿への参加を申し出たこと・・・合宿にOBが参加する場合には、OBが技術コーチとなる慣例が存すること・・・在学生の信頼するOBが参加することは技術の向上、連帯意識の向上等に効果的であり、また引率教員の補佐役という意味でもOBの参加が必要なものであると考えられていることをそれぞれ認めることができ、これらの事実によれば、Bは、同好の士がお互いにパーティーを組むような場合と異なり、引率教員である乙らの補佐役として本件合宿に参加したのであるから、最終的にはBもまた本件パーティーの実質的なリーダーである乙らの指揮の下にあつたものと解するのが相当である。したがつて、Bもまた乙らによる公権力の行使に服すべき地位にあつたものと解されるから、被告は、その主張する抗弁事実が認められない限り、Bに対しても国家賠償法一条一項の責任を負うと解するのが相当である。
東京地判昭和63年3月24日
と判示して、Bに対しても学生に対するのと同じ注意義務を前提に過失を認定しています。
しかし、二次訴訟1審では、上記の過失認定の後で、
・・・確かにBは本件パーティーにおいて乙の指揮の下にあつたと認められるが、他方で、Bは、登山経験をほとんど有しない他の生徒とは異なつて乙に次ぐ登山経験を有しており、しかも、乙とともに下山ルートについての偵察にも出るなどして、いわば乙の片腕として同人による引率、指導を補佐していたのであつて、本件パーティーが下山すべきか停滞すべきかについての重要な意思決定に際し、乙に対して雪崩の危険等について適切な意見を具申すべき地位にあつたと認めることができるにもかかわらず、偵察後の協議において下山について特に異論を述べることなく、乙の判断に安易に従つたものであること、及び下山行動開始後、乙の指示により、パーティーの先頭に立つて歩行している最中に雪面にクラックが生じたのを目撃したにもかかわらず、これを雪崩の前兆の一つとみて直ちに歩行を停止し、乙らと対策を協議するなどの措置をとらなかつたことがそれぞれ認められる。被告は、Bの損害額を判定するにあたつて過失相殺の主張をしてはいないが、右の事情を考慮するとき、Bは本件遭難事故の被害者であると同時に、乙の補佐として、右事故の発生につき主体的にいくばくかの原因を与えたことも否定できないので、少なくとも信義則ないし公平の観点から損害額の調整をする必要があると認められるから、当裁判所は、Bにつき過失相殺による減額を考慮せざるを得ず、右認定の事情に鑑みれば、これによる過失相殺の程度は二割をもつて相当と考える。
東京地判昭和63年3月24日
として、被告が主張していないにもかかわわらず、Bに対してのみ過失相殺を認定しています。
控訴審および上告審の判断
その後、二次訴訟でも控訴されましたが、控訴審(東京高判平成元年5月30日)もBに対する判断を維持し、更に、上告審(最判平成2年3月23日)において最高裁判所は、
所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、右事実関係の下において、本件春山合宿の引率指導をしていた乙及び丙に、本件春山合宿に参加した本件高等専門学校の卒業生のBを本件春山合宿の実施により生じるおそれのある危険から保護すべき注意義務があったものとした原審の判断は、正当として是認することができる。
最判平成2年3月23日
として、引率教員が卒業生との関係でも、安全に配慮する注意義務を負っていたことを認定しています。
二次訴訟における過失と過失相殺の問題
過失認定と過失相殺の関係
このBに関する損害賠償請求の判断に関しては、過失相殺を認定することにより、妥当な結論を導いているようにも思われます。
しかし、登山事故で不法行為に基づく過失責任(民法709条)を追及する場合、過失相殺については、民法722条2項において、
被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
民法722条2項
とされており、過失相殺は損害賠償の金額の算定上の問題であり、過失認定の際に考慮されるものではないことがわかります。
尚、本件の場合、国家賠償法4条に
第四条 国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法の規定による。
国家賠償法4条
と規定されていることから、民法722条2項が準用されると考えられます。
そうしますと、法理論的に考えると、過失相殺はあくまで損害額の認定上の問題であり、過失(注意義務違反)の有無の判断が先行されるはずです。
もし、過失が認定出来なければ、損害の金額の判断はなされず、請求は棄却されるはずです。
そして、その場合、過失相殺は問題となりません。
二次訴訟判決に関する疑問点
この点に関する裁判所の判断の合理性を検討するために、学校登山で引率教員が学生(生徒)に対し負う注意義務の程度を100としてみます。
ここで、この事故が学校登山ではなく、構成員に学生が含まれず、登山パーティーの構成が乙、丙およびBの3名であったと仮定してみます。
その場合は、上記二次訴訟1審判決の趣旨からしますと、乙の負う注意義務の程度は、学校登山の場合より低くなるものと考えられます。
そこで、この登山パーティーの構成が乙、丙およびBのみであった場合のリーダーが負う注意義務を、学校登山の場合の100より低い80とします。
そうしますと、登山事故発生時、引率教員であるリーダーが90の注意義務しか払っていなかった場合、前者の学校登山の場合であれば、学生(生徒)との関係では、100の注意義務を果たしていないことから注意義務違反が認定され、過失責任が成立し得ます。
しかし、後者のように、学校登山ではなかったと仮定すると、リーダーは80以上の注意義務は払っていたのですから、理論的には注意義務違反は成立しないこととなります。
このように、登山パーティーの過失認定に際し、リーダーが構成員に対し負う注意義務の程度が相対的に(各々個別に)決まると仮定しますと、二次訴訟1審判決のように過失相殺を用いて妥当な結論を導くことは、Bに対する過失認定を学生らへの過失認定とは別に、詳細な検討を加えていない点に、法理論的に問題を内包することとなりそうです。
この点について、上記判決引用部分の
Bは、同好の士がお互いにパーティーを組むような場合と異なり、引率教員である乙らの補佐役として本件合宿に参加したのであるから、最終的にはBもまた本件パーティーの実質的なリーダーである乙らの指揮の下にあつたものと解するのが相当
東京地判昭和63年3月24日
の部分から、乙の注意義務の程度は、パーティーの学校登山という性質により決定されるものであり、構成員全員に対し、リーダーは同種・同等な注意義務を負っていると考えるのであれば、過失認定上、Bとの関係でも乙は他の学生に対するのと同様な注意義務を負っていたと考えることとなり、上記判決と同様な結論に達することが出来ます。
しかし、そのように考えますと、不法行為との関係では、乙は、補佐役あるいは実質的なサブリーダーであった引率教員の丙に対しても、学生と同様な注意義務を負うこととなります。
そうしますと、仮に丙も当該事故で死傷していたとすると、過失相殺の割合をどのように認定するかは別として、甲は丙に対しても過失責任を負っていたことになりそうです。
不法行為責任が結果責任ではなく、行為責任であることと考え併せますと、学校登山において、リーダーはサブリーダーである同僚の引率教員、あるいはOB等が引率補助で参加していた場合、その引率補助者に対しても学生(生徒)に対するのと同様の配慮をしなければ、損害賠償責任が発生する可能性があることになります。
果たして、そのような配慮をリーダーが山行中になし得るのかは疑問ではあります。
この点、OBは、かつては引率教員の教えを受けていたのでしょうから、事実上、卒業後も上下関係が残り、通常のサブリーダーあるいは引率補助者とは異なり、引率教員の考えに異を唱えることができない立場にあったと考えると、上記の問題もクリアできるようにも思われます。
上告審である最高裁が、上記引用のように、「乙及び丙に・・・卒業生のBを・・・危険から保護すべき注意義務があった」としており、乙のみではなく、丙にもBに対する注意義務を課していることからしますと、このようにとらえるのが妥当とも考えられます。
二次訴訟判決の位置付け
法理論的な疑問はさておき、木曽駒ヶ岳雪崩事故の二次訴訟では、学校登山における事故において、補助者として参加した者に対しても、学校設置者が損害賠償義務を負うことがあり得ることを明らかにしていると言い得ます。