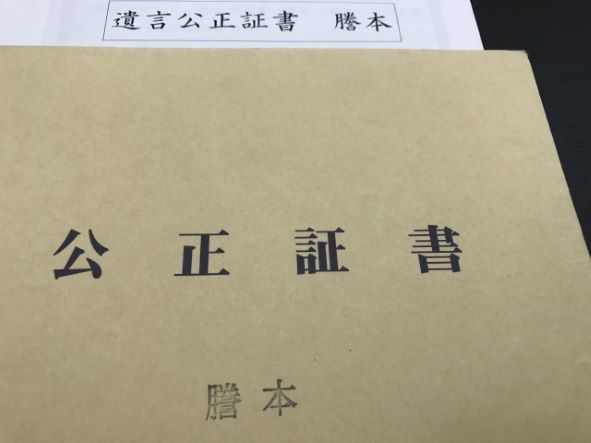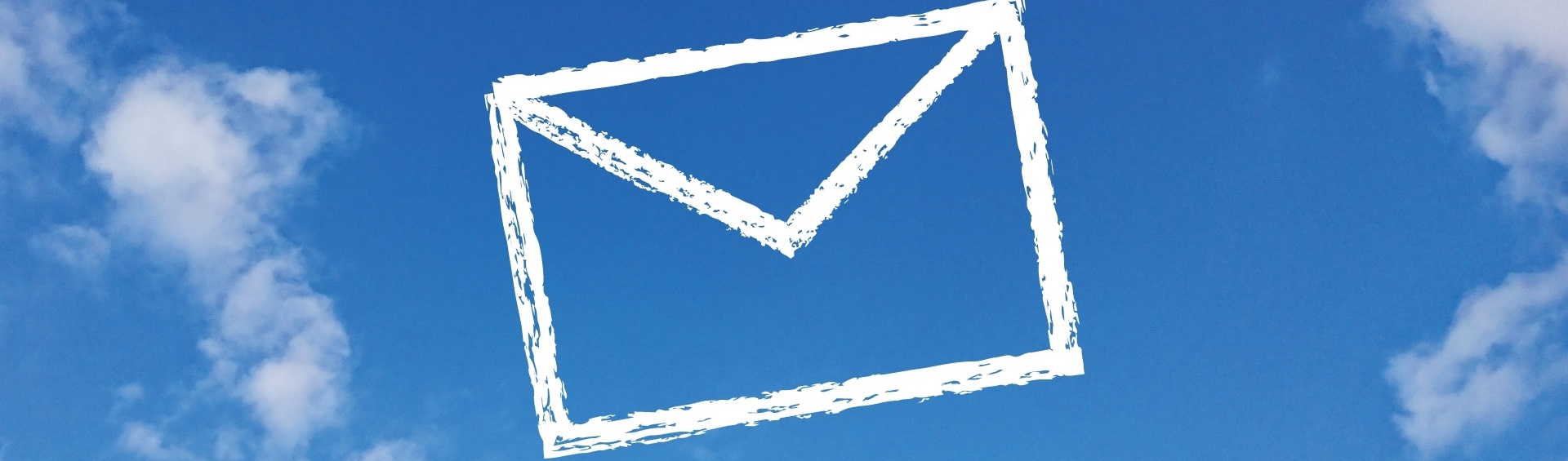目次
遺言書、遺言、「ゆいごん」、「いごん」など
遺言とは、自分の死後の法律関係を定める最終の意思表示とされており、主に民法960条~1027条において、遺言の方式、効果が定められています。
この「遺言」という漢字の読み方は、一般的には「ゆいごん」ですが、法律用語としては、「いごん」と読まれます。
「いごん」は、民法の要件を充たしたものの呼称で、「ゆいごん」に包含されるとの考え方もあるようです。
弁護士などに遺言に関する相談をしますと、「いごん」と言われ、戸惑うこともあるかもしれません。しかし、「ゆいごん」のことを言っているのだととらえても、さほど問題はありません。
遺言は、自分の死後のことを決めるものということもあり、民法では、書面で作成することを原則としています。
この遺言の内容を書面にしたものを、一般的には、「遺言書」、「遺言状」ということが多いようですが、法律用語では、「遺言書」とされています(民法1004条1項参照)。
この「遺言書」も、一般的な読み方は、「ゆいごんしょ」ですが、法律用語としては、「いごんしょ」と読むことは、「遺言」の場合と同じです。
遺言の方式の種類について
民法で定められた法的に有効な遺言の仕方のことを、民法では、遺言の方式といいます。
この遺言の方式としては、大きく分けて、通常の場合におこなう「普通の方式」と、遺言をする人の死亡が迫っているような特別の事情がある場合にのみ認められる「特別の方式」によるものがあります。
尚、以下、特に断りのない限り、普通の方式の遺言のみ扱うこととします。
遺言の普通の方式としましては、
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
があります。
尚、自筆証書遺言書保管制度は、上記の自筆証書遺言の遺言書の保管方法に関する制度です。ここでの分類としては、自筆証書遺言書保管制度のために作成される遺言書も自筆証書遺言に含まれることとなります。
自筆証書遺言書保管制度につきましては、後ほど触れることといたします。
遺言の方式としましては、一般的には、自筆証書遺言と公正証書遺言が用いられます。そこで、ここでは、自筆証書遺言と公正証書遺言に触れることといたします。
秘密証書遺言にご関心をお持ちの方は、民法970条~972条に規定されていますので、条文をご確認いただければと思います。
自筆証書遺言について
自筆証書遺言は、遺言をする人が、自筆(財産目録はPCなどでも作成可能となりました。)で作成するものです。
遺言書の書面中に必ず記載しなければならない事項、押印の必要性などの形式的な要件は民法968条で決められています。
民法968条で定められた要件を欠く遺言書による遺言は、無効となり得ます。
しかし、民法の条文には、具体的な詳しいことは書かれていないことから、自筆証書遺言を作成する場合は、まずは、書籍などで書き方を確認する必要があります。
この自筆証書遺言の方式では、実際に相続が開始したとき(遺言を残される人が亡くなったとき)、原則として、相続人が家庭裁判所で検認という手続きをとる必要が生じます。
ただし、自筆証書遺言書保管制度を利用した場合、検認は不要となります。
公正証書遺言について
公正証書遺言とは、公証役場において、公証人により公正証書として作成される遺言書による遺言です。
公証役場に電話をして公正証書遺言の作成の相談をしますと、事前に準備が必要なもの、考えなければならない事項を教えてもらえます。
また、遺言書の文言も公証役場で原案を作成してくれます。
尚、公正証書遺言の作成費用は、政令で決まっており、公証人連合会のサイトで確認できます。作成費用は、遺言により相続する財産の額などにより決められています。
また、自筆証書遺言と異なり、相続開始時に相続人は検認手続きをおこなう必要はありません。
自筆証書遺言書保管制度について
自筆証書遺言書保管制度は、自らが作成した自筆証書遺言を遺言書保管所(法務局)で保管してもらう制度です。
遺言書保管所に遺言書を預ける際に、遺言書保管所において、遺言書の形式的な要件のチェックはして貰えます。しかし、遺言の内容の相談には応じてはもらえません。
遺言者が死亡したときには、遺言書を預ける際に指定した、相続人、遺言執行者などの内1人に対し、遺言保管所から、遺言書を預かっていることが通知される死亡時通知の制度もあります。
この保管制度を利用した場合、自筆証書遺言ではありますが、相続人は、検認の手続をおこなう必要はありません。
しかし、この制度を利用しても、必ずしも遺言の有効性が推認されることにつながらないことに留意が必要です。
このことは、遺言書保管所が、遺言書の内容に関し、一切関与しないことの当然の帰結ともいえます。
相続開始後に問題となりがちなこと
形式的要件を欠く遺言書
公正証書遺言は、公証役場で作成してもらうものであることから、形式的要件をかくことは通常はありえないと考えられます。
また、制度が開始して間もないことから、明確ではありませんが、自筆証書遺言書保管制度を利用して保管されていた遺言書に関しても、保管時に遺言書の形式的要件の確認を遺言書保管所にておこなうことから、形式的要件が問題となるケースは少ないものと考えられます。
そこで、最も形式的要件が問題となるのは、弁護士などの関与もなく作成され、自筆証書遺言書保管制度も利用されない自筆証書遺言であると思われます。
尚、形式的要件を欠いた自筆証書遺言書は無効とされることがあります。
遺言の無効に関しましては、下記の記事でも扱っていますので参考にしていただければと思います。
遺言能力を欠く状態で作成された遺言書について
遺言の有効性に関して、特に問題となるのは、認知症の進行などにより、遺言書作成時点で、遺言者(遺言を残す人)に、遺言をする能力(「遺言能力」といいます。)が欠けていた場合です。
この遺言能力に関しましては、民法961条~963条で定められていますが、通常の財産処分時に問題となる行為能力よりは低い能力で足ると考えられています。
相続開始後に、遺言時に遺言能力が存在したかについて争いになるケースは少なくありません。この争いは、自筆証書遺言のみならず、公正証書遺言でも争われることがあります。
遺言書が、遺言能力を欠く状態で作成されたと認定された場合、その遺言書による遺言は無効となります。
複数の遺言書を作成した場合
複数の遺言を作成し、遺言の内容が相互に矛盾する場合(一方の遺言の内容を実現すると、他の遺言の内容を実現できないような場合、例えば、長女に自宅の土地・建物を相続させる内容の遺言書を作成したのちに、長男にも同じ自宅の土地・建物を相続させる内容の別の遺言書を作成したような場合)、先に作成した遺言は法的には撤回されたこととなり、後に作成した遺言書のみ有効となります(民法1023条1項参照)。
夫婦連名の遺言書の無効
仲の良い夫婦でも、連名で1枚の遺言書で遺言をすると、遺言は無効となります。
この点につきましては、下記のブログ記事で詳しく扱っておりますので、参考にしてみてください。
遺言が無効とされたときの相続について
遺言が上記の理由などで無効とされた場合、その無効とされた遺言はなかったこととして扱われます。
1通のみ遺言書を作成しており、その遺言書が無効となった場合、遺言は残されていなかった扱いとなります。
その場合、相続人は、原則として、法定相続割合に従って、遺産を(プラスの財産のみならず負債も)相続することとなります。
通常は、相続人間の遺産分割協議により、遺産の分配がおこなわれることとなります。
遺留分を侵害する内容の遺言を残した場合の問題
相続人には、法律により、遺産の一定割合が留保されており、その留保分を遺留分といいます。
しかし、特定の相続人への相続分を遺留分以下とする内容の遺言書も有効ではあります。
ただし、遺言により、相続分を遺留分以下にされた相続人は、相続開始後、他の相続人、受贈者などに対し、遺留分と遺言による相続分の差額を遺留分侵害額として請求できることとなります。
この、遺留分に関しては、下記のブログで詳しく扱っておりますので、参考にしてみてください。
遺言執行者について
遺言による個別財産の分配に際しては、手間がかかることも、相続人間で見解の相違が生じることもあります。
そこで、相続開始後に遺言の内容に従い、遺産の分配をおこなう遺言執行者を、遺言で指定しておくことも可能です。
しかし、遺言執行者は、遺言執行に関し、法的に一定の責任を負うことになります。そのこともあり、誰に遺言執行者を頼むかについては、慎重に考える必要があります。
尚、遺言書において遺言執行者に指定しても、その指定された人は、遺言執行者となること(遺言執行者への就職)を辞退することも可能となっています。
遺言執行者の職務、責任などに関しましては、下記の記事で扱っていますので参考にしていただければと思います。
遺言の方式選択のポイント
これまで、説明しましたように、遺言の方式としては、通常は、自筆証書遺言か公正証書遺言を選択することとなります。
公正証書遺言のメリット・デメリット
コスト面からしますと、公正証書遺言の方が高くはなります。
しかし、公正証書遺言の場合は、遺言書の文言の原案を公証役場が考えてくれることから、知識がなくても安心して遺言を残すことが出来ます。
ただし、遺留分をどうするのか、具体的財産を誰に、どのように相続させるのが良いのかといった点につきましては、やはり、遺言者(遺言を残す人)が考えなければなりません。
このこともあり、公正証書遺言を選択する場合でも、弁護士などに相談して、遺言書の原案を作成するケースが少なくありません。
自筆証書遺言のメリット・デメリット
一方、自筆証書遺言に関しましては、コスト的には、公正証書遺言と異なり、安価で作成することができるというメリットがあります。
また、これまで、自筆証書遺言であると、相続開始後(遺言者の死後)に遺言書が発見されず、遺言がなかったのと同様に扱われる危険性がありました。しかし、前述の自筆証書遺言書保管制度の創設により、このリスクを一定程度、回避することが出来るようになりました。
更に、相続人の検認の手続に関しましても、同保管制度を利用しますと不要となります(同制度を利用しないと、自筆証書遺言では、相続開始時に検認手続きが必要となります。)。
その上、同保管制度には、保管時に自筆証書遺言の形式的要件の確認を遺言書保管所がしてくれるという利点もあります。
この自筆証書遺言書保管制度の手数料は、1通3,900円(本記事作成時)と利用しやすい金額となっており、また、同保管制度の利用を検討することにより、自筆証書遺言のデメリットを一定程度、回避することが可能となりました。
しかし、同保管制度を利用しても、自筆証書遺言の内容の有効性の問題は残ることから、自筆証書遺言作成時には、弁護士等に遺言書の作成を依頼するケースも少なくはありません。
そのようなこともあり、残される財産の額によっては、公正証書遺言とコスト面でも変わらない場合も生じてしまいます。
遺言の方式の選択について
このように、公正証書遺言と自筆証書遺言のいずれを選択するのが、より良いのかは、残される遺産の種類・金額、相続人間の関係性、残されたい遺言の内容などの具体的事情により異なるといえそうです。
遺言作成前に整理しておきたいこと
休眠会社の清算
休眠会社が放置されている場合、休眠会社の株式の相続など相続人に負担が生じる場合があります。
必要に応じ、会社清算を検討する必要があります。
その他の財産の整理について
相続財産に遠隔地の遊休地、空家などが含まれていますと、相続人に管理負担が生じることがあります。
空家の管理責任に関しましては、下記の記事でも扱っていますので参考にしていただければと思います。
遺言書の作成に際して、相続人の生活状況を考え、財産の整理を検討することも有意義です。