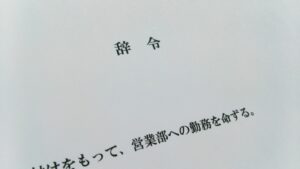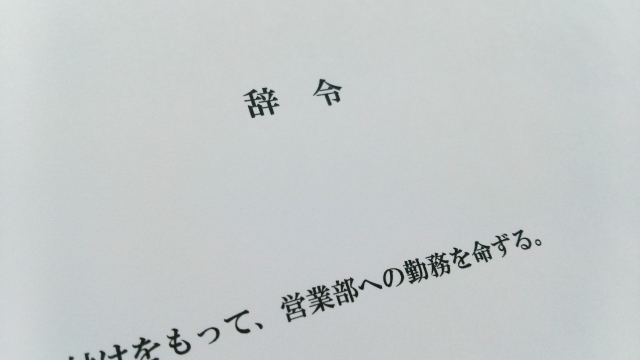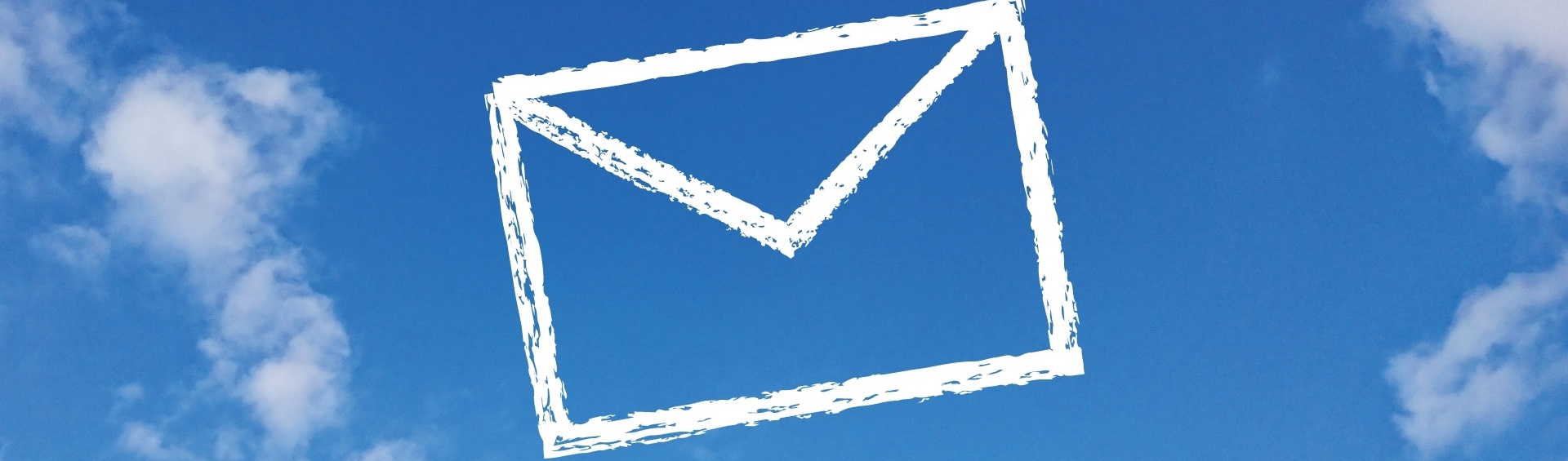会社と従業員の間の雇用契約について民法に規定があります。
その雇用契約を会社から解約する方法の代表的なものとして解雇がありますが、解雇に関しては、労働契約法、労働基準法などにより修正され、民法の規定が直接問題となるケースは多くありません。
一方、従業員からの雇用契約の解約である辞職に関しては、民法の規定が直接問題となります。
ただし、一部労働基準法の規定も問題となります。
ここでは、従業員が辞職する際の規律と、留意すべき点を、民法および労働基準法の条文をみながら解説します。
目次
雇用契約について
民法は623条~631条において、雇用契約に関する規定を設けていますが、会社(使用者)とそこに勤める従業員(労働者)との間の契約関係に関しては、労働契約法、労働基準法などの労働法規に修正され、民法の規定が意識されることは多くはありません。
労働契約の終了について
ところで、労働契約の終了としては、
- 期間の定めのない契約が定年により終了する場合
- 期間の定めのない契約が使用者により終了される場合
- 期間の定めのない契約が労働者により終了される場合
- 期間の定めのある契約が期限の到来により終了する場合
- 期間の定めのある契約が期限の到来前に使用者により終了される場合
- 期間の定めのある契約が期限の到来前に労働者により終了される場合
などがあります。
このうち、2と5のケースでは、使用者による解雇が問題となり、2のケースは労働契約法16条、5のケースは労働契約法17条などが問題となり得ます。
1のケースは再雇用の問題として高年齢者雇用安定法、4のケースは雇止めの問題として労働契約法19条などが問題となり得ます。
これに対し、労働者から労働契約を解約する3と6のケースは、労働法規ではなく、主に民法の問題として、3のケースは民法627条、6のケースは民法626条、628条などが問題となり得ます。
尚、労働者から労働契約を解除し、退職することを辞職ともいいます。
期間の定めのない雇用の辞職に関する規定について
上記の3のケースに該当する期間の定めのない雇用(無期雇用)の労働者が辞職する場合、下記の民法627条が問題となり得ます。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
民法627条
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2 期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。
同条2項と3項は、使用者から解雇する場合の規定であることから、労働者からの辞職申入れ時に問題となるのは同条では1項のみとなります。
そこで、同条からは、期間の定めのない雇用の場合、労働者はいつでも辞職可能であることになり、解釈上、どのような理由でも辞職可能であると考えられています。
尚、退職届などによる退職(辞職)の意思表示から2週間経過すると、契約が終了し、退職したこととなります。
期間の定めのある雇用の辞職に関する規定について
上記の6のケースに該当する期間の定めのある雇用(有期雇用)の労働者が契約期間中に辞職する場合、下記の民法626条および628条の問題となります。
(期間の定めのある雇用の解除)
第六百二十六条 雇用の期間が五年を超え、又はその終期が不確定であるときは、当事者の一方は、五年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。
2 前項の規定により契約の解除をしようとする者は、それが使用者であるときは三箇月前、労働者であるときは二週間前に、その予告をしなければならない。(やむを得ない事由による雇用の解除)
民法626条、628条
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
そこで、民法626条からは、雇用契約に、契約期間として5年超の期間の定めがある場合、雇用期間が5年経過した時点以降、期間の定めのない雇用の場合と同様、労働者はいつでも、どのような理由でも辞職が可能となり、辞職の意思表示をしてから2週間経過すると退職の効果が発生する点も、期間の定めのない雇用契約の場合と同様ということになります。
しかし、労働基準法14条では、
(契約期間等)
労働基準法14条
第十四条 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、五年)を超える期間について締結してはならない。
一 専門的な知識、技術又は経験(以下この号及び第四十一条の二第一項第一号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約
二 満六十歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)
とされていることから、同条から、5年を超える契約期間での期間の定めのある雇用契約(有期雇用契約)を締結することはできないことから、実際には、民法626条は問題とはなりません。
そこで、期間の定めのある雇用契約では、民法628条から、辞職は、「やむを得ない事由があるとき」に限り可能ということになります。
しかし、労働基準法(附則)137条では、
第百三十七条 期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第十四条第一項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)附則第三条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。
労働基準法(附則)137条
と規定されていることから、実際には、期間が1年超の雇用契約の場合は、雇用期間が1年を超えた時点において、期間の定めのない雇用契約同様に、いつでも、どのような理由でも辞職が可能となります。
したがって、実際には、雇用契約期間が1年以内、あるいは1年超の雇用契約期間でも雇用期間が1年以内の場合に限り、上記の民法628条により、雇用契約期間中の辞職について、やむを得ない事由がある場合にのみなし得ることとなります。
もちろん、会社の合意があれば、雇用契約も合意解約し得ることから、その場合、やむを得ない事由がなくとも退職は可能となることはいうまでもありません。
尚、労働基準法15条において
(労働条件の明示)
労働基準法15条
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
さ規定されていることから、労働条件通知書などで提示された労働条件が実際の労働条件と異なっている場合、民法628条にかかわらず、労働者は、雇用契約を即時に解除できることとなります。
辞職時の損害賠償責任について
上記の民法628条では、期間の定めのある雇用契約の契約期間中の辞職が、認められる場合でも、やむを得ない事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負うとされています。
尚、この損害賠償責任に関する規定は、期間の定めのない雇用における辞職の場合にも適用されるとされています。
就業規則による辞職の予告期間制限
上記のように、民法627条からしますと、期間の定めのない雇用契約においては、退職希望日から2週間前までに辞職を申し出ればよいこととなります。
しかし、就業規則において、退職の際、1カ月前までの申し出なければならないといった規定を設けている場合があります。
その場合、民法627条にかかわらず、辞職の申し出を退職希望日の1ケ月前までにおこなう必要があるのでしょうか。
この点については、少し古い裁判例ですが、東京地判昭和51年10月29日において、次のように判示しています。
期間の定めのない雇用契約について、同規定によれば、たとえば、月給制の、役付でない労働者が月の後半に解約を申し入れた場合のように、民法第六二七条による場合よりも短い予告期間で退職できる場合もあるが、その余の場合には、同条による場合より予告期間が長くなるところ、就業規則によって民法第六二七条で定める予告期間を、使用者のために延長することが許されるか、については説が分れているからである。・・・民法第六二七条は、期間の定めのない雇用契約について、労働者が突然解雇されることによってその生活の安定が脅かされることを防止し、合わせて、使用者が労働者に突然辞職されることによってその業務に支障を来す結果が生じることを避ける趣旨の規定であるところ、労働基準法は、前者(解雇)については、予告期間を延長しているが(第二〇条)、後者(辞職)については何ら規定を設けていない・・・また、同法は、契約期間について、民法第六二六条で定める期間を短縮し(第一四条。但し、例外がある。)、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約を禁止し(第一六条)、前借金等と賃金の相殺を禁止し(第一七条)、使用者が強制的に貯蓄をさせ、又は貯蓄金を管理することを禁止し(第一八条第一項)、また、労働者が自発的に貯蓄金の管理を使用者に委託する場合についても詳細な取締規定を設けており(同条第二項以下)、そして、右各条の違反に対しては罰則が設けられている・・・労働基準法第一四条は、端的に、長期の契約期間によって労働者の自由が不当に拘束を受けることを防止するものであり、同法第一六条及び第一七条は、労働者が違約金や賠償額又は前借金等の支払いのため、その意に反して労働の継続を強制されることを、また、同法第一八条は、貯蓄の強制や貯蓄金の使用者管理が場合によっては労働者の足留めに利用され、結局、労働者の自由が不当に拘束されることをそれぞれ防止する趣旨を含むものと解される。・・・
東京地判昭和51年10月29日
以上によれば、法は、労働者が労働契約から脱することを欲する場合にこれを制限する手段となりうるものを極力排斥して労働者の解約の自由を保障しようとしているものとみられ、このような観点からみるときは、民法第六二七条の予告期間は、使用者のためにはこれを延長できないものと解するのが相当で・・・変更された就業規則第・・・条の規定は、予告期間の点につき、民法第六二七条に抵触しない範囲でのみ・・・有効だと解すべく、その限りでは、同条項は合理的なものとして、個々の労働者の同意の有無にかかわらず、適用を妨げられないというべきである。
このように、この裁判例では2週間以上の予告期間を就業規則で設けても、民法627条が優先し、民法627条により予告期間は2週間に短縮されるとしています。
しかしながら、現在でも、就業規則の規定が優先するとの説もあります。
ただし、就業規則の規定が優先するとしても、予告期間をあまりに長い期間に設定している場合、当該予告期間の規定は、公序良俗違反などで無効となり得ると考えられています。