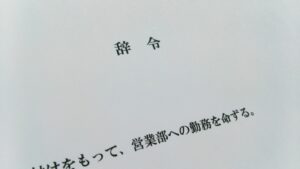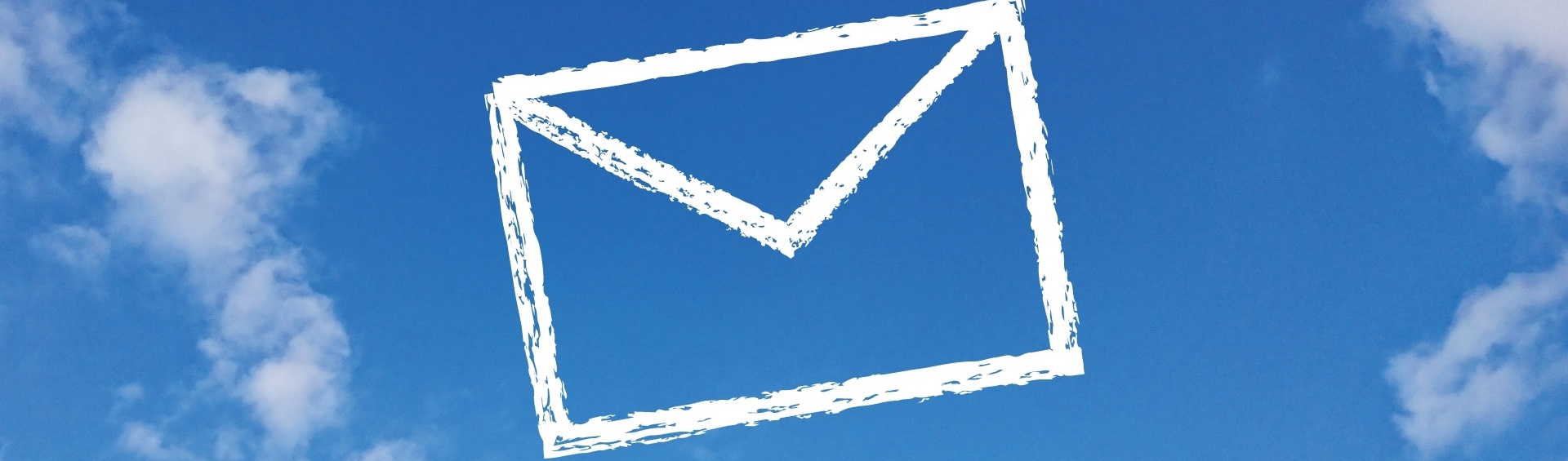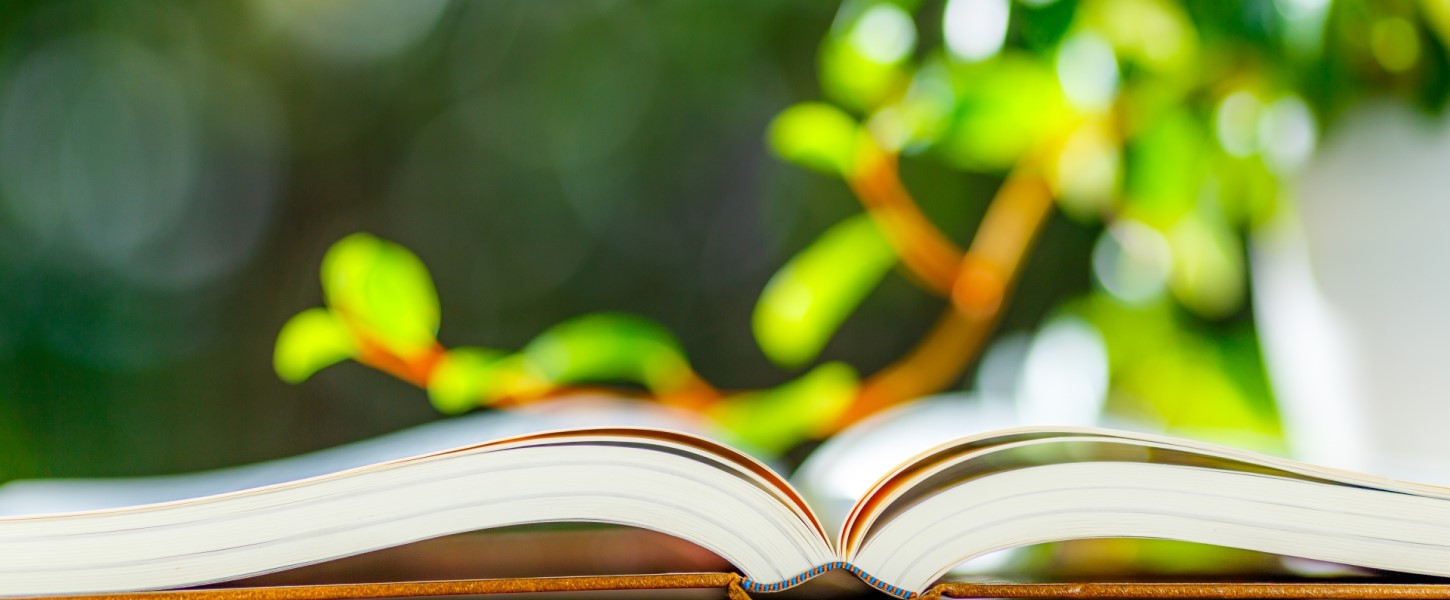著作権法と不正競争防止法は知的財産権に関する法律と位置づけられていますが、特許権、意匠権などの産業財産権とはどのように異なっているのでしょうか。
目次
著作権法と不正競争防止法について
著作権に関する法律として著作権法が、標識、営業秘密などに関する権利を保護する法律としては不正競争防止法が制定されています。
これらの法律で保護されている著作権および標識、営業秘密などに関する権利は種苗法に定められる育成者権とともに産業財産権に含まれない知的財産権に位置づけられます。
このことにつきましては、下記の記事で扱っていますので参考にしていただければと思います。
著作権法について
著作権法により保護される権利について
著作権法は、下記に引用する17条1項において、「著作者」の同法21条~28条に規定する権利を「著作権」と定義しています。
尚、同法17条1項は、著作権法とともに著作者の「著作者人格権」という権利を定めています。
(著作者の権利)
著作権法第17条
第十七条 著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。
2 著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。
更に、下記に引用した著作権法1条の文言、同法第4章の標題が「著作隣接権」とされていること、および第4章の条文などから著作権に隣接する権利としての「著作隣接権」も規定されていることがわかります。
(目的)
著作権法第1条
第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
このように、著作権法により、
・著作権
・著作者人格権
・著作隣接権
の3つの権利の保護がなされていることがわかります。
著作権について
上記に述べましたように、著作権法では21条~28条に規定する権利を著作権と定義しています。
そして、下記引用の著作権法2条1項2号から著作者とは「著作物を創作する者」のことであり、同項1号から「著作物」とは「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」であることがわかります。
そこで、「著作者」とは、思想又は感情を創作的に表現した文芸、学術、美術、または音楽の範囲に属するものを創作する者ということになります。
(定義)
著作権法第2条
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
二 著作者 著作物を創作する者をいう。
(以下省略)
そして、次に著作権法の21条~28条をみますと、
・複製権(21条)
・上演権及び演奏権(22条)
・上映権(22条の2)
・公衆送信権等(23条)
・口述権(24条)
・展示権(25条)
・頒布権(26条)
・譲渡権(26条の2)
・貸与権(26条の3)
・翻訳権、翻案権等(27条)
・二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(28条)
等に関する著作者の複数の権利を束にしたものが権利の内容であり、著作者のこれらの権利の総体が著作権であることがわかります。
尚、著作権は全部あるいは一部を譲渡することができます(著作権法61条1項)。
著作者人格権について
著作者人格権とは、著作者が取得する権利で、公表権、氏名表示権、同一性保持権がその権利内容となります(著作権法18条~20条)。
著作権と異なり、著作者人格権は一身専属的で譲渡することはできません(同法59条)。
著作隣接権について
著作隣接権は、著作物を生み出す著作活動そのものではなく、成立した著作物を公衆に伝達する行為に付与される権利です。
・実演家の同一性保持権、氏名表示権の実演家人格権
・実演家の録音権、録画権等
・レコード製作者の複製権、送信可能化権等
・放送事業者の複製権、再放送権等
・有線放送事業者の複製権、放送権等
が規定されています。
これらの権利に関しては一定範囲で譲渡が可能ですが、実演家人格権は一身専属的で譲渡できません。
産業財産権との相違について
著作権法は、文化の発展に寄与することを目的としており、産業の発達に寄与することを目的する特許権などの産業財産権とは異なります。
そして、産業財産権は設定登録により権利が発生するのに対し、著作権は創作の時に権利が発生するのであり、設定登録することが要件となっていません。登録制度はありますが(著作権法75条~78条の2等参照)、権利の公示、権利移転の安全性確保のために用いられるものであり、権利発生の要件ではありません。
不正競争防止法について
他の知的財産法との相違
不正競争防止法も知的財産権に関する法律(以下「知的財産法」といいます。)であると位置づけられています(知的財産基本法2条等参照)。
しかしながら、他の知的財産法が具体的な権利内容を条文で直接定義しているのに対し、不正競争防止法は、下記に引用する同法1条および2条からも分かるように、その保護される標識、営業秘密などの権利を条文で直接定義するのではなく、保護する権利への侵害行為を「不正競争」として不正競争の類型を条文で定め、不正競争に対する差止請求権、損害賠償請求権あるいは刑事罰を規定することにより不正競争の防止をすることにより知的財産権の保護を図っています。
(目的)
第一条 この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。(定義)
不正競争防止法
第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
一 他人の商品等表示・・・
二 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為
(以下省略)
不正競争防止法により保護される知的財産権について
不正防止法2条1項の1号~22号では、各々下記を侵害する行為を不正競争と規定しています。カッコ内は同項の号を記しています。
・商品等表示(1号)
・商品等表示(2号)
・商品の形態(3号)
・営業秘密(4~10号)
・限定提供データ(11~16号)
・一定の影像、音、プログラムその他の情報の記録(17、18号)
・ドメイン名(19号)
・商品等の原産地、品質、内容、製造方法、用途、数量等の表示(20号)
・営業上の信用(21号)
・代理人等の商標(22号)
したがって、これらに関する権利の一部が不正競争防止法により保護されている知的財産権と考えることができます。
上記列挙からも分かりますように、不正競争防止法の保護対象は多岐にわたり、特許法、著作権法など他の知的財産法の保護対象外の権利を包括して保護しているものともとらえることができます。